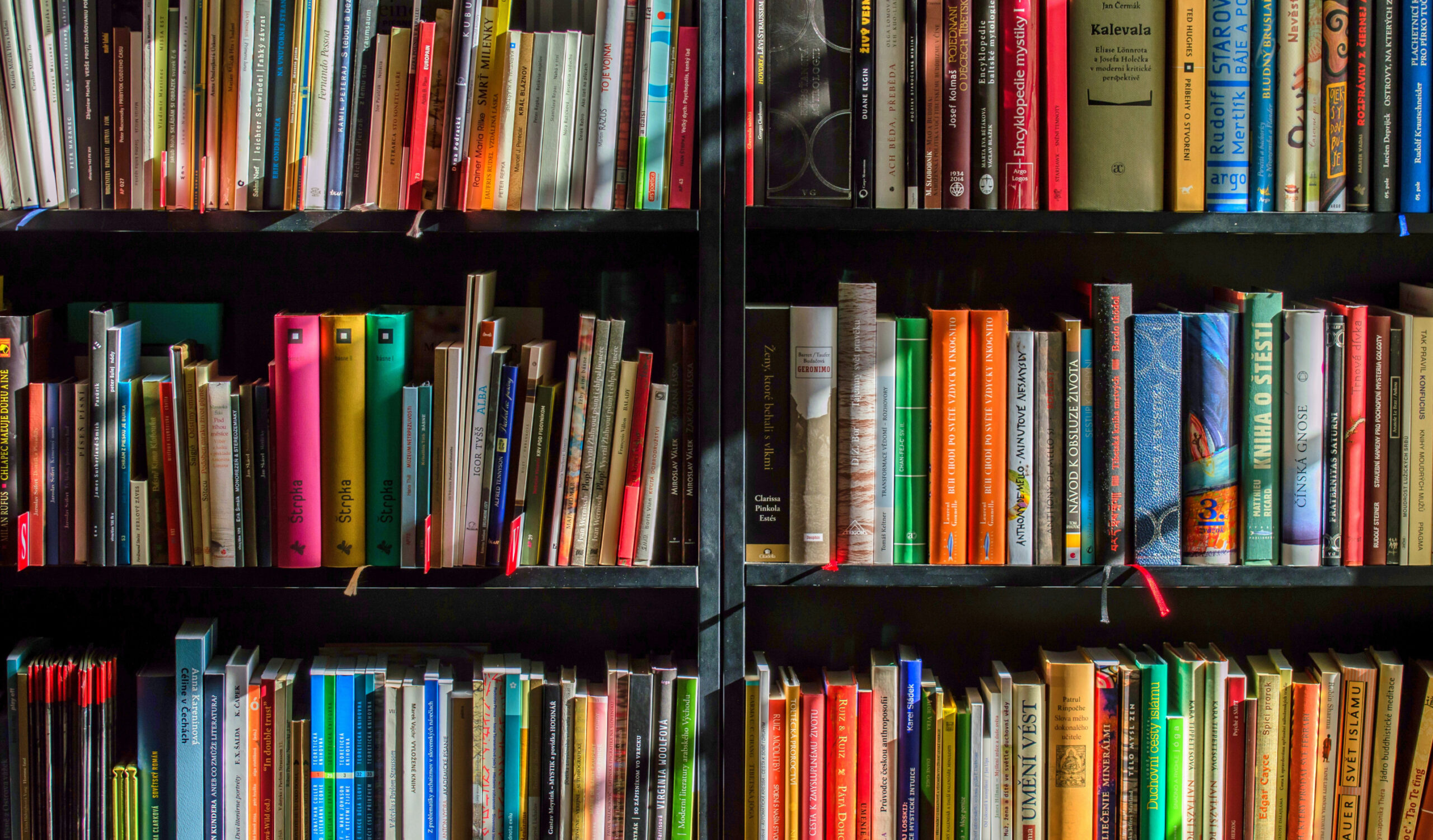今回は【落ちる子と伸びる子 分かれ道はいつ?親が気づくべきサイン】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもが小学生となり、学校でテストを受けるようになると、親は授業を理解できているか、テストの点数の推移、そして周りの子の様子を気にするようになります。
そして、学年が上がれば上がるほど、その悩みは増えていきます。
とくに小学生から中学生になると順位がハッキリするだけでなく、高校受験が迫ってくるため、【子どもの学力=子どもの未来】となってしまいます。
しかも、成績の低下というのは【ここが分岐点でした】とスパッと切り取れるほど明確なものではないことが多いです。
なんとなく、【去年までは成績も良く、やる気もあったのに…】【テストがあったのかどうか喋らなくなった】【宿題も雑になってきた気がする】という小さな変化を感じ取ることの積み重ねで気がついていきます。
こんなふうに、小学校4年生、5年生を境に、子どもの学力や学習姿勢に不安を感じはじめるご家庭は少なくありません。
ただし、子どもはある日突然ガクッと成績が下がるわけではありません。
その前には必ず、【子どものちょっとした変化やサイン】が現れます。
ところが多くの家庭では、これを【一時的なもの】として見過ごしてしまいがちです。
重要なのは、【分かれ道】に差しかかる前に、親がその兆候に気づけるかどうかにかかってきます。
その一方で、伸び続ける子どもは【見えない学力に必須な力】が家庭で育っています。
しかも、そういうタイプの子達が決して【目立つ優等生】とは限らないこともあります。
【まさか、あの子があの高校に合格したの?!】というケースも多くはありませんがあります。
成績だけでは測れない、思考力、感情のコントロール、学びに向かう姿勢などの土台が、時間をかけて形成されていき、人知れず学力の静かな伸びを見せているのです。
では、【落ちる子】と【伸びる子】は、いつ、どこで差がつくのでしょうか?
実はその分かれ道は、小学校の時期にすでに始まっています。
しかも、点数だけを見ていると親が気づかないケースも珍しくありません。
子どもたちは、表面的には同じように見えて、内側で大きく分かれていく時期があります。
学習内容が【覚える】から【考える】へと質的に変わっていく小学3年生から4年生、そして、思春期と学習の自立期が重なる4年生から5年生という2つのタイミングは、将来に向けて大きな分岐点になります。
そこで今回は、成績が落ちる子が出す3つのシグナル、【伸びる子】に育てるための家庭習慣、そして親ができる、日々のアクションについて、ご紹介していきます。
見かけの成績に騙されない!『できる子』の落とし穴
まず、テストの点が良い=安心、ではないと肝に銘じましょう。
小学生のうち、とくに低学年から中学年にかけて、【テストの点が良い】ということが、学力の安定を示すサインだと受け取られがちです。
しかし、ここに落とし穴があります。
テストの点が良いからといって、その子の考える力が育っているとは限らないのです。
たとえば、学校のテストは基本的に記憶型の問題が多く、出題のパターンもある程度決まっています。
つまり、覚えていれば点が取れる形式が多いのです。
とくに勉強が丁寧で、真面目な子ほど【求められたことにきちんと答える】ことが得意です。
しかし、これは再現力であって、応用力や思考力とは別物です。
高学年になり、中学進学が近づくにつれて、学びの性質は【考え方】や【理由】を求めるものに変わっていきます。
そうなったとき、これまでのような【覚えて解く勉強法】では、対応できなくなる子が出てきます。
塾でも、実際にそういうタイプの子が毎年、一定数いました。
親が【うちの子はできる方だから】と安心していると、思考の力を育てる機会を逃すことにもなりかねません。
今点が取れているかではなく、【なぜそう考えたのか?】【この解き方は他にもある?】と、思考の深さに目を向ける視点が大切です。
そして気をつけて欲しいのが、親の過保護な伴走が子どもの自立を妨げるということです。
成績が良い子どもには、親の手厚いサポートが背景にあることも多いものです。
宿題の声かけ、ドリルの採点、勉強スケジュールの管理などなど、つい【一緒にやってあげた方が早い】と思ってしまいがちですが、実はこの丁寧な伴走が、子どもの自立を遅らせてしまう原因になっている場合もあります。
中学以降、学習量も内容も一気に複雑化します。
すべてを親が見てあげることは物理的に難しくなります。
さらに、定期テストや実力テストでは、【自分で理解し、整理し、実行する力】が問われます。
つまり、自分の勉強を自分で動かす力がないと、たとえ成績優秀でも伸び悩み始めるのです。
たとえば、親がミスを先に見つけて指摘する、つまずいた問題をすぐに解説してあげる、間違ったときに正解を教えてしまうなど、【よかれと思った介入】が、子どもの【考える機会】【自分で立ち直る機会】を奪ってしまうことになるのです。
成績がいいうちにこそ、【わからない】【間違えた】という経験をきちんと自分で処理できるようにしておくことが大切です。
小さな躓きを、自分でどうにかする練習のチャンスと捉えましょう。
また、【よくできる子】ほど気をつけたいのが、まじめさの罠です。
親の子どもの頃の同級生、そして我が子のクラスの中にも【真面目で言われたことはしっかりやるタイプ】の子どもがいます。
もちろん、この姿勢自体は素晴らしいのですが、【指示待ち】【正解することが良いことだという固定観念を持つ】になってしまうと、後々伸び悩みの原因になります。
こういうタイプの子は、枠の中で完璧にやろうとする反面、自分で考えることや、正解のない問いに向き合うことに不安を感じやすいです。
小学校ではそれでうまくいっていても、中学以降の【思考型の学び】に移行する段階で立ち止まってしまうことがあります。
たとえば、作文や自由研究でテーマを決めるとき、【どうしたら褒められるか】【何を書けばいいの】と聞いてくるような場合は、要注意サインです。
このようなことを子どもが言ってきたら、【自分で考えたことに価値がある】【完璧じゃなくても、自分の意見を出してみよう】ということの大切さを伝えていくようにしましょう。
間違えることを恐れず、未知の問いに挑戦する力は、テストの点数では測れない本当の意味での学力の土台になります。
成績が良いうちから【考える習慣】【自分で学ぶ力】【間違いを受け入れて立て直す力】を育てておくことが、将来の安定した学びにつながります。
分かれ道は小学校の後半にある
さて、子どもが小学生となり学校の勉強をすんなり理解できなくなる、テストの点数で高得点が取れなくなってくるタイミングが小学3年、4年生頃です。
小学校6年間を二つに分けると、折り返し地点、
ちょうど、学びが【考える力】を要するようになり、考えるのを苦手とする子は授業中に【わからない】と感じることが徐々に増えていきます。
低学年での学びの雰囲気が変わり、小学校高学年、そして中学へとつながる抽象的な概念の度合いが強まる前の橋渡し期間でもあり、暗記中心から思考型へとシフトし始める時期です。
たとえば算数では文章題や図形問題、国語では登場人物の心情や文の構成を読み取る力が求められます。
この段階で問われるのは、【答えを出す力】と同じように【どう考えるかというプロセス】が重視されていきます。
この時期に伸びる子は、【なぜそうなるの?】【どうしてこう思ったの?】という問いに対して、自分の言葉で説明しようとします。
一方、ここで躓く子は、【覚えたことを当てはめる】という学びの型から抜け出せず、初見の問題や少し捻られた問いに手が止まるようになります。
たとえば文章題を読んでも状況をイメージできない、語彙力が不足していて文章の意図がつかめない、といったケースです。
これらは見逃しやすい【考えることを拒否してしまう】ことにつながります。
単純ですぐに分かる問題しか取り組まなくなるため、勉強量の割には伸びにくくなるという悪循環に陥ってしまいます。
そのままにしておくと、高学年や中学進学後に大きな差につながります。
親としてできることは、子どもが考えるプロセスに関心を持ち、問い返す習慣をつけることです。
【答えは合ってるけど、どうやって考えたの?】【違うやり方ってあるかな?】と、考えを言語化する機会を与えることで、思考力の芽を育てていくことができます。
また、子どもにとって第2の分かれ道と言えるのが小学5年生から6年生です。
高学年になると、求められる力はさらに変化し、自分で学習を組み立てる力、つまりは自走力の有無で結果も変わっていきます。
この時期になると、授業の難易度が上がり、英語も加わります。
単に言われたことをやるだけでなく、【自分で何を・どれくらい・いつやるか】を考えて動けるかどうかが、後の中学生活を大きく左右します。
成績が安定して伸びている子は、自分で学習計画を立てたり、苦手な部分を自分で分析したりする習慣が身についています。
宿題以外にも、間違えた問題を解き直したり、分からないことを調べ直したりと、【自分のペースで学びを回す力】があります。
反対に、親に言われないと動かない、自分で考える前にすぐ【わからない】と言う、やった内容を振り返らない…といった姿勢のままだと、中学に入ってから大きく崩れます。
なぜなら中学では、【量】と【質】の両方の学習をこなさなければならないからです。
難化する勉強を確実に理解するには学習量は必要ですし、ただ問題を解けば力がつくわけでもないので質も意識して、部活と両立させながら家庭学習を進めていく必要があります。
中学生に向けて、小学校高学年からはToDoリストや学習記録の習慣を取り入れたり、週末に親の子【一週間の振り返りタイム】を設けたりすることで、自走力を育てる基盤をつくるのが理想的です。
大切なのは、小学校の折り返し地点を過ぎてからは親誘導から脱却し、【親はサポーターになる】と立場を変えることです。
そして、子どもが成長してから見逃してはいけないサインがあります。
【まだ小学生だから大丈夫】【うちは成績いいし】と思っている間に、実は子どもが【成績が落ちるルート】に入り始めていることがあります。
テストの点数に現れない見えないサインを見逃さないことが、親の大切な役割です。
たとえば、【なんとなく宿題をこなしているが、中身が伴っていない】【質問されたときに自分の考えが言えない】【間違えたときに原因を深掘りしない】【正解ばかり求めてくる】という言動のすべては、思考力や自走力がまだ弱いサインです。
また、子どもが【質問をしない】【自分の間違いを隠そうとする】【やっているふりが上手くなってきた】といった行動が見られたら要注意です。
やっている風に騙されず、本当に学びが身についているかどうかを見極める目が親には求められます。
親としてできるのは、叱りたい気持ちをグッと堪えて、【どう考えた?】【どうすればよかったと思う?】と問いかけ、学びの内側に関わっていくことです。
この働きかけが、学力の質を育て、将来の伸びにつながっていきます。
伸びる子が家庭で身につけている『3つの習慣』
ところで、小学3年生、4年生頃から学力差が出始める時期になっても伸びる子というのは【考える力】があり、自分の考えを口にすることに抵抗感がない特徴があります。
そしてその考えたことを言葉にして説明できる力があることです。
この力を育てるカギは、日々の親子の対話次第になります。
【どう思った?】【なんでそう思ったの?】【他の考え方はあるかな?】と、考えたことを引き出す問いかけを日常的にしている家庭では、子どもが自分の頭で考え、それを整理して伝える力が自然と育ちます。
とくに、正解のある問いだけでなく、答えのない問いについて話し合うことが有効です。
たとえば、読書の感想を共有する場面や、ニュースを見たときの意見交換などが挙げられます。
親が答えではなく、子どもの考え方に関心を持つこと、耳を傾けることで、子どもは安心して自分の思考を言葉にする習慣がついていきます。
説明する力は、理解の深さを映す鏡です。
口に出して言えるということは、それだけ理解が整理されているということを意味しています。
さらに大切なことは、【言われたからやる】ではなく、【自分で決めてやる】という意識を早いうちから持てるかどうかが、自走する学びの分かれ道になります。
伸びている子どもは、学習の内容やペースを自分で管理する力を少しずつ身につけています。
たとえば、今日はどの教科をどれくらいやるか、どこが苦手か、どの順番で進めると集中できるかなど、自分なりの工夫をしながら学習を動かしています。
これを家庭で育てるには、ToDoリストや学習記録、週単位の振り返りなどを一緒に取り入れるのがおすすめです。
けれど、親が【こうしなさい】と押し付けるのではなく、子ども自身に決めさせ、親はサポート役に徹することが大切です。
小さな成功体験を重ねることで、子どもは【自分はできる】【自分で動かすのが気持ちいい】と実感し、自ら学びに向かう姿勢をつくっていきます。
この自走力は、学年が上がるほど必要になる力であり、中学、高校、大学と長く役立つ一生もののスキルです。
そして、【家庭の雰囲気】が子どもを伸ばします。
子どもが伸びるかどうかを決定づけるのは、意外にも【家庭の空気感】です。
家内安全という言葉がありますが、家の雰囲気が落ち着いていると子どもは余計なことで悩まずに済みますし、勉強そのものへの意欲や学習習慣は、家庭内の価値観や会話のなかで自然と形づくられていきます。
たとえば、【なんでこんなミスしたの?】と点数ばかりを気にする家庭では、子どもは失敗を恐れ、本質的な学びに向き合いづらくなります。
私も小さい頃に経験していますが、両親がいがみ合っていると、子どもはオロオロして勉強どころではありません。
一方で、【ここ、よく考えて工夫したね】【間違えたところを自分で気づけたのはすごい】といった声かけがある家庭では、点数よりもプロセスが大事だという価値観が育ちます。
さらに大事なのは、親自身も【学びに前向きな姿勢】を見せることです。
本を読む、ニュースを一緒に見て話す、自分が学んでいることを話題にするなど、大人が楽しそうに学んでいる姿は、子どもにとって何よりの教材になります。
つまり、【勉強しなさい】と言葉で伝えるよりも、学ぶことを大事にしている空気を日常的につくることが、最も自然で効果的な教育なのです。
成績が落ちる子と伸びる子の差は、今の成績ではなく、【どう学んでいるか】という姿勢にあります。
小学3年生から6年生の間に、考える力や自分で学習を動かす力が育っているかどうかが、大きな分かれ道です。
親ができるのは、教えることではなく、子どもの思考や行動を引き出し、見守りながら育てていくこと。
テストの点に一喜一憂するのではなく、【この子は自分の力で伸びていけるか?】という視点を忘れずに、日々の関わりを見直していきましょう。