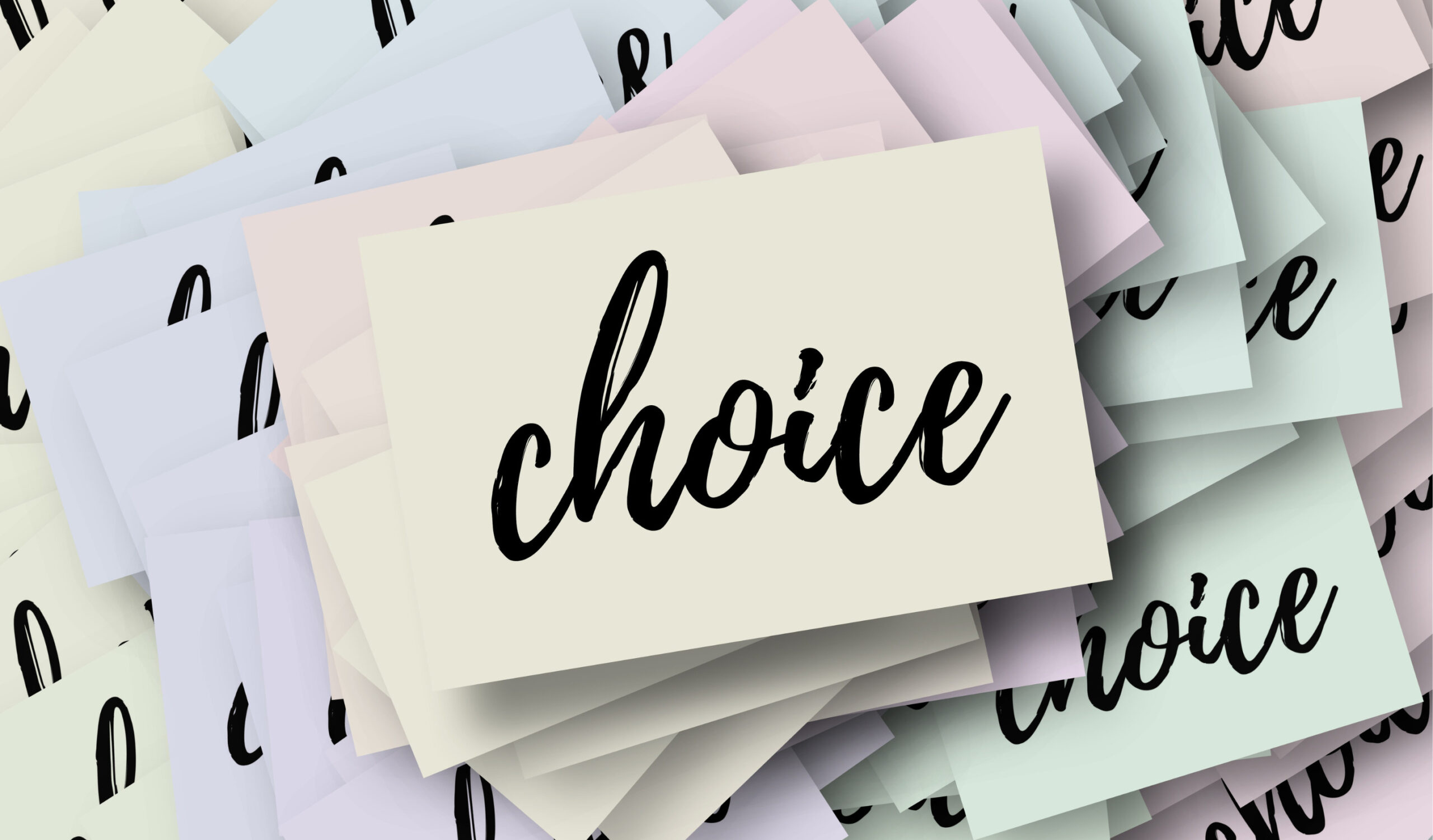今回は【塾なしでは難しいのか 進学校を目指す子に塾が必要とされる理由】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
親世代の頃から進学校を目指す子ほど、中学生になると塾通いをするようになっていました。
塾に通うというのは大都市圏や都市部の家庭だけの話ではなく、地方でも【進学校を目指すのであれば塾なしでの合格は難しい】と考えている親は少なくありません。
私が中学生の時は偏差値60以上の高校を目指す同級生はほぼ例外なく塾に通っていました。
一昔前、しかも地方においては【塾に通うライン】というものがあったと感じています。
時は流れ、少子化が進み一人の子どもにかけられる教育費も増えたことや、個別指導タイプの塾が普及したこともあり、必ずしも上位校を目指す子だけが塾に通うわけではなくなってきました。
私も幅広い学力層の子と出会ってきましたし、自分の中学生時代とは変わってきているんだなということを感じました。
都会でも地方でも塾の存在感は増しているわけですが、その一方で、【インターネトで検索したらノー塾で最難関校に合格した親子がいる】【通信教材だけで最難関大学に合格した子もいる【塾に行かないと合格できないっておかしくない?】と疑問を抱く親も少なくないです。
確かに、ノー塾で素晴らしい進路進学という結果を残している家庭もありますが、中学受験、高校受験そして大学受験のそれぞれの各段階での母数と、成功した人の人数を考えると、詳しく調べなくてもその成功例がかなりレアなものだということが分かると思います。
そもそも、勝手に子どもが勉強するというところに持ってくるまでが大変ですし、我が子がもの凄く学力スキルが高くて、しかも自走する子になる保証もありません。
そうなると、受験学年が近づけば教育産業の力を借りる選択をする方が【安全手形】と考えるのは自然なことだといえます。
ちなみに、我が家の子ども①②の周囲にいる優秀な同級生たちの中で、完全なるノー塾で【トップ高校レベル】または【難関大学以上に進めそうな子】は1人、2人くらいです。
地方でもこういう状況です。
できることなら、教育費を抑えて子どもの合格を勝ち取りたいところですが、なかなか現実的には【塾抜きで受験が語られることはない】が圧倒的に多いです。
ただし、なぜ、これほどまでに塾が必要とされているのか不思議な面もあります。
そこで今回は、進学校を目指す子ほど塾に通っている理由をご紹介していきます。
学校の授業との“ギャップ”があることも
まず、学校の授業と入試問題のギャップがあり、塾に通うことを選択している家庭もあります。
その背景には、単なる【親や子の安心感】や【周囲で通っている子が多いから】という理由だけでなく、学校と受験のレベルの差があるという理由もあります。
教育熱がそれほど高くない地域では、【学校の授業と実際の入試との間に大きなギャップ】が存在しています。
これは、私が塾で仕事をしている時も、子育てを通じて違う学区に住んでいるママさん達の話を聞いても感じましたが、教育熱の低い地域では難易度の高い問題がテストで出題されることはほぼありません。
授業や定期テストの内容は、教科書に沿った基本事項、ワークの内容や事前に先生が配布したプリントの内容がほぼそのまま出るということもあります。
思考力や応用力を問うような問題は少なく、テストもしっかり点数を取らせるという設計になっていることが多いため、成績が良くても【本当の学力】が見えにくいという課題があります。
これは決して学校の指導が悪いということではなく、その地域のニーズ、生徒の学力レベルを踏まえての公教育としての公平性や標準化が前提となっているため、深い学びや高難度の問題演習を出すということは誰の得にもならない、為になるのはその学校の1位であり、トップ高校を目指せる学力のある子くらいといのが実情です。
一方で、進学校を目指す場合は私立であれば問題の難易度が当然ながら高く、出題傾向も幅広く、記述力や論理的な思考力を問う設問が多くなっています。
地方の公立高校であっても、上位校になればなるほど、難易度の高い問題での正答率が合否を左右する決定打になります。
つまり、【中学校の授業を真面目に受けていれば大丈夫】というレベルでは、合格に届かないケースも少なくありません。
そのギャップを埋める存在として、多くの家庭が頼っているのが塾です。
私も、荒れている中学に通い、その学校で学年1位という生徒を担当したことがありましたが、【学校のテストがトンデモナク簡単】と嘆いていたのを覚えています。
こういう子は、塾に来て進学校を目指す子が解いている問題を解いたり、切磋琢磨する環境に身を置いて学校とのギャップを埋めるということをしていました。
塾では、入試に特化した教材やカリキュラム、過去問分析に基づいた対策授業が提供されており、【受験仕様の学び】が体系的に用意されています。
また、模試や演習を通じて、自分の立ち位置や苦手分野を客観的に把握することができる点も大きなメリットです。
もちろん、すべての子が塾に通わなければならないわけではありません。
しかし、塾の存在が“あって当たり前”となっている背景には、学校と入試の間にある現実的なギャップと、それを埋める手段としての役割があるのです。
進学校を本気で目指すなら、そのギャップをどう乗り越えるかを家庭でも意識することが求められています。
周囲との競争意識で学力が底上げされる
さて、受験を見据えて塾に通う子どもが多い背景には、【わかりやすい授業】や【受験情報の提供】だけでなく、塾という環境そのものが持つ競争の空気が、受験を控える子どもにとって大きな影響を与えています。
とくに進学校を目指す子にとって、周囲のライバルだけど仲間という同級生達の存在が、何よりの刺激となります。
塾には、同じように高い目標を持って努力している子たちが集まります。
そうした中で勉強することは、単に知識を得るだけでなく、【自分も負けていられない】【もっと頑張ろう】と自然と意識を高め合う環境を作り出します。
家庭で一人で机に向かっていては得られない、【緊張感】と【仲間の存在】が、子どもたちの内面に良い刺激を与えるのです。
我が家の子ども①も中学3年生の夏休みは部活が引退したこともあり、塾の自習室に缶詰めになって同じ高校を受ける同級生、ライバルの子達と競い合うように勉強をしていました。
家だけでは中学3年の最大のヤマ場である夏休みにこうした気持ちで勉強できなかったと思います。
また、塾で扱われる問題のレベルも、学校に比べてワンランク上であることが多く、【このくらいは解けて当然】という基準感覚が自然と身につきます。
これは子どもにとっては重要なポイントです。
受験本番では、受験生の中でどれだけ頭一つ抜けられるかが勝負になります。
そうした時に、高い基準で物事を考える習慣があるかどうかが、大きな差となって表れます。
さらに、塾では定期的に実施される模試や順位の発表などを通して、自分の立ち位置を客観的に把握できる機会が多くあります。
これは家庭学習ではなかなか得られない価値です。
点数や偏差値だけではなく、【自分より少し上にいる子がどんな勉強をしているのか】【どうすればそのレベルに近づけるのか】といったリアルな比較と気づきが、学力の底上げを加速させます。
もちろん、競争がプレッシャーになる子もいます。
しかし、適切なサポートや声かけがあれば、競争意識は成長のエンジンに変わるのです。
ただ成績を上げるためだけではなく、切磋琢磨しながら努力する姿勢を育てる意味でも、塾の存在は大きな役割を果たしています。
【塾に通わせるべきか】と悩む方も多いと思いますが、こうした家庭では整えることができない【環境の力】を活かすという視点で、子どもにとって最適な学びの場として塾通いを選択する家庭が多いです。
「計画管理」と「情報戦」の存在
ところで、受験を控えた子どもにとって、塾が果たす役割は【勉強を教わる場】だけではありません。
むしろ近年では、家庭だけでは対応しきれない【受験全体のマネジメント】を担う存在として、塾の重要性が高まっています。
そのひとつが、学習計画の管理と受験情報のサポートです。
まず、入試に向けた年間の学習計画や、志望校別の対策は、非常に複雑で専門性を要します。
特に複数教科をバランスよく進め、学力を段階的に伸ばしていくためには、長期的な視点と緻密な計画が必要です。
しかし、日々の学校生活や部活があるなかで、それを親だけが完全に設計・管理するのは現実的に難しいのが実情です。
その点、個別指導塾では志望校ごとの出題傾向や過去問分析に基づき、どの時期に何を重点的に学ぶべきか、個別のプランを立ててくれるのが大きな強みです。
集合クラスでも相談することで生徒に合わせた勉強の取り組み方や計画の立て方などをアドバイスしてくれることもあります。
加えて、塾によっては定期的な模試や復習テストを通じて、子どもの学習状況を客観的に把握し、必要に応じて軌道修正してくれる体制も整っています。
とくに直前期の対策や弱点克服の指導は、家庭では手が回らない部分をしっかりと補ってくれます。
また、塾にはもうひとつ大きな役割があります。
それは、【情報戦】とも言える親にとっては貴重な受験情報の提供です。
進学校を目指すにあたっては、併願校の選び方、校風、内申点の扱い、倍率の動向や過去に在籍した生徒の合否と成績を比較した【合否の確率】など、膨大かつ最新の情報が必要です。
これらを一から家庭で調べ、判断するのは容易ではありません。
その点、塾には各学校に関する詳細なデータと実績があり、合格可能性や受験スケジュールの組み方まで具体的にアドバイスしてもらえるため、受験全体の見通しが立てやすくなります。
親にとっての精神的な支えにもなり、迷いなく受験に集中できる環境づくりにもつながるのです。
受験は、単なる勉強量だけでなく、【何を、いつ、どれだけやるか】という戦略と、【どういう情報をもとに判断するか】という戦術の勝負でもあります。
塾は、その戦略と戦術の両面で家庭を支える受験の伴走者として、非常に頼もしい存在と言えるでしょう。
塾は必須ではありませんが、通うことで得られることも多いのも事実です。
進学校を目指す子どもにとって、塾は【必ず通わなければならない場所】ではありません。
しかし、限られた時間で確実にレベルアップし、同じ目標を持つ仲間と競い合いながら成長できる環境として、多くの子が塾に頼るのは自然な流れとも言えます。
大切なのは、【塾に通わせるかどうか】で最初から考えるのではなく、自分の子どもにとって受験に立ち向かうために【塾に通った方がメリットが多いか】という視点で選択することになります。