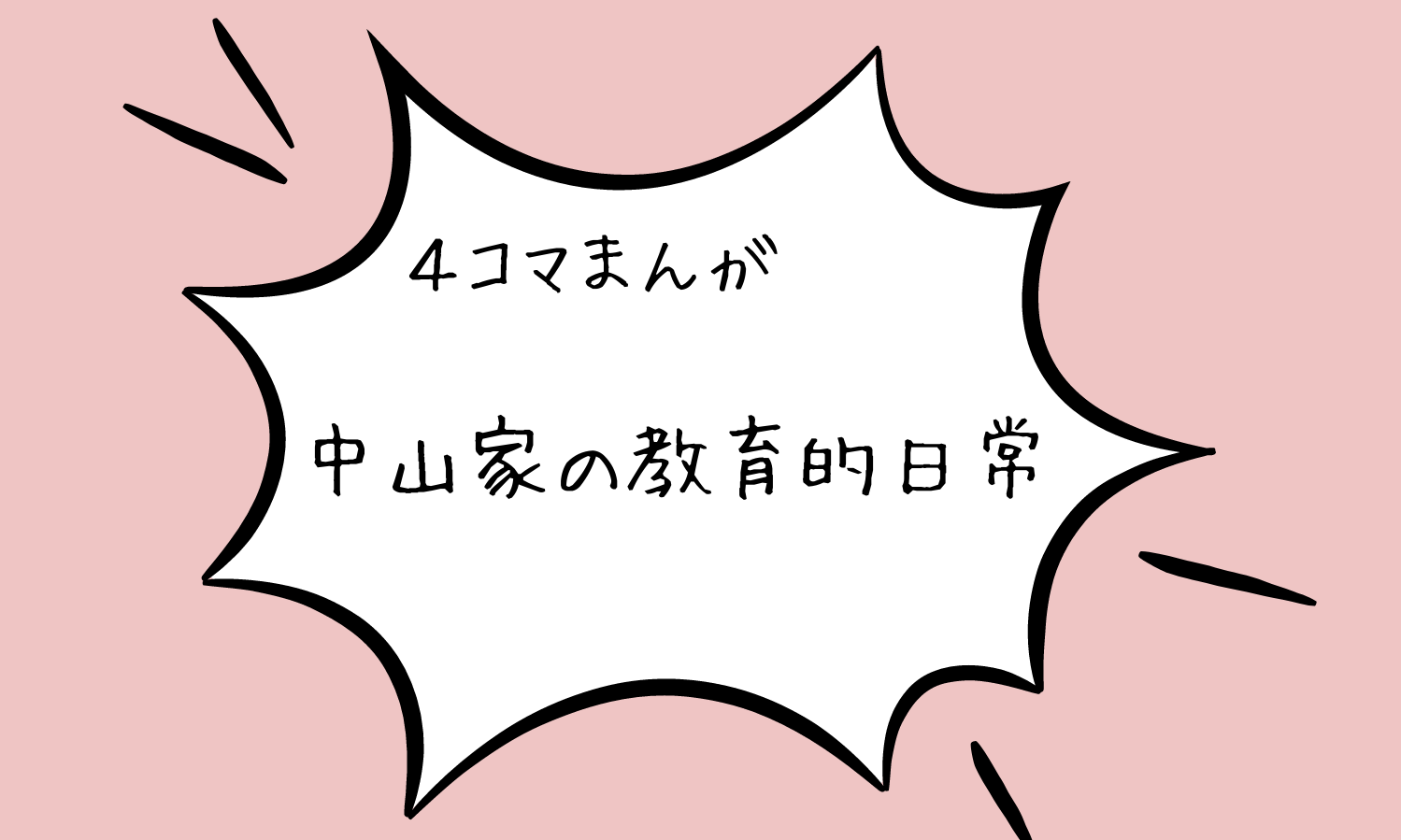今回は【我が子が小学校で優等生と呼ばれるために今すべき7つのこと】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【先生によく褒められる子】【学級で信頼されている子】【勉強も行動もきちんとしている子】。
いわゆる優等生と呼ばれる小学生には、どこか共通する空気があります。
周りの子どもや先生から信頼され、自然と頼りにされるような存在。
親としても、【わが子にもそんなふうに育ってほしい】と願うのはごく自然なことです。
ですが、優等生というと【もともと頭の良い子】【育ちのいい子】というイメージを持ってしまいがち。
実際には、そうした特別な子だけが優等生になるわけではありません。
そこで今回は、わが子が小学校で優等生と呼ばれるようになるために、今すべき7つのことをご紹介します。
【うちの子、少しずつ変わってきたかも】
【前より学校の話を楽しそうにするようになった】
そんな変化を実感できるような、すぐに取り組める具体策をまとめました。
今日からできることばかりですので、ぜひご家庭で取り入れてみてください。
① 生活の【基本リズム】を整える
優等生と呼ばれる子どもは、例外なく【生活が安定している】ことが多いです。
つまり、早寝早起き・朝ごはん・時間通りの支度といった、生活の当たり前がきちんと習慣になっているということです。
人間は、心と体が安定して初めて思考力・集中力・感情コントロール力を発揮できます。
朝バタバタしている、夜更かししている、食事をいい加減に済ませている。
そんな状態では、学校で100%の力を出せるはずがありません。
【うちの子、学校で落ち着きがないみたい】と感じている親御さんほど、生活習慣をまず見直してみることが大切です。
チェックポイントを挙げるとすると、
・就寝時間は21時前後になっているか
・朝の支度に余裕があるか
・朝ごはんを毎日しっかり食べているか?
これらが整ってくると、子どもの表情が変わり、先生方からの評価も自然と上がりやすくなります。
②【挨拶・返事・ありがとう】は親が見せる
優等生の子に共通するのが、人との基本的な関わり方がきちんとしていることです。
とくに、【挨拶】【返事】【感謝の言葉】は、その子の印象を大きく左右します。
たとえば朝、教室に入ったときに元気に【おはようございます】と言える子。
先生に何かしてもらったときに【ありがとうございます】と自然に言える子。
こうした子は、それだけで丁寧で感じのいい子という印象を与えます。
これらの習慣は、親の姿勢がそのまま反映される部分です。
家庭内での【ありがとう】【おはよう】【はい】のやりとりが、無意識のうちに外でも出せる力になります。
親が意識したいこととして挙げられるのは以下の通りです。
・自分から先に挨拶する
・子どもの行動に対しても【ありがとう】と伝える
・大人にも子どもにも分け隔てなく丁寧に接する
こうした家庭での言葉づかいが、そのまま学校での優等生らしさに繋がります。
③ 自分のことは【自分で】やらせる
優等生になるには、自立した行動ができることが大きなカギになります。
自分の持ち物を自分で管理できる、忘れ物を自分でチェックできる、提出物を出し忘れない。
これらはすべて日々の習慣で身につきます。
とはいえ、最初から完璧にできる子はいません。
親がつい【ちゃんとランドセルに入れた?】【これ忘れてない?】と先回りしてしまいがちですが、それでは自立のチャンスを奪ってしまいます。
大切なのは、【気づくきっかけを与えて、任せること】。
子どもに考えさせる習慣をつけると、やがて【自分でできる】自信が生まれ、それが行動力や責任感に変わっていきます。
おすすめの工夫としては、
・チェックリストを一緒に作って、毎朝確認する
・忘れ物をしても親が届けないルールにする
・できたときはしっかり褒める
依頼心がない、自分でできる子は、先生の信頼を集めやすくなります。
④ 感情のコントロールを教える
学校生活では、【我慢】【譲る】【言い方を工夫する】といった感情のコントロール力が求められます。
優等生の子は、こうした気持ちの折り合いが自然とできる子が多いです。
とはいえ、子どもにとって感情の調整は難しいものです。
親が感情的になって叱ってばかりでは、子どもも感情を爆発させやすくなります。
まずは家庭の中で、
・怒ってもいいけれど、どう伝えるかを一緒に考える
・【今イライラしてるね】【悔しいよね】と気持ちに共感する
・落ち着く方法(深呼吸・ひとりの時間など)を一緒に考える
このように、感情との付き合い方を言語化しながら伝えることで、子どもは【感情を出していいけれど、出し方を考える】ことができるようになります。
心が安定している子は、先生からも【安心して任せられる】と感じてもらえる存在になります。
⑤ 学習習慣を短く・毎日で整える
優等生の印象を左右する大きな要素が、【学習面の安定感】です。
決して成績がトップである必要はありませんが、毎日コツコツ勉強する姿勢がある子は、担任の先生からの信頼も厚くなります。
ここで大切なのは、【長時間の勉強】ではなく、【短くていいから毎日続ける】こと。
習慣化のポイントは、やる気に頼らないことです。
親ができる工夫として挙げられるのは以下の通りです。
・夕飯前の10分だけドリルタイムを設ける
・一緒にタイマーを使って【集中チャレンジ】する
・勉強のあとはしっかり褒めて、ポジティブに終える
この毎日少しだけの積み重ねが、学力だけでなく自己管理能力や学ぶ姿勢につながります。
結果的に、それが優等生らしさの一部になります。
⑥ 自分の意見を言える【家庭の空気】をつくる
優等生と呼ばれる子は、【自分の考えを持っていて、それを伝える力がある】傾向があります。
たとえ人前で話すのが得意でなくても、自分の意見を整理し、人に伝える経験を積んでいるかどうかが大きな差になります。
この力は、家庭で育まれます。
たとえば、
・親が【あなたはどう思う?】【なんでそう考えたの?】と聞く
・ニュースや本の内容について一緒に考える
・家族でテーマトークをする時間を設ける
家庭で【意見を言ってもいい空気】があれば、子どもは自分の考えに自信を持ちやすくなります。
それが学校でも発言できる子、自分で考えられる子という評価につながっていきます。
⑦ 先生を信頼し、協力的な姿勢を見せる
実は、先生から優等生の親子と思われるかどうかも、子どもの評価に少なからず影響します。
学校は家庭と連携して子どもを支える場。親が先生を信頼し、前向きに協力する姿勢を見せることで、子どもも安心して学校に通えるようになります。
具体的には、
・連絡帳やプリントへの返信を丁寧に書く
・学校行事にはできるだけ参加する
・子どもが先生の話をしたとき、否定的な発言を控える
こうした積み重ねが、学校との信頼関係を築き、結果として子どもの印象を良くする土台になります。
優等生は家庭から自然に育つ
わが子が小学校で優等生と呼ばれるための7つのポイントをご紹介してきました。
ここで、改めて振り返ってみましょう。
・生活リズムを整えて、安定した心身をつくる
・挨拶・返事・感謝を家庭で自然に習慣化する
・自分のことは自分でやらせる勇気を持つ
・感情コントロールを一緒に言葉にして学ぶ
・学習習慣は【短く・毎日】を意識して習慣に
・家庭で意見を言える空気を意識的に作る
・先生との信頼関係を家庭からサポートする
優等生と呼ばれる子は、決して特別な存在ではありません。
むしろ、家庭での日常の積み重ねが、自然とその子の姿勢や言動を変え、結果として学校で評価されるようになっていくのです。
もちろん、今すぐにすべてを完璧にするのは無理があります。
どれかひとつでも、今日から家庭で意識してみてください。
【気がついたら、わが子が優等生に育っていた】
そんな未来を、家庭の力で育てていきましょう。