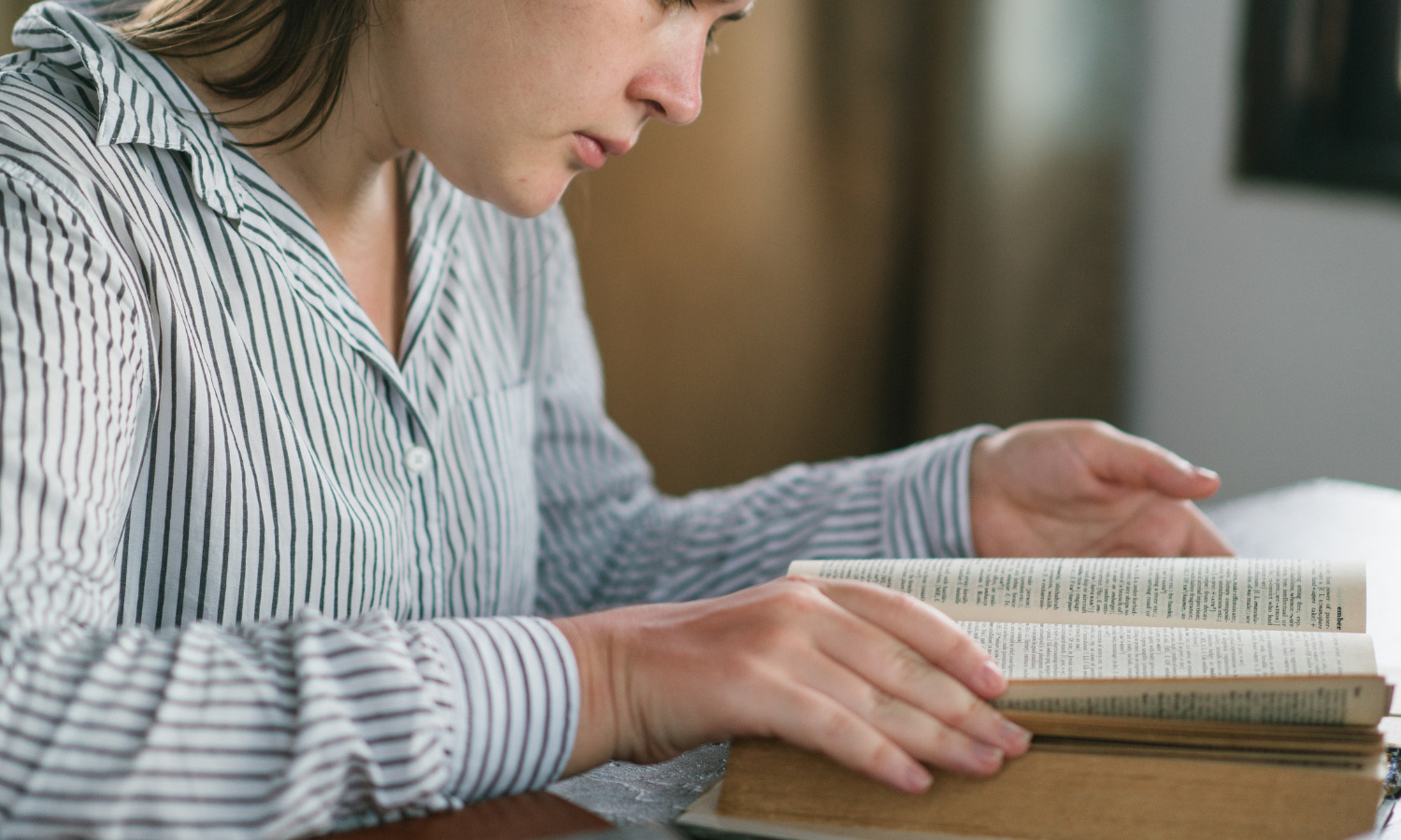今回は【どうしてあの子はできるの?小3で差がつく5つの理由】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校3年生。
それは、子どもたちの学力差がじわじわと表面化しはじめる時期です。
これまで一緒に団栗の背比べのようにあまり差がない中で学校の勉強を学んできたはずのクラスメイトの中で、【あの子はスラスラ解けるのに、うちの子は…】と感じ始める親も少しずつ増えてい来るタイミングではないでしょうか。
これは、親自身が子どもの頃はまだ小学3年生時点では気がつかないけれど、親となって子どもの勉強を見ていると感じるようになってきます。
少し周りを気にしない子どもでも【周囲との明らかな差】を感じるのは小学5年生だけれど、実際には小学3年生時点でジワリと学力差が出始めてきます。
小学校3年生というのは6年間の小学校生活の前半が終わる節目の学年でもあり、【学習の転換期】にあたります。
当然ながら、各教科の学ぶ内容の難易度も1年生、2年生の時よりも上がります。
そして、理科と社会もスタートします。
抽象的な理解や自学自習の力が求められ始めるため、学力の差が出やすい時期なのです。
しかし、差がつくのは子どもの能力差だけが原因ではありません。
環境・習慣・親の関わり方など、日々の積み重ねが影響しています。
この記事では、小3でできる子に共通する特徴を明らかにし、その後、賢い子に近づくための具体的な対策と、親ができるサポート方法までを3章構成でお伝えします。
小3でできる子に共通する5つの特徴
まず、子どもの学力は、単に知識量や勉強時間の長さだけで決まるものではありません。
小3以降に差がつきやすいのは、学習に対する【姿勢】や【思考習慣】、さらには【家庭環境】による影響が大きくなってくるからです。
【どうしてあの子はできるの?】という問いの裏側には、家庭ではなかなか見えない習慣の違いが隠れています。
ここでは、学力の高い小3の子どもたちに共通する特徴を5つに絞って紹介します。
①コツコツと続ける【習慣化】ができている
できる子に共通しているのは、【勉強を特別なことと思っていない】という点です。
毎日の生活の中に自然と学習が組み込まれていて、たとえ短時間でも継続することが習慣になっています。
こうした習慣は、最初は親の声かけや環境づくりによって育まれます。
【宿題は帰ったらすぐやる】【寝る前に音読する】といったルールが生活の一部になることで、勉強へのハードルが下がり、結果として学力が安定して伸びていきます。
学習習慣が出来上がるには、日常生活の安定が欠かせません。
起床時間と就寝時間が固定しているという、毎日の流れが出来上がっていることで、【この時間は勉強する】という時間を確保しやすくなります。
勉強するようになったら、次に大切になってくるのは【長時間やること】ではなく、【毎日続けること】です。
その積み重ねが後の大きな差につながっていきます。
②分からないを【放置しない】力がある
学力が伸びる子は、【分からないこと】をそのままにしません。
分からなかった問題を放置せず、調べたり、先生や親に聞いたりして解決しようとする姿勢が身についています。
これは、私が塾で仕事をしている時に学力グループごとに分類できるくらいハッキリとした傾向が出ていました。
つまり、学力上位層は間違い直しをしっかりする、分からないことを放置しませんでした。
学業不振になればなるほど間違いから逃げるという言動をしていました。
間違いやつまずきに向き合うことで、知識が定着し、理解の深さが増していきます。
この、【分からないことに気づいて対処する力】は、勉強に限らずあらゆる学習の場面で武器になります。
反対に、分からないまま流してしまうと、理解の穴がどんどん広がってしまいます。
できる子は、間違いをチャンスととらえ、そこから学ぶ意識が自然と身についているのです。
③語彙力と読解力が育っている
小3になると、どの教科でも【文章を読んで考える力】が必要になってきます。
できる子は、日頃から語彙力が高く、読解力もついているため、問題文の意味を正確に理解できるのが強みです。
とくに算数の文章題や理科・社会の記述問題では、語句の意味が分からなかったり、文章構造が読み取れなかったりすると解けません。
読書量や言葉に触れる機会が多い子ほど、自然とこの力が伸びていきます。
そして、正直、子どもの語彙力というのは家庭次第、親次第です。
小学1年生時点でかなりの差が出来上がっています。
ですから、学年が上がってから挽回するというのは子どもに相当な負担をかけることになります。
親子の会話や読み聞かせ、本や図鑑への興味が、すべて語彙力のベースをつくる大切な時間になります。
④勉強への【自己効力感】がある
できる子は、勉強に対して前向きで、【やればできる】という自信を持って取り組んでいます。
私は小学生時代、グータラでしたから周囲の優等生のキラキラしたやる気というものが偽善のようにも映ったことがありました。
しかし、【頑張るぞ!】という純粋な気持ちがなければ、学力を鍛えることも辛い受験を乗り越えることもできません。
受験はまだまだ先かもしれませんが、【やればできる!】という気持ちを小学生の頃から持つよう意識しておくことが、子どもの人生を助けることにつながります。
このような気持ちは、【自己効力感】と呼ばれ、小さな成功体験を積み重ねることで育まれます。
【この前より速く計算できた】【苦手だった問題が解けた】といった成功が、次への挑戦を後押しします。
反対に、【どうせ無理】と思ってしまうと、やる前からあきらめてしまい成長が止まります。
自己効力感は、親や先生からのポジティブな声かけや、努力を認めてもらう経験によって高まっていきます。
⑤家庭との連携が取れている
できる子の背景には、学習だけでなく家庭のサポート体制が整っていることが多いです。
親子の会話が日常的にあり、学びの進み具合や苦手なことについて自然に話せる関係ができています。
過干渉ではなく、見守る・応援するスタンスが基本です。
頑張ったことを褒める、失敗を責めず一緒に振り返る、学習に集中しやすい環境を整えるなど、子どもが安心して挑戦できる雰囲気づくりが大切です。
家庭が【学びを支える場】になることで、子どもはより意欲的に勉強へ向かうようになります。
賢い子に近づけるための具体的な対策
さて、【うちの子はそんな特徴、当てはまらないかも…】と感じたとしても、心配はいりません。
なぜなら、学力を伸ばす力は後天的に育てることができるからです。
小3はまだまだ伸びしろのある時期。
今からでも間に合います。
ここでは、学力の差が広がる前に実践したい具体的な対策を紹介します。
どれも特別な教材や塾を必要とせず、家庭でコツコツとできる内容ばかりです。
① 毎日5分のルーティン学習をつくる
学力を伸ばすには、長時間の勉強よりも【毎日続けること】が効果的です。
とくに小学生には習慣化がカギ。
毎日同じ時間、寝る前や帰宅後に5分だけでも学習時間を取ることで、脳が自然と【今は勉強する時間】と認識するようになります。
内容は漢字練習や音読、計算ドリルなど簡単なものでOK。
大切なのは、勉強するのが当たり前という空気を家庭の中に作ることです。
短時間でも積み重ねれば、自信につながり、集中力や粘り強さも育ちます。
タイマーを使って勉強の型を作るのもおすすめです。
②1日1つ【わからない】を解決する
わからないことを放置する癖がついてしまうと、理解の穴が広がり、やがて勉強そのものが苦手になってしまいます。
逆に、【わからない】をその日のうちに1つ解決する習慣があれば、理解力も自信も着実に伸びていきます。
ポイントは、完璧を求めず【1日1つだけ】と決めて続けることです。
学校の宿題で迷った問題を一緒に解き直したり、教科書を見返したり、YouTubeの授業動画を見るのも効果的です。
【どうせわからない】ではなく、【わかるようにできる】経験を重ねることが、賢い子への第一歩です。
③本やマンガで国語力の土台を強化
すべての教科に関わってくるのが【国語力】です。
しかも、力がつくのに時間がかかるという特徴があります。
問題文の意味が読み取れないと、算数や理科も正しく理解できません。
とはいえ、急に難しい本を読ませても逆効果。
まずは子どもが興味を持てるジャンルから入るのがコツです。
マンガや図鑑、会話が多いストーリーなどは、語彙力・表現力の入り口として十分に効果があります。
親子で感想を話し合ったり、一緒に音読したりするのもおすすめです。
読書を【楽しい体験】として積み重ねることで、自然と読解力が身につき、文章への苦手意識も薄れていきます。
④勉強で【できた!】を増やす仕掛けを
子どもが勉強に前向きになるには、【できた!】という成功体験が欠かせません。
難しいことをやらせるより、確実に達成できることを積み重ねる方が、自己効力感が高まります。
1ページ終わるごとにシールを貼る、できたことを見える化するチェック表を作るなど、小さな達成感を形にする工夫がおすすめです。
親が【ここまでよく頑張ったね】と声をかけることで、子どもは努力を認めてもらえたと感じ、自信を持って次に進めます。
成功の記憶が、学習意欲をぐんと引き上げてくれるのです。
⑤話す・説明する時間を意識的に取る
学んだことを【人に説明する】ことは、理解を深めるために非常に効果的です。
子どもは、説明しようとする過程で【自分がどこまで分かっているか】に気づき、曖昧な部分を自ら整理するようになります。
【今日学校で何をやったの?】【どうやって解いたの?】といった質問を、日常会話の中に自然に取り入れてみましょう。
正解かどうかよりも、【考える】【言葉にする】ことが目的です。
親がしっかり話を聞いてあげることで、子どもは安心して学びを振り返り、自分の成長を実感するようになります。
親にしかできないサポートとは
ところで、子どもの学力を左右する大きな要素の一つが、【親の関わり方】です。
ただし、それは教えることではありません。
小学校3年生になると、子どもは自立に向かい始める時期。
親ができるのは、環境を整え、気持ちを支え、学ぶ姿勢を育むことです。
ここでは、学力を伸ばすために親ができる具体的なサポートについてお伝えします。
①【勉強しなさい】よりも【よく頑張ってるね】
【早く勉強しなさい!】とつい言ってしまいがちですが、命令よりも、子どもの行動を認める声かけの方が、はるかに効果的です。
【やり始めたね】【集中してるね】【昨日より進んでるね】など、努力そのものに目を向けた言葉は、子どものやる気を引き出します。
子どもは大人以上に【見てもらえている】ことに敏感です。
小さなことでも認めてもらえると、自分の行動に意味を感じ、前向きな姿勢が育ちます。
勉強が好きになるきっかけは、親のひと言から始まることも多いのです。
②成績よりプロセスを認める
テストの点数や順位ばかりに注目すると、子どもは結果に一喜一憂し、【失敗=悪いこと】と思い込みがちです。
けれど、実際に学力を伸ばす子は、プロセスを大切にする経験を重ねています。
たとえば、【最後まであきらめずに解いたね】【前より丁寧に書けてたね】といった声かけは、努力や成長を実感させ、継続する力につながります。
点数だけで評価するのではなく、どう取り組んだかに目を向けることで、子どもは自信を持って次のステップに進んでいけるのです。
③一緒に勉強する時間をつくる
子どもが勉強に集中できないのは、単にやる気の問題だけではありません。
【1人でがんばらなきゃ】という孤独感や不安も大きく影響します。
そんな時は、親が近くにいて共に時間を過ごすことが心の支えになります。
一緒に机に向かい、親は読書や仕事に役立つ情報を収集したり資格取得の勉強をするだけでもOK。
同じ空間で静かに取り組む時間は、子どもに安心感と集中力をもたらします。
付きっきりで教える必要はありません。
【そばにいる】という存在感が、子どものやる気や継続力を育てる大きな要素になるのです。
④失敗しても責めない姿勢を
子どもが学力を伸ばすには、失敗を受け入れ、そこから学ぶ力が欠かせません。
ところが、間違いを責められたり、過度に指摘されると、【間違ってはいけない】と思い込み、挑戦する意欲を失ってしまいます。
重要なことは【失敗は成長のチャンス】というメッセージを家庭の中で伝えることです。
【よく気づけたね】【次はどうすればいいかな?】といった言葉で、失敗を前向きに捉える習慣が育ちます。
安心して失敗できる環境こそが、子どもの学びを支える土台になります。
⑤子どもの話を聞く時間を意識的に持つ
勉強の成果を伸ばすには、ただ子どもに問題を解かせるだけでなく、【学びを振り返る時間】が重要です。
親が子どもの話をじっくり聞くことで、子どもは自分の理解を言葉にしながら整理するようになります。【今日の授業、どうだった?】【どこが難しかった?】など、答えやすい質問から始めてみましょう。
子どもを否定せず、頷きながら聞く姿勢を持つと、子どもは安心して本音を話せます。
じっくり自分の気持ちを話すことで学びが深まり、親との信頼関係も強まる。
一石二鳥のサポート方法です。
小3は見えない差が大きくなる時期
小学校3年生は、勉強の内容が一気に抽象的になり、学力の差が目に見えて広がり始める重要な時期です。
しかし、その差の多くは、子ども自身の才能や能力の差ではなく、日々の学習習慣・家庭環境・親の関わり方といった見えにくい要素によって生まれています。
できる子は、特別なことをしているわけではありません。
【コツコツ続ける】【わからないを放置しない】【家で会話がある】など、当たり前のように見えることを日々積み重ねているのです。
だからこそ、今どんな状態であっても、子どもはここから伸びていけます。
親にできるのは、焦らず・責めず・信じて見守りながら、学びの環境を整えてあげること。
小3は分かれ道ではなく、まだ挽回が可能な時期です。