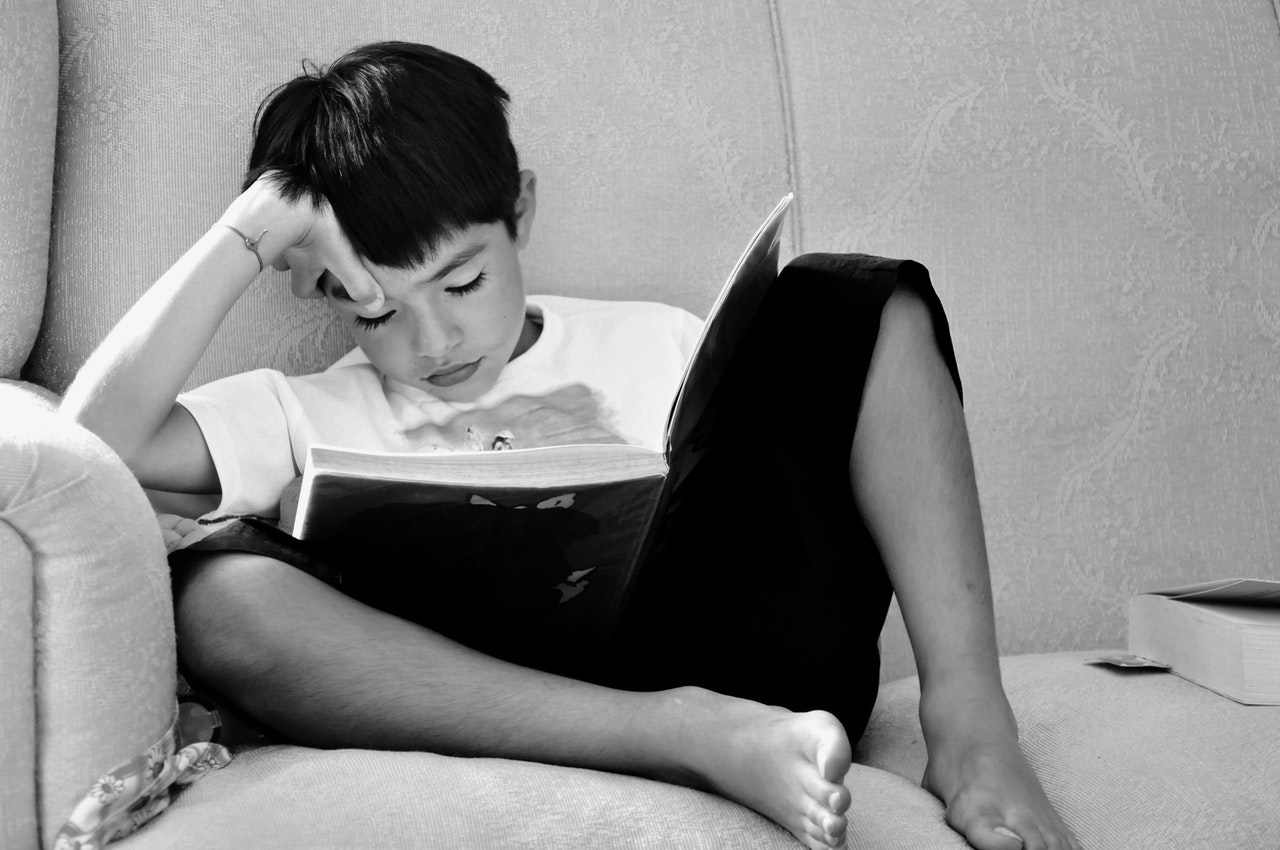今回は【【英語だけできる子】にしない!教科バランスを守る先取り英語対策】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
2020年度から小学校での英語教科化がスタートし、それに伴い教育に関心の強い家庭を中心に早い段階から英語に取り組む家庭が増えています。
小学校の英語は俗にいう【楽しみながら英語に親しむ】という要素が大きいものの、中学校の英語では文法事項が複雑化し、授業の進度も速くなっていることから、【少しでも早く準備しておきたい】と考える親は多いでしょう。
私の周りでも、そう考えて対策を講じている方もいました。
英語を得意にさせたいという思いから、低学年から英会話スクールや英検対策に取り組ませるケースも珍しくありません。
しかし、その一方で【英語は得意だけれど国語や算数が伸び悩んでいる】【英語学習を優先した結果、他教科の基礎が不十分になってしまった】といった悩みも生まれてきます。
私も塾で仕事をしている時に、【英語だけ妙にできる】という子がいました。
子ども①②の周りにもいます。
弾みとなる、強みとなる教科があることは良いことですが、やはり入試は3教科、または5教科の総合点で争う世界です。
英語に注力するあまり、他教科への影響が出てしまうというのは、見落としがちな落とし穴です。
国語や算数は、いずれも言語理解や論理的思考力に深く関係する教科であり、英語と切り離して考えることはできません。
つまり、英語だけ先行しても、土台となる力が育っていなければ本質的な理解にはつながらないのです。
そこで今回は、英語の先取り学習をしながらも他教科とのバランスを保ち、総合的に学力を育てる方法について詳しく解説していきます。
なぜ【英語だけできる子】になってしまうのか
まず、ご存じの通り小学生向けの英語教育が盛んになる中で、早期から英語に触れることのメリットは多く語られています。
英会話教室やオンライン英会話、英検対策に取り組む子も増え、【小学生で英検3級に合格】【ネイティブと自由に会話できる】といった実績がSNSなどで紹介されることもあります。
英語が【できる】ことは、目に見えやすく、親の満足感にもつながりやすい分野です。
しかしその一方で、実際の学力面では、英語が得意なはずの子が国語の読解問題でつまずいたり、算数の文章題で正確に情報を読み取れなかったりするケースも見受けられます。
【英語はできるのに、なぜ他の教科では点が取れないのか?】という疑問は、多くの親が直面する悩みの一つです。
その背景には、【英語学習が目的化しすぎている】という問題があります。
子どもにとっても親にとっても、英語は達成感を得やすい科目です。
単語を覚えればテストにすぐ反映され、英会話を習えば聞き取れるようになる。
そうした即効性のある成果が見えるため、【英語=努力が報われる教科】として優先されがちです。
ところが、国語や算数はそうはいきません。
漢字や読解問題は、すぐに成果が見えるものではなく、文章を読みこなす力や論理的に考える力は、時間をかけて育てていくものです。
そのため、親が英語に安心感を持つあまり、国語や算数の学習が後回しになってしまうという構図が生まれてしまいます。
とくに英語学習を進めるうえで見落としがちなのが、【英語は日本語とは別の延長線上にある言語活動】であるという事実です。
つまり、英語を理解するには、その前提として母語=日本語の運用能力が不可欠なのです。
中学英語では、単語の暗記だけでなく、文の構造理解、主語と動詞の関係、修飾語の位置など、論理的な読解力が求められます。
たとえば、【I play soccer after school.】という文を見て、主語(I)・動詞(play)・目的語(soccer)・副詞句(after school)という文構造を理解するには、そもそも日本語での【文の要素】や【意味のつながり】に慣れている必要があります。
また、長文読解では、情報の取捨選択や文章の構成を把握する力が必要です。
これはまさに国語の読解力であり、英語の力とは切っても切り離せないものです。
国語の力が弱いまま英語を進めてしまうと、初期のうちはうまくいっていても、学年が上がるにつれて理解が追いつかず、急に伸び悩むケースが多くなります。
実際、中学生に英語を教えている時に国語力のある子は英文法の理解が早く、たとえ英語の勉強を中学からスタートしたとしてもグングン伸びていくのを何人も見てきました。
その一方で、国語力の低い子は形容詞、副詞という話をしても全くピンとこず、ずっと中学1年生の内容を乗り越えられないという状態になっていました。
さらに、算数でも同じような傾向が見られます。
文章題や図形の説明文などでは、【何を求められているのか】【条件は何か】を読み取る力が必要です。
これもまた、言語力、とくに日本語を通じた論理的思考力が問われる部分です。
英語にばかり時間を割き、母語の処理力や論理力の育成が不十分なままだと、算数の成績にも悪影響を及ぼすことがあるので、気を付けてください。
どうしても【英語ができる=勉強ができる】と短絡的に判断してしまうと、学習のバランスが崩れてしまうリスクがあります。
実際、英語の先取りをして英検の級を持っている子どもが、中学に入ってから英語の文法や読解でつまずく例は珍しくありません。
子ども①よりもはるかに英語力があるけれど、学校のテストや塾のテストでは同程度になるという笑えない話もありました。
それは、小学生のうちに【表面的な英語の力】ばかりを伸ばし、【支える言語力の土台】が育っていなかったためです。
また、こうしたゆがみは、子ども自身の【学習の自信】にも影響を与えます。
英語が得意だったのに、他の教科でつまずき、全体の学習意欲を失ってしまうこともあります。
英語の先取りは確かに有効な取り組みですが、それが【英語だけの子】になってしまっては本末転倒です。
本当に大切なのは、英語を軸としながらも、国語や算数といった教科と相互に補完し合いながら、総合的な学力を育てていくことなのです。
教科バランスを崩さない英語先取りの考え方
さて、小学生から英文法の先取りをしていく際、他の教科の学習時間の【配分】を意識するようにしましょう。
英語の先取り学習を始める際、まず意識したいのが【時間の配分】です。
多くの家庭では、子どもの学習時間には限りがあるため、英語に時間を割くほど他の教科の時間が減ってしまいがちです。
たとえば、1日の勉強時間が1時間しかない中で英語学習に30分を充てると、残りの30分で国語・算数・理科・社会すべてをこなす必要が出てきます。
これでは、他教科の学力が低下するのも無理はありません。
そこで大切なのは、【英語の学習時間を新たに捻出する】という発想です。
具体的には、勉強時間全体を10〜15分でも増やし、その増えた分を英語にあてることで、既存の教科の学習時間を圧迫せずに済みます。
また、時間だけでなく内容の質も見直すことが重要です。
ダラダラと机に向かうのではなく、集中した短時間学習に切り替えることで、同じ30分でも密度の濃い学習が可能になります。
学習スケジュールを見直し、子どもが無理なく取り組める配分を考えることが、教科バランスを保つ第一歩です。
さらに、英語の学習にプラスアルファを求めるなら、他教科の力を引き出す方法を考えることも大切になってきます。
英語の学習は、それ単体で完結するものではありません。
英語を学ぶことで他教科の力を引き出すことも可能です。
ポイントは、英語を【知識として教える】のではなく、他教科とのつながりを意識した【言語活動】として活用することです。
たとえば、英文の音読や書き取りを行う際には、主語や述語、修飾語の位置に注目させることで、日本語での文法意識にもつながります。
これは、国語の文構造を理解する土台となり、読解力の向上にも役立ちます。
また、英語の短い文章を読んで、それを日本語で要約する練習も効果的です。
英語の意味を読み取り、自分の言葉で再構成する作業は、国語の要約力や作文力を養う上でも非常に良いトレーニングになります。
別の切り口で考えると、算数との組み合わせも工夫できます。
英文で出題される簡単な算数の文章題に取り組むことで、英語と数学的思考を同時に鍛えることが可能です。
たとえば、Tom has three apples. He buys two more. How many apples does he have now? のような問題を扱うことで、英語の理解と算数の計算力を一緒に高められます。
このように、英語を孤立した教科として教えるのではなく、国語や算数と連携させることで、他教科の理解を深める【言語的な土台】として機能させることができます。
これは、教科バランスを崩さないどころか、全体の学力の底上げにもつながる方法です。
そして、先取りで英語を学ぶ際は勉強する内容についても工夫が必要です。
小学生向けの英語教育では、【英会話中心】【フォニックス中心】といった音の学習に偏るケースが多く見られます。
もちろん、リスニング力や発音の習得は大切ですが、中学英語にスムーズに移行するためには、文法や読み書きの基礎を疎かにしてはいけません。
中学英語のカリキュラムは、1年生の段階からbe動詞、一般動詞、三単現、疑問文、否定文、助動詞など多くの文法事項を短期間で学ぶ構成になっています。
音だけに慣れていた子は、いざ中学で文法が導入されたときに【英語が難しい】【わからない】と感じ、混乱してしまうことがあります。
そのため、小学生のうちから英語を先取りする際には、【主語+動詞】【I like apples.】のような基本的な文を声に出しながら書く、【疑問文に答える英文を書く】【簡単な英文日記を書く】といった読み書き中心のトレーニングが効果的です。
日本語と同じように、英語でも【言葉を使って表現する力】を育てることが、中学英語の土台づくりに直結します。
また、文法の名称を無理に覚える必要はありません。
大切なのは、【この順番で言えば意味が通じる】【主語が変わると動詞の形も変わる】といった感覚を、小学生のうちに自然と身につけることです。
そのためには、文法知識を単独で教えるのではなく、【意味のある文】を扱う形で学習させることがポイントです。
小学生の英語先取りにおすすめの実践ステップ
ところで、英語の先取り学習を効果的に進めるには、【いつから】【どのように】始めるかが非常に重要です。
ただ知識を詰め込むのではなく、年齢や発達段階に応じた取り組み方を選ぶことで、他教科とのバランスも自然に保つことができます。
とくに小学生のうちは、英語を教科としてではなく【ことば】として捉える感覚が大切です。
ここで、国語力や論理力を土台にしながら、英語の文法や語順に親しむ具体的なステップや、家庭で無理なく続けられる実践方法についてご紹介します。
ステップ①:国語力を育てながら英語を始める
英語を先取りする前に見直したいのが【国語力】です。
英語の理解には、日本語での文構造や語彙力、読解力が基礎になります。
たとえば、【主語と述語の関係】【文の要点をつかむ力】【説明文を正確に読む力】などは、英語の文法や長文読解に直結します。
つまり、国語が弱いまま英語を先取りしても、表面的な暗記で終わり、本質的な理解に結びつきにくくなってしまいます。
そのため、小学生の英語の先取りは【国語と並行して進める】ことが鉄則です。
たとえば、日本語での要約練習や音読、簡単な作文に継続的に取り組みながら、英語学習を進めると、両方の力が相乗的に育ちます。
【日本語で考え、英語で表す】サイクルを意識することで、英語の学びも自然で深いものになっていきます。
ステップ②:遊び感覚で文法と語順に親しむ
小学生には、文法用語を機械的に覚えさせるのではなく、【感覚的に語順を理解する】ことが大切です。
簡単な主語・動詞・目的語(SVO)構造の英文カードを使って並び替えゲームをすることで、自然と英語の語順に慣れていきます。
【I like apples.】【He plays soccer.】といった短い例文を何度も声に出して書く練習も効果的です。
主語を変えてみたり、動詞を置き換えてみたりすることで、英文構造への理解が深まります。
こうした繰り返しによって、【英語は語順が大事】という感覚が身につき、文法への抵抗感も減っていきます。
ステップ③:簡単な英文の読み書きを日常に取り入れる
英語の【読み書き】を日常に取り入れることも、文法重視の先取り学習には有効です。
たとえば、英語日記を毎日1文でも書く、小学生向けの英語絵本を読む、などの習慣を作ることで、自然に英語に触れる時間が増えます。
また、英語の意味と構造を正確に理解するために、日本語訳を一緒に書く活動もおすすめです。
単なる丸暗記ではなく、【なぜこの語順なのか】【なぜこの単語が使われているのか】を意識させることが、深い学びにつながります。
英語先取りの学習は、やり方次第で国語や算数の力を引き出すことも可能です。
大切なのは、英語だけにならないよう、言語の土台を広げながら進めること。
日常の中に自然に取り入れられる工夫で、無理なく、かつ確かな力を身につけることができるのです。
英語の先取り学習は、将来の学習や入試において大きなアドバンテージになります。
しかし、それが【英語だけできる子】を育ててしまうのでは本末転倒です。
英語は言語の一つに過ぎず、その理解には国語力や論理的思考力といった学びの土台が欠かせません。
小学生のうちは、教科ごとのバランスを意識した学習が何よりも大切です。
英語を早くから学ぶ場合でも、国語や算数の力をしっかり育てながら取り組むことで、むしろ相乗効果が期待できます。
英語は孤立した特別な教科ではなく、他教科とつながる【考える力の一部】です。
子どもにとって無理のないペースで、読み書きを中心に英語の文法や語順に親しみながら、日常的に触れる機会を作っていく。
そんな丁寧な学びの積み重ねが、中学・高校以降に伸びる本当の英語力につながっていきます。
焦らず、確実に、総合的な学力を育てていきましょう。