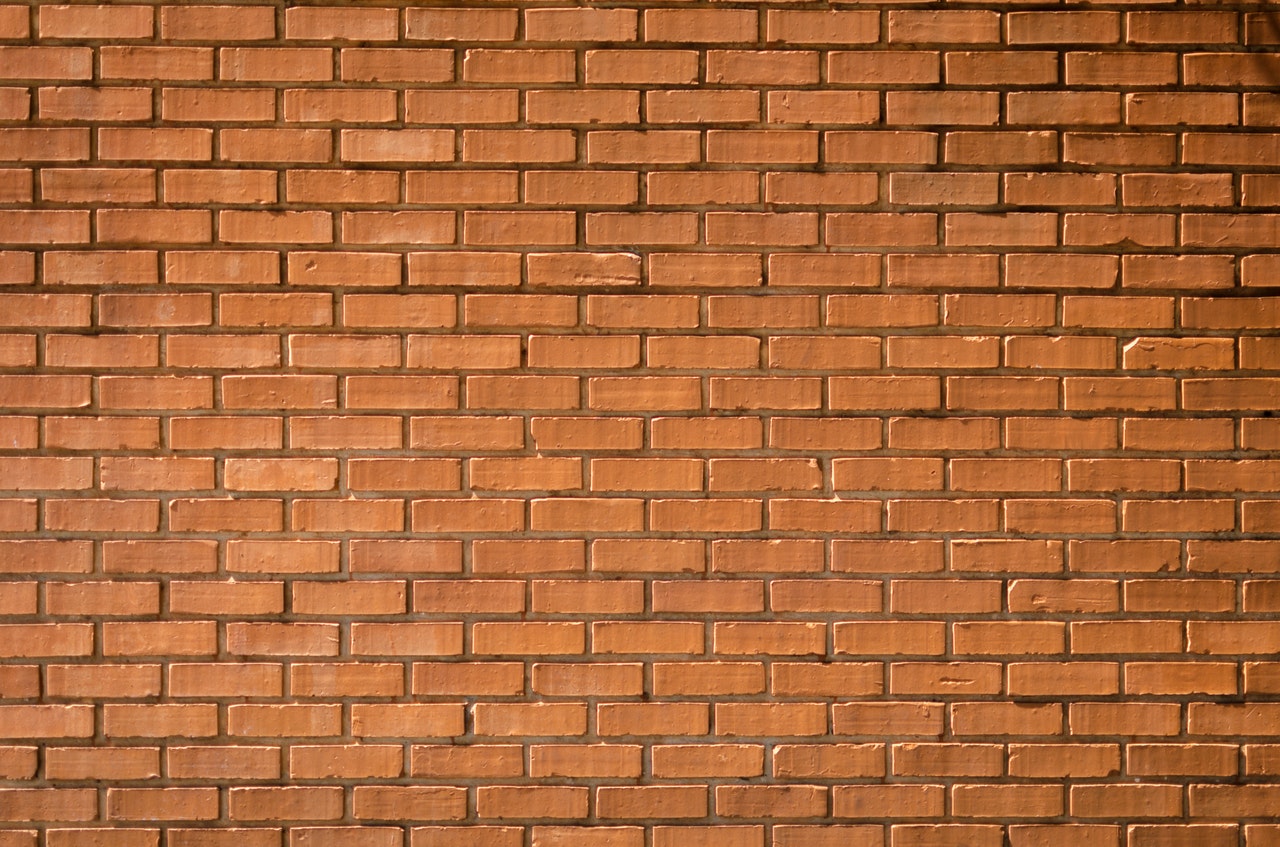今回は【高学年でつまずかない! 10歳の壁で差がつく【読解力】と【論理的思考力】】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
10歳の壁、それは【学びの質】が変わるサインです。
そして、多くの親にとっては不気味な壁であり、どうやって乗り越えていけばいいのか思案します。
私も、塾で出会った子ども達、そして子ども①②③や学校生活の様子を見聞きする中でも感じましたが、子どもが小学校高学年に差し掛かり、日々の勉強に【あれ?】と感じることが増えていきます。
【これまでスラスラ解けていた算数の文章問題でつまずくようになった】
【資料問題に手を焼いている】
【理科や社会で、暗記だけでは点数が取れない】
【学校のテストで高得点が取れなくなってきた】
もしひとつでも心当たりがあるなら、それは子どもが【10歳の壁】に直面しているサインかもしれません。
【10歳の壁】とは、一般的に小学4年生頃に訪れる、学習内容の急激な変化と、それに伴う子どもたちの躓きを指します。
この時期から、学習は【知識の丸暗記】から【知識を活用し、考える】段階へとシフトします。
とくに重要になるのが、読解力と論理的思考力です。
低学年では、教科書に書かれている内容をそのまま理解するだけで十分でした。
しかし、高学年になると、文章の行間を読み解き、物事の因果関係を自分で見つけ出し、自分の言葉で説明する力が求められます。
この【学びの質】の変化に対応できるかどうかで、将来の学力に大きな差が生まれるのです。
そこで今回は、なぜ10歳の壁で【読解力】と【論理的思考力】が重要になるのかを掘り下げ、そして、ご家庭で今日からできる具体的な対策をご紹介していきます。
この時期を親子で協力して乗り越え、子どもの大きな成長につなげましょう。
なぜ【10歳の壁】で読解力と論理的思考力が不可欠になるのか
まず、 読解力の不足が【全教科】に影響するという現実を直視してください。
多くの方が【読解力は国語の力】と思われがちですが、実はそうではありません。
読解力は、算数、理科、社会、そして英語など、すべての科目の土台となる力です。
余談になりますが、塾で中学1年生に英語を教える時、当時は大半の子が中学1年生になってから英語の学習をスタートさせるため、スタートラインは同じでしたが、国語力の高い子ほど英語の理解力も早かったですし、他の教科で新しいことを学ぶ時も定着するまでの時間というのは読解力が不足気味なこと比べると短かったです。
ですから、小学校高学年以降の勉強の出来不出来は読解力のレベル次第になるというのを忘れないでください。
高学年の算数では低学年のような計算問題が主体の学びではなくなります。
複雑な文章問題では、【何が問われているのか】【どの情報をどう使うのか】を正確に読み解く力が必要になります。
読解力が不足気味だと、計算はできても問題の意味が分からず、正解にたどり着けません。
理科や社会では 実験や歴史的事象の説明文、図やグラフから必要な情報を読み取る力が必要です。
単なる暗記では、応用問題や思考力を問う問題に対応できません。
読解力の不足は、まるで視界にモヤがかかった状態で勉強するようなもので、全ての学習効率を下げてしまいます。
10歳の壁で求められるのは、単に文字を読む速さではなく、文章の意図や背景、筆者の主張を深く理解する力です。
そして、読解力と同様に重要度が高まるのが論理的思考力です。
そもそも、論理的思考力がなければ【考える力】は育ちません。
論理的思考力とは、物事を筋道立てて考え、結論を導き出す力のことです。
これがなければ、せっかく知識を学んでも、バラバラの情報のままになってしまいます。
思考のプロセスが求められる高学年の学習では、【なぜそうなるのか】【AとBの関係は?】といった、思考のプロセスを問う問題が増えます。
たとえば、【日本の人口が都市部に集中している理由を説明しなさい】といった問題では、歴史的背景や社会経済の変化など、複数の要因を論理的に結びつけて考える必要があります。
知識を【使える力】に変えなければいけません。
論理的思考力があれば、学んだ知識をただ覚えるだけでなく、それを現実の問題解決に応用できるようになります。
これは、将来社会に出てからも役立つ、最も重要なスキルの一つです。
【10歳の壁】でつまずく原因は、これらの【読む力】と【考える力】の不足であることがほとんどです。
これらの力がなければ、いくら頑張って勉強しても、成果が出にくいという悪循環に陥ってしまいます。
【考える力】を育むための具体的な対策
さて、それでは子どもの考える力を鍛えようと思っても、その方法をパッと思いつくのは難しいものがあります。
インターネットで検索しても、その方法が子どもにピッタリ合う保証はありません。
子どもの性格を踏まえて、たくさんある情報から【この方法なら改善しそう】【効果がありそう】とピックアップし、実践していくしか解決策はないです。
ここでは、少しでも解決の糸口になる手助けになるよう、子どもの【読解力】と【論理的思考力】を鍛えるための具体的な方法、【読解力を鍛えるための3つのステップ】を今すぐ始められるものからご紹介します。
ステップ1:音読と要約の習慣をつける
音読は、文章の構造を把握する上で非常に効果的な方法です。
声に出して読むことで、目で追うだけでは見落としがちな接続詞(しかし、したがって、なぜなら)や主語・述語の関係を意識するようになります。
学校の宿題の音読だけでなく、家庭学習に取り入れてみましょう。
子どもが親に読み聞かせてもらった本を逆読み聞かせしてもらったり、子どもが好きなマンガの文章でも構いません。
声に出して読む習慣をつけましょう。
我が家でも、親に聞いて欲しい漫画のセリフ、本の一節、一章を読むということをしてきました。
言葉の区切り、接続詞の使い方を自然と身につけるのに効果があったと思っています。
もう少し一歩進んで【要約に挑戦させる】というのをやってみるのもおすすめです。
読んだ文章や物語について、【この話で一番大事なことは何だった?】【結局、どういうこと?】と尋ねてみてください。
最初は一言でもOKです。
少しずつ、20字、50字と要約する練習をさせることで、文章の全体像を捉える力が育ちます。
ステップ2:新聞やニュースに触れる機会を作る
新聞やニュースは、要点が簡潔にまとめられており、読解の練習に最適です。
毎日1記事を一緒に読むことで、色々なスキルを高めることもできます。
子ども向けの新聞や、インターネットのニュースサイトを、親子で一緒に読んでみましょう。
【この記事のタイトルは何?】【この記事は何について書かれているかな?】と問いかけ、内容を一緒に考える時間を作ることが重要です。
ニュースをただ読むだけでなく、【なぜ?】を掘り下げることも意識してください。
記事を読んだ後、【なんでこんなことが起きたんだろうね?】【この問題はどうすれば解決できると思う?】といった質問を投げかけ、子どもの思考を深めるきっかけを与えましょう。
ステップ3:語彙力を増やす工夫をする
読解力は語彙力と密接に関係しています。
知らない言葉が多いと、文章全体の意味を理解するのが難しくなります。
多くの子が嫌がりますが、塾でも【するしない】で学力差が顕著だった【辞書を引く習慣】をするようにしてください。
学力の高い子はわからない言葉に出会ったら、【面倒です】と口で言っても、ちゃんとその場で辞書を引く習慣がありました。
一方で、学力が伸び悩む、またはボトム層の子ほど絶対に自分から調べようとしませんでした。
今は紙の辞書がない家庭も多いので、電子辞書やスマホの辞書アプリも便利です。
また、子どもとの会話を楽しみながら読解力を鍛えていくのにピッタリなのが【言葉遊び】です。
言葉遊びはしりとりなどがありますが、この他にも【この言葉と似ている言葉は?】【この言葉の反対は?】といった言葉遊びも、楽しみながら語彙力を高める良い方法です。
我が家でも、類義語対決や果物仲間対決などをして言葉を磨くようにしていきました。
論理的思考力を鍛えるための3つの方法
ところで、【うちの子、どうして答えにたどり着けないんだろう?】【なぜ、問題の意味がわからないんだろう?】と感じたとき、多くの場合、子どもの論理的思考力が原因になっていることがあります。
論理的思考力とは、物事を筋道立てて考え、結論へと導く力です。
この力は、算数の文章問題を解くことはもちろん、理科や社会の因果関係を理解したり、自分の意見を明確に伝えたりするためにも不可欠です。
しかし、この力は親が何も対策をせず、子ども任せにして十分なレベルの力が身につくものではありません。
小学校高学年になると、論理的に考えることを求められる場面が格段に増えるため、論理的思考力の有無や、対策をせずにいると、学力全体に影響が出てきます。
【もう手遅れだ】と絶望に近い気持ちになるかもしれませんが、論理的思考力は、日々の生活のちょっとした工夫や、親の関わり方次第で、誰もが伸ばすことができます。
机に向かうだけが勉強ではありません。
ここでは、遊びや会話を通じて、楽しみながら論理的思考力を育むための具体的な方法を3つご紹介します。
方法1:親子でディスカッションを楽しむ
家庭での会話を【問い】と【答え】だけのやり取りではなく、【なぜ?】や【どうして?】を深く掘り下げるディスカッションの場に変えてみましょう。
一番やりやすいのが、テーマを決めることです。
【なぜご飯を食べる前に手を洗うの?】【もし1日だけ透明人間になれたら、何がしたい?】など、身近なことから少し非現実的なことまで、何でも構いません。
次に、子どもに理由を説明するよう促してみてください。
子どもが何か意見を言ったら、【なんでそう思ったの?】【その理由を3つ教えて】と優しく問いかけ、自分の考えを論理的に説明する練習をさせましょう。
今の小学校の勉強でも、自分の意見を言う機会が親世代の頃よりも格段に増えてきています。
自分の言葉で理路整然と話ができるかどうかは、クラス内での立ち位置を決めることもあるので、力を入れていて損はありません。
方法2:プログラミング的思考を養う
2020年度にスタートした学習指導要領でプログラミング教育が導入されると決まってから、何かとプログラミング教室が増えたような気もしますが、プログラミング教育とは何もパソコンオンリーとは限りません。
学校でのプログラミング教育は、物事を順序立てて考える【プログラミング的思考】を鍛えることを目的にしており、その結果、公立小の勉強やテストも考えさせる問題が以前よりも増えてきています。
こうした考えに柔軟に対応するには小難しいものではなく、遊びから始めるのがベターです。
プログラミング教育用のロボットやおもちゃ、無料の学習サイトなどが豊富にあります。
まずはゲーム感覚で、楽しみながら論理的な思考のステップを学ばせてみましょう。
そして、身近な例で考えてみるということも、おすすめです。
【朝、学校に行くまでの手順を細かく説明して】【カレーライスを作る手順を言葉で説明してみよう】といった日常的なタスクを分解して考える練習も、論理的思考力を養います。
方法3:パズルやボードゲームを活用する
戦略を立て、論理的に考えることが求められるパズルやボードゲームは、楽しみながら思考力を鍛えることができます。
おすすめのゲームは 将棋、囲碁、チェス、オセロ、立体パズル、推理ゲームなどが挙げられます。
我が家でも、こうした類のゲームはガンガンやってきましたし、完全に趣味となっているものもあります。
そして、こうしたゲームを親も一緒に楽しむと子どものスキルを磨くだけでなく、親子関係にもプラスに働きます。
子どもと一緒にゲームに熱中することで、コミュニケーションも深まり、子どももより積極的に取り組むようになります。
【10歳の壁】は、決して怖いものではありません。
むしろ、これまで培ってきた基礎学力を土台に、子どもの【考える力】が大きく花開く、最高のチャンスです。
この時期に親ができることは、答えを教えることではなく、考えるための【問い】と【環境】を与えることです。
子どもが【わからない】と口にしたら、それは成長のチャンスです。
【どこがわからないの?】【どうすればわかると思う?】と問いかけ、一緒に考える姿勢を見せましょう。
そして、小さなことでも構いません。
難しい問題が解けた、自分の意見をしっかり言えたなど、日々の成功体験を認めて褒めてあげることで、子どもは自信をつけ、次の挑戦へと向かうことができます。
周りのお子さんと比較したり、結果を求めすぎたりせず、子ども一人ひとりのペースを大切にしてください。
読解力と論理的思考力は、短期間で身につくものではありません。
日々の積み重ねが、やがて大きな力となります。
子どもの【知りたい】【考えたい】という気持ちを大切にし、温かく見守ることで、10歳の壁を力強く乗り越え、大きく成長してくれるでしょう。