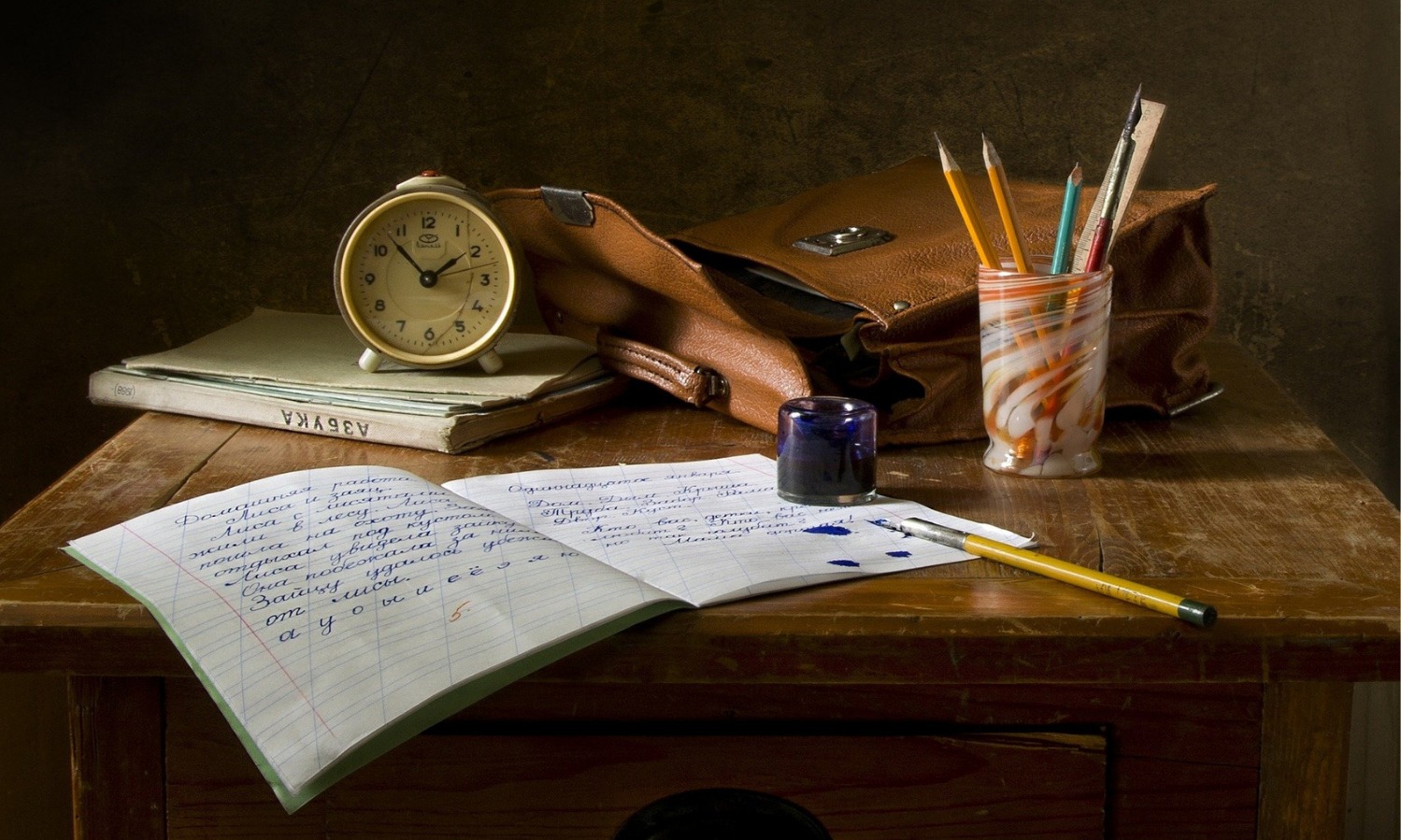今回は【集中できない子の特徴 そのまま放置すると起こる3つの学力低下】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【毎日机に向かっているのに、なぜか成績が伸びない】
【友達と同じくらい勉強しているはずなのに、テスト結果がまったく違う】
そんな違和感を感じている方も多いのではないでしょうか。
学年が上がると気になる学力差の引き金になるのが、目に見えにくい【集中力】という要素が大きく関わっています。
集中している子は短時間でも質の高い学習ができる一方で、集中できていない子は時間だけが過ぎ、内容がほとんど頭に残っていない、というケースが珍しくありません。
【まだ小さいから仕方ない】【高学年になれば自然と集中できるようになるはず】と期待している方もいらっしゃるでしょう。
残念ながら、成長すれば勝手に集中力がアップするほど甘いものではありません。
私も塾で色々なタイプの子と接する中で気がつきましたが、中学3年生より小学2年生の子の方が集中力があるといったケースに遭遇したこともあります。
もちろん、集中力のある子の方が知識の吸収量も多く、成績がよく、中学3年生という受験学年だけれど集中力が続かない子は、知識の定着が甘いという傾向がハッキリと出ていました。
集中力は年齢とともに自然に身につくものではなく、意識的に育てていくスキルです。
そして、集中力のなさを放置してしまうと、理解力・思考力・記憶力といった学力の土台が崩れていく、または学力を鍛えようとしても思うようにいかない危険性があります。
そこで今回は、【集中できない子どもに共通する特徴】【集中力がないと起こる3つの学力低下】【家庭でできる集中力の育て方】について取り上げていきます。
我が子の【なんとなく伸び悩んでいる】原因を知りたい方にとって、ヒントになれば幸いです。
集中できない子の特徴と行動パターン
まず、成績の伸び悩みを感じている時は子どもの集中力がどの程度か振り返ってみてください。
【うちの子、ちゃんと勉強してるのに、なかなか成果が出ないんです】
そう相談される方の多くに共通しているのが、【実際にどれだけ集中しているか】を把握していないという点です。
私も塾で感じましたが、集中力が続かない子どもには明確な共通点があります。
勉強そのものが苦手というよりも、【集中しづらい行動パターン】や【環境】が習慣化してしまっていることが多いのです。
以下に代表的な特徴を4つご紹介します。
① 勉強中も姿勢が安定しない
まず最も目立つのが、【落ち着いて座っていられない】という共通点があります。
椅子に座っていても体を揺らしたり、何かを触っていたり、鉛筆を回していたりと、常に体が動いている状態です。
書いている途中に手が止まり、ノートが進まないこともしばしばあります。
癖だから仕方がない、というのではなく、【勉強したくない】という気持ちが態度に出てしまっている子がほとんどでした。
勉強に対する反抗心が姿勢が安定しないというカタチで出てしまい、それがお世辞にも勉強しやすいものではなく、結局勉強していても時間だけが過ぎてしまうという、悪循環に陥っているというのを個人的に感じていました。
ゲーム好きな子に【ゲーム中もそういう姿勢になるのか】と質問したことがありますが、【そんなことはない】と答えていたので、やはり気持ちの問題だと思います。
姿勢が安定しない子は、【勉強に対する嫌悪感を取り除く】ということに力を入れないと、親がガミガミ叱っても改善するのは難しいです。
得意教科を最初は多目に勉強することや、短時間でも集中したら褒めるという成功体験を積んでいくなどして【勉強=辛い】という感情をなくしていくようにしましょう。
② 周囲の音や動きに敏感
家族の話し声、テレビの音、通りすがりの人の気配が気になる子は一定数います。
集中できない子は、こうしたちょっとした刺激にすぐに反応してしまいます。
例えば、勉強中に誰かがキッチンで音を立てると、それに気を取られてペンが止まる。
外で犬が吠えたら、窓の方をじっと見てしまう。
こうした行動は一見小さなことのようですが、毎回集中が切れることで、勉強の流れが作れなくなってしまうのです。
また、スマートフォンやタブレットが近くにあると、その存在自体が集中の妨げになります。
通知音が鳴らなくても、目に入るだけで意識が持っていかれてしまうことがあります。
音に敏感で集中力が途切れがちな子は、【我慢しなさい】と一喝するのではなく、子どもと一緒に勉強する環境をもう一度見直して、音が出にくい環境を協力して整えるようにしてください。
③ 目的やゴールがあいまい
集中できない子の多くは、【何のためにその勉強をしているのか】を理解していません。
まだ低学年の頃は良いのですが、学年が上がり、小学校高学年や中学生になっても勉強の意義が見いだせないと集中力に影響が及ぶことがあります。
たとえば【宿題を解けばいい】という行動自体が目標になっていて、その中身や宿題をすることの意味、将来にわたることを全く理解していないことも多いです。
【とりあえず言われたからやる】【終わらせればいいや】という意識のままだと、子どもは勉強に対する意欲が湧きにくくなり、本気モードに突入するまでに時間がかかります。
目標が不明確な状態では、集中する理由がない=すぐに注意が逸れるという悪循環になるので、日々の勉強でも何かしらの目的意識を持つようにする、短期や中期の目標を設定すると、集中力改善にもつながります。
④ 集中する前に【疲れた】と言ってしまう
やり始めてすぐ【疲れた】【もう無理】と言う子は、集中に入る前の助走すら終えていないことが多いです。
私も塾で子どもたちに勉強を教えている時に、授業が始まってすぐに【疲れた】と白旗を上げる子がいました。
人は集中状態に入るまでに少し時間がかかります。
しかし、集中する前に離脱してしまえば、当然ながら学習は深まりません。
【疲れた】と言うことで、親に【もう休んでいいよ】と言ってもらえる経験を繰り返すと、それが習慣化してしまうこともあります。
また、集中状態に入っていない学習は、いくら長時間やってもやった感だけが残り、知識の定着にはほとんど結びつかないのが現実です。
以上のような特徴を持つ子どもたちには、【机に向かっている時間】は確かに存在しています。
けれどもその中で、実際に脳が働いている=学んでいる時間はごくわずかです。
この集中している時間の密度の差が、徐々に成績や理解力に反映され、周囲の子との差となって現れます。
だからこそ、親が見るべきポイントは【どれだけ長く勉強しているか】ではなく、【どれだけ集中しているか】なのです。
集中力不足が引き起こす3つの学力低下
さて、集中力は、ただ【じっと座っていられる力】ではありません。
それは【目の前の学習に意識を向け続ける力】であり、学力を鍛える上では欠かせない力です。
そして、この集中力が十分に育っていないまま勉強を続けていると、気づかないうちにじわじわと学力の低下を引き起こす可能性があります。
ここでは、集中力の不足によって特に影響を受けやすい3つの力について、具体的に解説していきます。
① 理解力の低下:【見ているのに分からない】状態
集中できていない子どもは、目の前の情報をしっかり受け取ることができません。
授業中、先生の説明を聞いていても、途中で気が散ってしまい、話の流れが途切れてしまう。
教科書を読んでいても、頭の中では全く別のことを考えている。
こんな状態では、当然ながら内容を理解することは難しくなります。
これは【ちゃんと聞いているはずなのに、なんでわからないの?】という親の疑問に直結するポイントでもあります。
子どもは聞いたつもり・読んだつもりであっても、理解に必要な情報を頭に入れるための集中状態に入っていないために、情報が正確に頭に届いていないのです。
その結果、基本的な説明や例題の意味を取りこぼし、授業の後半になるほどついていけなくなります。
こうして少しずつ、授業内容そのものが【わからないもの】になってしまうのです。
② 思考力・応用力の低下:【考えなくなる】習慣がつく
集中力がないと、思考が深まらず、複雑な問題に対する粘り強さも育ちません。
たとえば少し考えないと解けない文章題や図形の問題など、応用力が問われる場面になると、【わからない】【やりたくない】とすぐに手を止めてしまうのが典型的な例です。
【ちょっと難しいけど、頑張って考えてみよう】という姿勢が理想的ですし、そういう考えで勉強に取り組んでいければ思考力や問題解決力を育てます。
ところが集中力が足りないと、問題をじっくり読み込むこと自体が苦痛になり、【わからないものに取り組まない】習慣ができてしまいます。
これが続くと、やがて【難しい問題はやらない】【考えるのがめんどくさい】という思考回避型が定着し、
その子の伸びしろが奪われてしまうことにもつながります。
また、応用問題への苦手意識が強くなることで、定期テストや入試の得点力にも大きな差が出てきます。
③ 記憶の定着が悪くなる:【やっても覚えられない】原因に
勉強をしているのに内容がなかなか頭に入らない。
これも集中力が足りない子によく見られる現象です。
集中していない状態で文字や問題を見ても、頭が処理モードに入っていないため、情報が短期記憶のまま流れていってしまいます。
その結果、何度も同じ漢字を間違える、公式がなかなか覚えられない、語句がすぐ抜け落ちる、といった事態が繰り返されるのです。
とくに暗記系の勉強は、【集中して覚えたかどうか】で記憶の定着率が大きく変わります。
だらだら眺めていても覚えられず、【覚えられない→やる気が下がる→さらに集中できなくなる】という悪循環に入ってしまうのです。
このような状態では、勉強時間をどれだけ確保しても成果が出にくく、子どもの自己肯定感も下がってしまうので注意が必要です。
一見すると、学校の宿題もやっているし、塾にも通っている。
家でも毎日机に向かっている。
それなのに、成績は平均以下。
こうしたケースでは、ほぼ例外なく【集中の質】が低いことが原因になっています。
集中力が十分に育っている子は、短時間でも理解し、考え、記憶に残す学習ができます。
逆に、集中できない子は、どれだけ長く机に向かっていても、【入っていない・考えていない・覚えていない】の三拍子が揃い、努力が空回りしてしまいます。
この【集中力の差】は、最初は小さくても、時間が経つほどに成績という形ではっきりと差が開いていきます。
集中力を鍛えるために家庭でできること
ところで、集中力を鍛えるにはどうすれば良いのでしょうか。
【うちの子、集中力がないんです】と心配される方は多いですが、そもそも集中力は生まれつきのスキルの差は多少なりともあります。
ただ、集中力のベースの差はあるにしろ、日々の生活や学習の中で【育てていくことができる力】でもあります。
そして、集中力が身につくかどうかは、子ども自身の意識以上に、家庭環境や親の関わり方に大きく左右されます。
ここでは、家庭で無理なく始められる、集中力を育てる4つの具体的なポイントをご紹介します。
ポイント①:集中できる【環境】を整える
まずは、物理的な環境を見直すことが大切です。
集中力の弱い子は、少しの刺激でも注意が逸れてしまいます。
テレビの音、家族の話し声、スマホの通知、散らかった机。
こうしたものが視界や耳に入るだけで、脳はそちらに反応してしまうのです。
子どもが勉強する場所は、できるだけ静かで落ち着いた空間にしてあげましょう。
机の上は【今使うものだけ】に限定し、余計なものはすべて片づけます。
また、スマホやゲーム機などの誘惑は、勉強時間だけは物理的に見えない場所に置く工夫が必要です。
環境を整えることは、【集中しやすい条件をつくる】第一歩です。
ポイント②:短時間でも【集中の成功体験】を積ませる
集中力は、いきなり30分や1時間持続できるものではありません。
最初は5分でも10分でもいいので、【集中してやり切れた】という経験】を積ませることが大切です。
おすすめはキッチンタイマーなどを使って、【今から10分集中!】と時間を区切る方法です。
我が家の子ども①も集中力が短めな子でしたが、タイマーを導入してから勉強に集中する時間は格段に改善しました。
まず簡単にできるのが、【タイマーが鳴るまでは手を止めない】とルールを決めてスタートすることです。
短時間の集中ができたら、【今すごく集中できてたね!】とすぐに声をかけて、達成感や認められた感覚をしっかり伝えましょう。
このような小さな積み重ねが、【集中って気持ちいい】【やりきれる自分ってすごい】という自信につながっていきます。
ポイント③:【何のための勉強か】を言葉にする
集中力が続かない理由のひとつに、【目的があいまい】という問題があります。
ただ【宿題をやりなさい】【勉強しなさい】と言われても、子どもにとっては【なぜやるのか】が分かっていないことがほとんどです。
目的のない作業は、どうしても集中しづらくなります。
そこで大切なのが、小さくていいので【今日の目標】を明確にすることです。
たとえば、【このページの漢字を全部書けるようにする】【計算ドリルを10分以内に終わらせる】など、本人にも理解できる具体的なゴールを一緒に決めてから始めます。
さらに、終わった後に【この部分ができるようになったね】と一緒に振り返ることで、勉強が意味のある時間だったと実感できます。
ポイント④:ご褒美よりも【できた実感】を大切に
つい【終わったらお菓子あげるよ】【YouTube見ていいよ】など、ご褒美でモチベーションを引き出そうとする場面も多いかもしれません。
もちろん、適度なご褒美は悪いことではありませんが、【集中=何かをもらえる時間】になってしまうと、自主的な集中力が育ちにくくなります。
それよりも大切なのは、勉強を通して【できた!】【分かった!】という実感を持たせることです。
【さっきできなかった問題が、自分で解けるようになった】
【昨日よりも早く終わった】
【先生によくできたねと言われた】
こうした自分の成長を感じられる瞬間こそが、次の集中を生む原動力になります。
親がそれに気づき、ポジティブなフィードバックを与えることで、自然と集中する力が育っていきます。
どうしても、子どもに【集中しなさい!】と叱ってしまいがちですが、大切なのは叱ることではありません。
集中できる条件をつくることが、親にできる最も効果的なサポートです。
環境、時間の使い方、声のかけ方、そして目標の持たせ方。
こうした工夫が積み重なることで、子どもは【集中することが苦じゃない】【集中できると気持ちいい】と思えるようになります。
集中力は一朝一夕で身につくものではありませんが、日々の関わりで着実に育てていくことができます。
子どもの可能性を引き出すために、まずは今日からできる小さな一歩を、家庭の中から始めてみてはいかがでしょうか。
集中力があるかどうかは、子どもの学力の伸びに直結します。
理解する力、考える力、覚える力はすべて、【集中して学べているか】に大きく左右されます。
逆に、集中できないまま勉強を続けると、時間ばかりが過ぎて中身が伴わず、本人の自信ややる気も失われていきます。
けれど、集中力は鍛えられる力です。
学年が上がれば自然と身につくものではなく、今のうちから少しずつ育てていくことが大切です。
まずは、集中できる環境が整っているかを見直し、短時間の集中でも成功体験を積み重ねていく。
その一歩一歩が、やがて大きな学力の差につながります。
努力の量よりも、【どれだけ集中して取り組めたか】が大切です。
子どもの未来を支える鍵は、集中力にあります。
ぜひ今日から、家庭の中でできる工夫を始めてみてください。