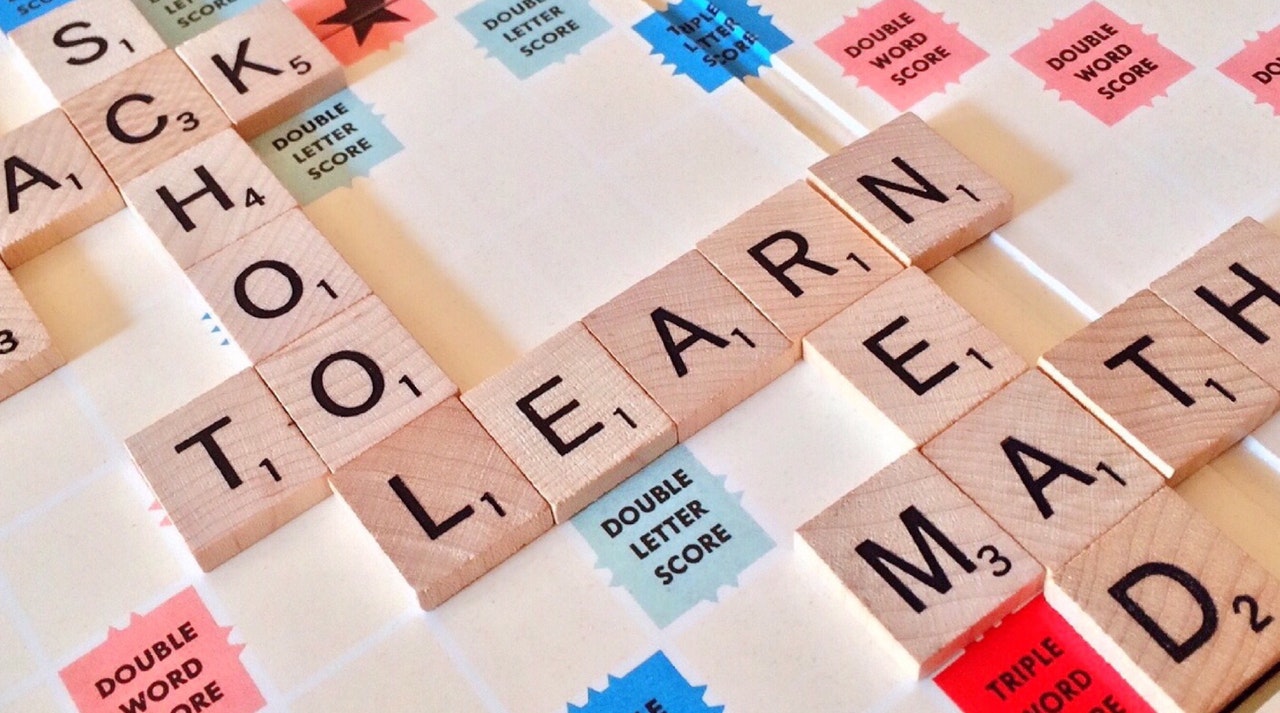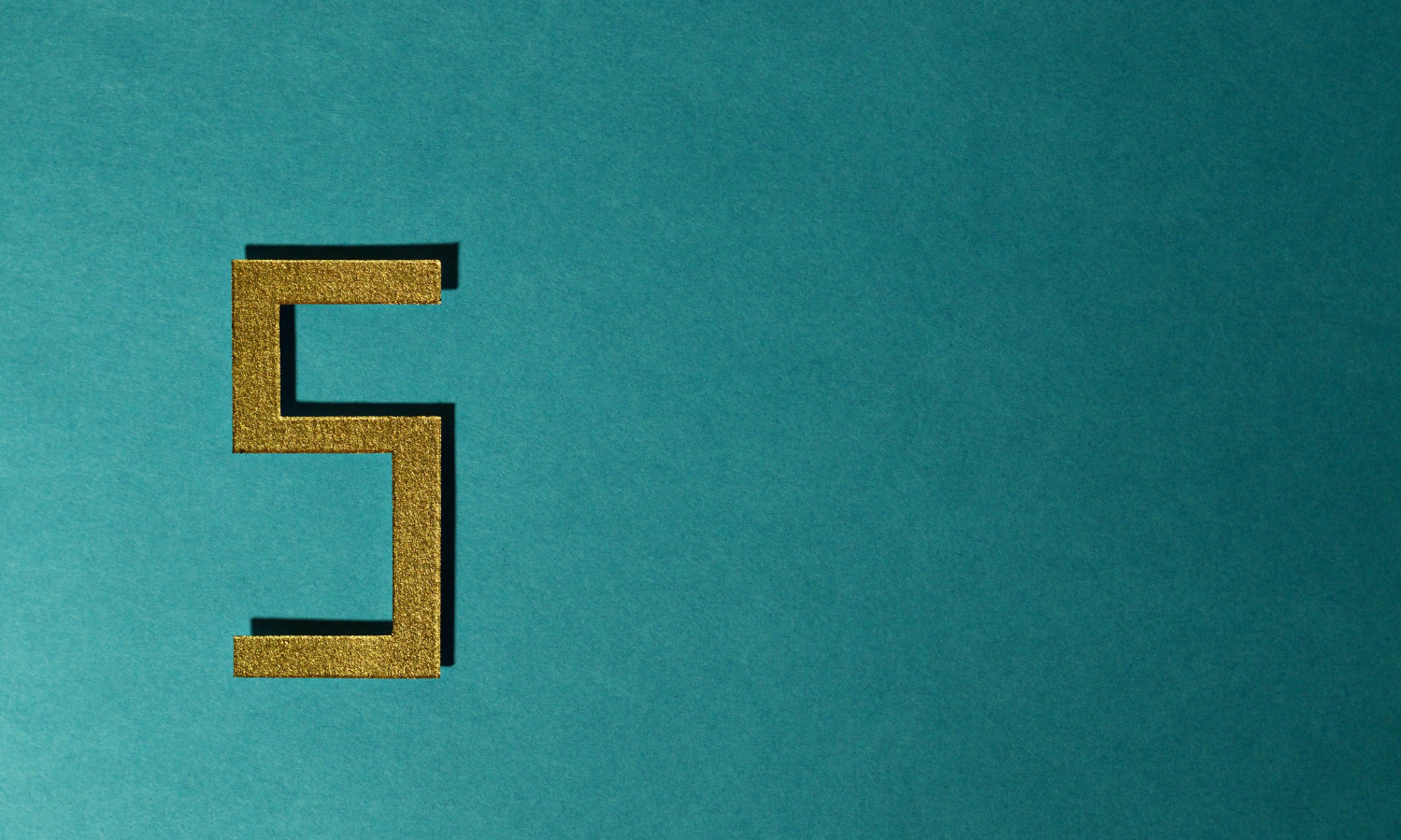今回は【小学生で方向性が決まる!目指す高校から逆算する学習戦略】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【中学から頑張ればいい】【うちの子はまだ小学生だから、勉強はそこそこで大丈夫】と考えている親はけっこういます。
私も塾で仕事をしている時に、夏休み前頃から夏期講習の問い合わせ、体験授業を希望する方が増えました。
その中でも印象に残っているのが、【中学生になって初めての定期テストで思った以上に悪い結果になった】【中学生になったら自分で勉強するかと思っていたがそんなことはなかった】というお母さんたちの声でした。
小学生と中学生とでは、たった一学年の違いなのに、勉強を取り巻く環境は全くの別物になります。
【中学に入ったらそれなりに勉強してそこそこの高校を受験する】と、そんなことを描いていたら、入学して数ヶ月も経たないうちに現実を知ることになった。
ミドル層より上の同級生は子どもと同じくらいだと思っていたのに、そうではないということも珍しくありません。
実は、高校受験における進路の方向性は、小学校高学年の段階である程度見えてきているのが現実です。
学校や塾でのテスト、模試の結果から、子どもが属する学力グループが形成され、そのグループ分けは中学に進んでも大きく変わることはありません。
もちろん、努力次第で逆転できるケースもありますが、それはごく一部です。
多くの子どもは、小学校で培った基礎学力や学習習慣、さらには【勉強に対する姿勢】や【性格的な問題】によって、中学入学後の成績がある程度予測できるのです。
加えて、中学では部活動や人間関係など、学習以外の負担も増えます。
【中学に入ってから頑張る】のでは、すでに学力の土台が固まっている子たちに追いつくのは容易ではありません。
だからこそ、小学生の今が重要なのです。
そこで今回は、なぜ小学校高学年から学力差が固定されやすいのか、中学での成績や受験校にどう影響するのかを解説しながら、家庭でどのように備えるべきか、塾の活用タイミングや志望校からの逆算の考え方まで、ご紹介していきます。
学力グループは小学校高学年でできあがる
まず、小学校高学年になると、子どもたちの学力差が徐々に明確になってきます。
小学校3年生くらいまでは【みんな横並び】に見えていた成績も、小学4年生を境目に、5年生6年生になると、テストでの点数の安定度や、応用問題への対応力に明らかな違いが出始めます。
とくに、単元テストや外部模試では、同じ問題を解いても【理解の深さ】【ミスの少なさ】が成績差に直結するようになります。
この時期にすでに差がつき始める理由は、【勉強の仕方】の差にあります。
ただ解くだけ、丸暗記するだけの子と、【なぜそうなるか】【どう応用するか】を考える学び方ができている子とでは、学びの質が大きく異なります。
さらに、家庭学習の習慣があるかないか、自分から学習に向かう姿勢が育っているかなど、学力の【土台】となる要素がこの段階で固まり始めるのです。
一度形成された学力グループは、中学に入っても大きく変わらないことが多いです。
中学では学習内容が一気に難しくなり、授業スピードも速くなります。
ここで重要なのは、【小学校の知識をどれだけ自分の言葉で理解しているか】。
暗記で乗り切ってきた子は、中学での思考型・記述型問題に苦戦しやすくなります。
一方、小学校から丁寧に考える習慣を持っていた子は、新しい知識もつながりとして理解しやすく、さらに伸びていく傾向があります。
もちろん、中学からの【逆転】も不可能ではありません。
ただしそれには、強い自走力、つまりは自ら計画し、行動し、改善する力が必要になります。
そして、困難な道のりでも成し遂げるという意志の強さも求められます。
私は中学から逆転した人間ですが、小学生時代の同級生で同じくらいの学力だったこの中で同じようにド根性で下から這い上がってきた子はいませんでした。
ですから、中学に入ってから頑張ればいいという考えは持たない、そして親も期待をしない方がいいです。
さらに、高校受験の実態を知ると、この【小学校高学年の学力層】がいかに重要かが見えてきます。
多くの都道府県では、中学1年生から内申点(通知表)が高校受験に直結します。
つまり、中学1年の初めからすでに受験は始まっているということです。
内申点は、一度下がると挽回が難しく、特に定期テストの結果が評価に強く反映されるため、【中学スタート時点で学力が整っていること】が合否を分けるカギになります。
もし、小学校高学年の段階で基礎学力が不十分であれば、中1の定期テストで高得点を取ることは難しく、その時点でトップ高校という選択肢が遠ざかってしまうのです。
また、多くの親が気づいていないのが、子ども自身が【なんとなくの実力】で自分の進路を決めてしまうリスクです。
小学校高学年で【自分はできない方だ】【勉強は苦手】と思い込んでしまうと、中学でもその自己認識が成績や志望校の選択に影響します。
本当は潜在能力がある子でも、【どうせ無理】と思ってしまえば、難関校を目指す選択肢そのものがなくなってしまうのです。
一方で、小学生のうちに【わかる喜び】や【努力すればできる】という成功体験を積んだ子は、中学に入ってからも意欲的に勉強に取り組みます。
結果として中1の成績が良くなり、内申も安定し、志望校の幅が広がるという好循環生まれます。
小学校高学年は、たしかにまだ義務教育の範囲内です。
しかし、この時期に身につけた学びの姿勢と基礎学力が、その後の中学生活、そして高校受験の【スタート地点】を決定づけるのです。
逆に言えば、今の取り組み次第で、中学での順位や志望校の選択肢を自分の手で広げることができるということでもあります。
親としては、テストの点数や偏差値の上下だけに一喜一憂するのではなく、子どもがどのように学び、どんな姿勢で知識と向き合っているかを観察し、必要に応じて軌道修正をしていくサポートが重要です。
そして、できれば高学年のうちから【高校受験】や【中学の学び方】を見据えた準備を始めていく。
それが、長期的に子どもを伸ばすための対策になります。
中学での成績は【学力】×【性格】で決まる
さて、中学に進学すると、勉強の難易度が一段と上がるのはもちろんですが、もう一つ見逃せない要素があります。
それが【性格】です。
私も塾で色々なタイプの子どもたちに接して感じましたが、中学の成績は小学生時代に築かれた学力だけでなく、その子の性格的傾向と学び方が大きく関係してきます。
中学になると、塾や学校の先生からのアドバイスを受ける場面が増えてきます。
ただし、子どもの方は思春期真っ只中で、大人に対して不信感や馬鹿にした態度をしてくる子もいます。
ここで成績が伸びる子は、自分の弱点や課題に向き合い、それを改善しようとする姿勢を持っている子です。
つまり、素直に先生の話を聞き、謙虚に自分の悪い点、改善したいところを受け止められることができる子は、修正力が高く、成績を上げやすいのです。
一方で、プライドが高く頑固な子、間違いを指摘されると不機嫌になったりして、改善する気持ちがほぼなく、学力が伸びない特徴があります。
また、言い訳をしたりするタイプの子は、アドバイスを吸収できず、楽な方に逃げて間違いを繰り返す傾向があります。
どんなに地頭がよくても、改善ができなければ徐々に周囲との差が開いていきます。
勉強は自分を変えていく行為ですから、他者からの働きかけにどう反応するかが中学では一層重要になるのです。
そして、どうしても、中学での学びは質が変化してくるので、それに対応する意識が成績を左右するところがあります。
小学生のときは、感覚的なひらめきや短期集中で何とか乗り切れていた子も、中学ではそれが通用しなくなってきます。
なぜなら、中学の勉強は【継続】が前提だからです。
予習・復習・小テスト・定期テストと、学びが連続的に積み重なる仕組みになっており、直前の詰め込みだけでは乗り切れません。
ここで強さを発揮するのが、いわゆるコツコツ型の子どもたちです。
毎日の宿題や課題をきちんとこなし、スケジュールを守って学習を積み重ねる姿勢は、テストごとの得点力に結びつきます。
定期テストで安定して高得点を取ることは、内申点に直結し、高校受験でのアドバンテージになります。
親としては、派手な成果ばかりに注目せず、【地味だけど確実な努力】ができる性格こそ、受験を勝ち抜く最大の強みだと理解しておくことが大切です。
性格以外にも、親も経験している中学生活では、ご存じの通り学習以外にも部活や交友関係など様々な要素が子どもを取り巻き、成績面への影響も少なからずあります。
その中で、学力を上げ続けられる子には共通点があります。
【もっとできるようになりたい】【今より上を目指したい】という気持ち=向上心があることです。
向上心を持つ子は、自分の弱点にも正面から向き合います。
苦手科目にも逃げずに取り組み、部活との両立も計画的に行い、失敗しても落ち込まずに立ち上がります。
こうした姿勢がある子は、着実に偏差値を上げていきます。
逆に、向上心が薄い子は【周囲と同じくらいでいいや】【今のままでも困らないし】という気持ちに流され、努力を怠りがちです。
中学では特に、環境に流される子と自分で進む方向を選べる子の差が如実に出ます。
結果として、高校選びも【行ける高校の中から選ぶ】のか、【行きたい高校に合わせて努力する】のかという、根本的な進路選択の差になります。
このように、中学での成績や進路は、小学生時代の学力だけでは決まりません。
【性格】という目に見えにくい要素が、成績の伸びや安定性に強く関わってくるのです。
親としては、子どもの努力の方向性や取り組み姿勢を日常の中でよく観察し、褒めるポイントを【結果】よりも【姿勢】に置いてサポートしていくことが、将来の伸びを決定づける大きなカギとなるでしょう。
志望校から逆算する!小学生のうちに親ができること
ところで、【高校受験はまだ先】【中学に入ってから考えればいい】と思われがちですが、実際には小学校高学年のうちに、ある程度の進路の方向性が決まっています。
だからこそ、子どものために親としてできることは、将来の選択肢を増やすために、今から逆算して動くことです。
ここでは、小学生のうちに親ができる3つの大切なことをご紹介します。
1.目指す高校を知ることが第一歩
まず大切なのは、【どの高校に行きたいか】を親がある程度イメージしておくことです。
もちろん、小学生の子ども自身に志望校の明確なビジョンはまだありません。ただし、親が地域のトップ校や2番手校の偏差値、内申点の基準、難関大進学率、教育方針、雰囲気やどんな部活があるかなど特色を把握しておくことで、家庭での教育方針が見えてきます。
例えば、偏差値65〜70のトップ校に進学したいと考えるなら、中学では学年トップ層に入り続ける必要があります。
中学のレベルが低ければ、模試の志望校判定でB判定以上を取れるようにするなどの具体的な目標を掲げつつ、中1から定期テストで450点以上を安定して取る必要があります。
さらに内申点を意識した提出物や態度の積み重ねも必要です。
このように、志望校に必要な実力を逆算して把握することが、小学校段階での準備の方向性を決める軸になります。
2.塾の活用は【いつ・どこで・何を学ぶか】が重要
次に考えたいのが【塾のタイミングと選び方】です。
中学受験をしないご家庭でも、高校受験を見据えた通塾は必要になるケースが多くなってきています。
ただし、ただ早く始めればいいというものではありません。
小学生の段階では、【中学内容の先取り】をするかどうかが大きな分かれ目です。
すべての子が先取り学習に向いているわけではありません。
むしろ、基礎を確実に理解し、思考力・表現力をじっくり育てる塾や教材を選ぶことが重要です。
また、高校も私立、公立によって出題傾向も異なります。
記述力を問う学校、思考型の問題が多い学校、内申重視の学校などの傾向に合わせた指導ができる塾かどうかを、早めに見極めておく必要があります。
さらに、塾だけに丸投げするのではなく、家庭と塾が連携して子どもの状況を把握しながら学習サイクルを作っていくことが、高校受験で安定して力を出すためのカギとなります。
私も塾にいた人間として断言できますが、塾に丸投げで子どもの成績に無関心という家庭の子で成績がかなり良いという子は皆無に等しかったです。
ですから、塾に入る際は【お任せ思考】になるのではなく、塾との連携ができそうかという視点も大切になります。
3.家庭で育てたいのは学ぶ姿勢と自走力
今の子育てでは塾のことを考えるのはオーソドックスになってきていますが、やはり塾や外部に頼るだけでは不十分です。
もっとも大事なのは、子どもが自ら学び、成長できる力=自走力を育てることです。
自走力とは、【自分で計画を立てて実行できる】【わからないことを放置せず、調べたり質問したりする】【失敗したらやり直す】という力です。
これは一朝一夕に身につくものではありません。
むしろ、小学生のうちに家庭での声かけや習慣づくりの中で、徐々に育っていくものです。
【今日はどこまでやるか、自分で決めてごらん】【この問題、どうやって考えたの?】と問いかける。
【間違えてもいいから、自分の言葉で説明してごらん】と促す。
こうした対話を重ねることで、自分で考える習慣と、挑戦を恐れない姿勢が育ちます。
また、成績が思うように伸びなかった時も、【どうしてダメだったの?】ではなく、【次はどうする?】と前向きに声をかけることで、子どもは失敗しても立て直せるという成功体験を積むことができます。
【学力】だけでなく【精神的な持久力】も、小学生期からの育ち方で大きく変わってくるのです。
小学生の段階で、将来の高校受験や学力の伸び方が決まってしまうわけではありません。
ただし、何の準備もなしに【中学から頑張ろう】としても、環境やペースの変化に飲み込まれてしまう子は多くいます。
子ども自身も、まだ小学生だと中学生になる未来や高校受験というのはまだまだ先のことで【その時になればなんとかなる】と考えている子が多いです。
そして、いざ中学生となった時にテスト結果を見て【自分の学力はこのくらいなんだ】と現実を知ることになります。
だからこそ、小学生の今こそが先を見据えて地盤を固める絶好のタイミングです。
将来の志望校から逆算し、必要な学力・性格・習慣を育てていくことで、子どもは中学でも高校でも、自分の力で未来を切り開けるようになります。
親としては、【今はまだ早い】と構えず、今だからできることに目を向けて、少しずつサポートしていくことが、最も確かな教育戦略になります。