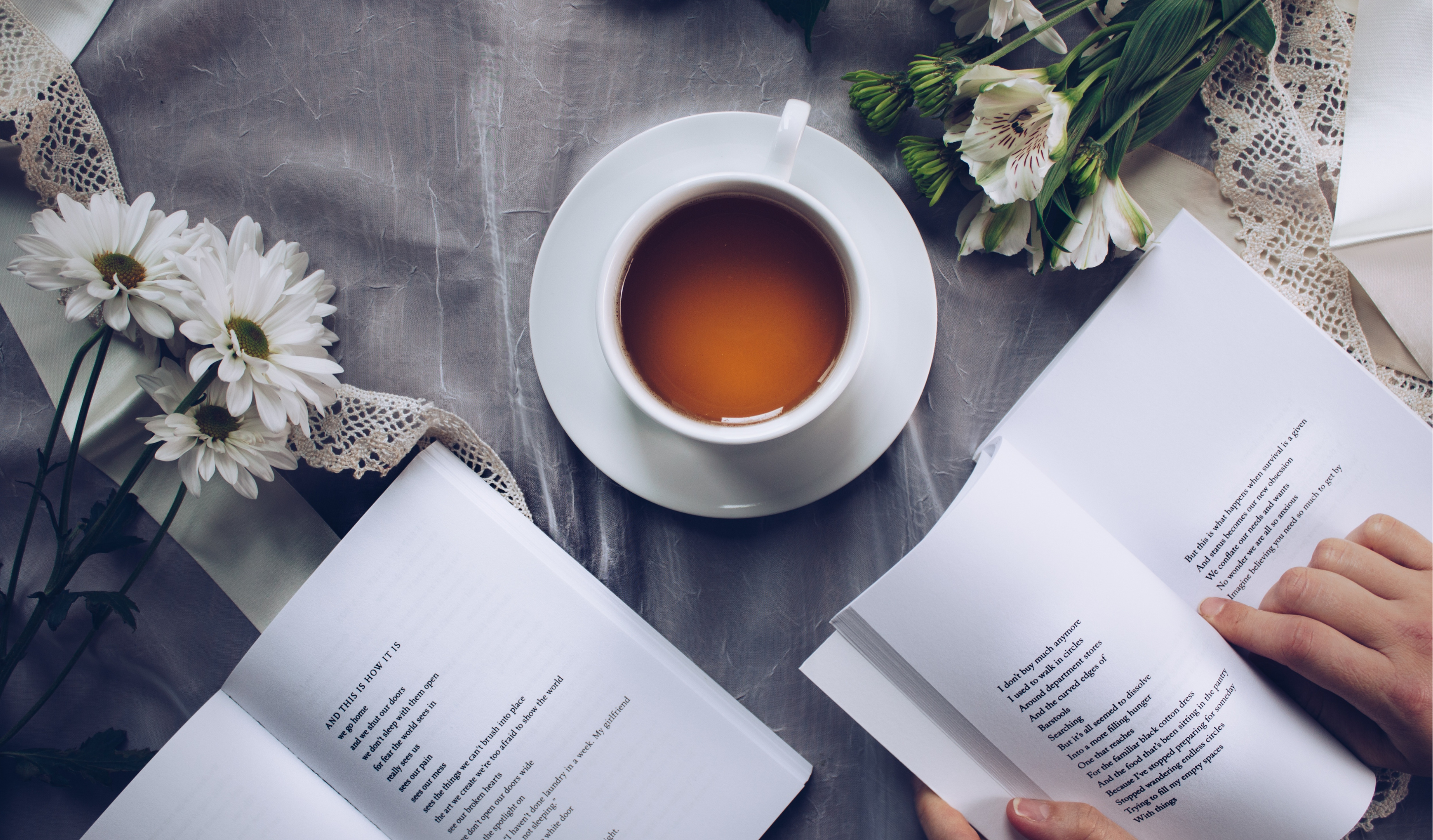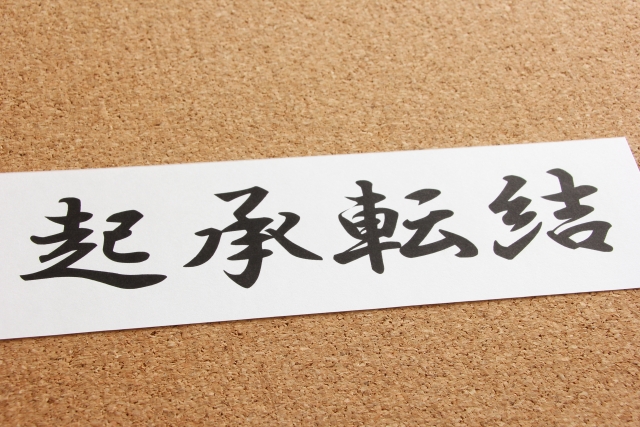今回は【小学生で成績が後伸びする子の特徴】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
成績が後から伸びて、先を走る子に追いつき追い越すという子は少なからずいます。
先頭を走る子にとっては脅威に感じるかもしれませんし、そういう子を持つ親からすると【どうしてこんなに伸びてきたのか】と不思議に思うでしょう。
親としては、【後からでも挽回できる力がある子はどんなタイプなのか】というのは非常に興味深いものがあります。
先を走る優等生の中には途中で息切れをし、【成績上位者】から脱落する子もいます。
脱落するには脱落する理由がありますし、それと同じように後伸びする子は後伸びする理由があります。
インターネット上にはたくさんの情報があり、それを見ては【うちの子はどうなのか】と一喜一憂する方も多いと思います。
子どもの伸び方というのは色々ありますし、情報通りに上手く成績が伸びる保証もありません。
ただ、【こういう特徴があると後伸びしやすい】と感じる子どもの性格というのは確かにあります。
子どもは成長するに伴い、自分の個性を強めていきます。
先を走ってきた子の中で成績が低迷する、下がる子は【親が誘導してきてそれに引っ張られてきたけれど引っ張られるのが辛くて耐えられなくなった】というタイプがけっこういます。
または、誘導されてきたことでその子に合った勉強法を子ども自身が色々と考えて構築していく経験が全くなく、勉強が難しくなる中で【分からなくなってきたけれど乗り越え方が分からない】となり、成績が下がる子もいます。
こういう子を尻目にグングン成績が伸びていく子はどのような個性を持っているのかをご紹介していきます。
言葉をよく知っている
まず、成績が伸びる子は会話をしていても【言葉をよく知っている】【会話のバリエーションが豊富】と感じることが多いです。
言葉はすなわち語彙力のことですが、語彙が少ないと会話の中身も単調となるだけでなく、学校で作文やレポートを書く時も一本調子になってしまいます。
しかも、子どもの語彙力というのは小さい頃から差がでています。
乳幼児期から小学校に入るまでの子どもの過ごす環境を考えると、保育所といった施設で過ごす時は【先生が絵本や紙芝居を読んでくれる】【先生の子どもへの声がけ】も基本的にはどの施設も大差はないので、得られる語彙というのもほぼほぼ平等だと思っていいでしょう。
差が出るのは家庭でどのような言葉を使っているか、読み聞かせをしているか、親子でどのような会話をしているかになってしまいます。
子どもの語彙獲得は家庭の力、親のサポートの部分がかなり強いです。
私も塾で仕事をしている時に、中学生の生徒と話をしていても【語彙力は相当な違いがある】というのはかなり感じました。
小学生でも、下の学年の子の方が知っている言葉が多いということもありましたし、言葉をよく知っている子ほど成績が良かったです。
会話もいつも同じことばかりになる、会話の広がりが見えない子もいました。
会話一つで全てが分かるわけではありませんが、狭い範囲での話で終始してしまうと広い世界を知らぬまま成長することになり、視野が狭くなってしまう恐れもあります。
子どもの語彙獲得は親の影響力が大きく、親が使う言葉の数が少なければ子どもが小さい頃から触れる言葉の数も限られてしまいます。
その反対に語彙力があるということは、本を読んでいる、親と色々な話をしていることを意味しています。
【豊富な語彙力】は裏を返せば知的好奇心が強く、知識をグングン吸収するタイプでもあるので、国語の物語文や説明的文章を読んでも【どんなお話なのか】と前のめりで読みます。
勉強を勉強と区切らず、たくさん知りたいことがあり、全てのことから学ぶという姿勢が強いです。
間違い直しや調べることを嫌がらない
さて、塾で仕事をしていると必ず生徒は問題を解いていると、間違える瞬間があります。
その時に感じたのが、【素直に間違える子と面倒だと文句を言ってやろうとしない子の未来の進路と学力の推移】の関係性でした。
これは年齢、学年問わずに【素直に間違え直しをした子は学力上位層をキープする、または努力家で学力が上がる子】でした。
一方、間違い直しをやりたがらず文句ばかり言ったり駄々っ子状態で授業時間をなんとか消費させようと必死な子は、たとえその頃は学力上位層でも徐々に成績が低迷していきました。
実際に、【この子は学力スキルが非常に高いな】と感じ、順調にいけばトップ高校に入って難関大学や有名大学に入るだろうと思っていた小学生が、間違い直しをやりたがらず、答えを聞きたがるタイプで、結局
3番手の高校に進学したというケースもありました。
成績を上げていく、学力を高い状態でキープするには【素直さ】がとても大切です。
素直に自分の間違いを認めてやり直しをしていくというのは、簡単そうに思えて子どもの性格では全くやろうともしない子もいます。
また、分からない漢字や言葉の意味が出た時、辞書で調べるよう指示した時も、自分で文句を言わずに調べる子がいる一方で、駄々をこねて先生から答えを引き出そうとする子がいました。
こういうタイプの子も成績は伸びにくくなります。
逆に、皆が面倒で避けている辞書引きを嫌がらずにやる子は成績が伸びやすいです。
意味調べは正直、私でも面倒だなと子どもが思うのは仕方がないと思っています。
ただ、その面倒さを【嫌だ】と全力で避けている子は遅かれ早かれ成績が伸びにくくなるというのを塾でも見てきたので、後伸びする子に少しでも近づくには【間違いのやり直しを嫌がらない】【ちゃんと自分で調べる】という気持ちを持てるかがカギを握っています。
勉強には前向き
ところで、成績が伸びるには【勉強をする】ということが不可欠です。
そして、勉強を自分からする気持ちがある、というのも成績の伸び率を高める要素の一つになります。
親が誘導して成績優秀者になる子もいますが、心の成長により【親に勉強させられてきた自分が辛い】と感じ始めれば、これまでとは勉強との向き合い方も変わっていきます。
自我が芽生えて勉強に対してどのような感情を持つかでその子の学力、成績が左右されることも珍しくありません。
たとえ小学生時代、クラスメイトの誰もが認める【賢い子】であっても、高学年や中学生になって勉強をやりたくない気持ちが強まって行けば成績は低下していきます。
後伸びする子は自分から学ぶ気持ちが強く、【勉強することで叶えたい夢がある】と思ってもいます。
そうした心が原動力となり、グングン成績がアップしていく子もいます。
塾でも驚異的な伸びを見せる子は【勉強することで自分の道を切りひらく】という固い信念を持っていました。
ちなみに、勉強に対して受け身かどうかというのは割と早い段階から差が出ています。
塾でも、【イヤイヤ連れてこられた子】と【親に言われたけれど塾の勉強も頑張る】にザックリと分けることができまいた。
【親に言われて仕方なく】と義務として勉強するという思いが強い子は、どうしても嫌だなというマイナスな気持ちで勉強するので、成績は上がりにくかったです。
面倒なので、間違い直しや調べることも消極的になってしまいます。
一方、勉強に対して【これは自分のため】【知らないことを知りたい】と感じている子は成績を上げることで発生する努力も抵抗感を抱きません。
結果としてこうした気持ちを持って勉強していれば自ずと成績を伸ばすことにつながります。
子どものやる気を引き出すことや、勉強に前向きになれるかどうかはお金を出して塾や家庭教師の先生にお願いすることもできます。
しかし、幼児期から【勉強をちゃんとやる子】に育てるには親の関わり方、サポート次第になります。