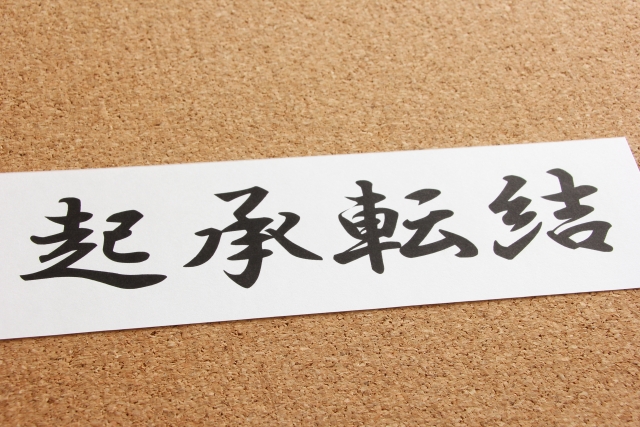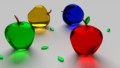今回は【中学でもトップ間違いなし?小学校で明らかに賢い子の特徴 PART2】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校のクラスの中には、【なんだかあの子、他の子と違うよね】と感じさせる子がいます。
私も小学生時代に低学年の頃から【違うな~】という子はいましたし、塾でも通っている小学生の中でも【他の子と明らかに違う】と感じる子はいました。
優等生だけれど、上辺だけの優等生ではなく、【あっ、この子はトップ高校に入って、そこでも上位層をキープして難関大、最難関大学に進むんだろうな】というのを醸し出している子です。
そういう子達は先生の話を聞く姿勢、友達とのやり取り、課題への取り組み方が、同年代の子と明らかにことなり、賢さがじわりとにじみ出ていました。
実はこうした子どもたちは、中学、高校と進学しても安定して高い学力を保ち、周囲から信頼を集める存在になることが多いのが現実です。
実際に、私も子ども時代にそんな風に感じた同級生、そして塾で出会った生徒も世間一般的には最難関大学に進んでいました。
一方で、小学校の頃は成績優秀でも、中学以降に突然伸び悩む子も少なくありません。
その差は、何によって生まれるのでしょうか。
【小学校のテストができる子】=【賢い子】ではなく、中学生になってからの学びに。
テストの点数だけでは測れない、もっと本質的な考える力や学びへの姿勢が、将来の成長を大きく左右します。
そしてそれらは、実は小学校時代からすでにあらわれているのです。
では、どんな行動や習慣にその【違い】が現れ、そして、親はその兆しにどう気づき、どんな関わり方をすればよいのでしょうか。
そこで今回は、学校生活の中で見られる賢い子の特徴、親の関わり方や習慣、そして伸び続ける子に備わっている非認知能力という3つの視点から小学校時代にこそ見抜ける【将来伸びる子の本質】についてご紹介していきます。
学校生活ににじみ出る【賢い子】の共通点とは
まず、小学校のクラスや塾には、【この子は伸びるな】【この子は違うな】と先生が感じ取るような子がいます。
テストの点数や発言回数よりも、その子の考え方や立ち振る舞いからそこはかとなく伝わってくるものがあります。
では、そんな【明らかに賢い子】は、どんな特徴があるのでしょうか。
実際の学校生活を例にその特徴を4つほどあげると、まず一つ目の特徴が、話の聞き方に【目的】があるということです。
賢い子は、先生の話をただ聞いているのではなく、【何を理解すべきか】【どこが大事なのか】を意識しながら聞いています。
話の途中でノートに図を書いたり、自分の言葉でまとめていたりと、受け身ではない能動的な聞き方をしている特徴があります。
話を聞いているかどうか、という中にも【内容を自分で咀嚼して理解できる子】と【ただ聞くだけの子】がいます。
賢い子は、先生の問いかけにも、ただ正解を答えるのではなく、【こう考えたけれど、違っていたらどうなるんだろう】といった思考の過程を見せるような発言が多く、深い理解を求めている姿勢がうかがえます。
二つ目の特徴は、間違いや失敗を【学び】に変える力があるということです。
テストで間違えても、悔しがるだけで終わらないのが賢い子です。
【なぜ間違えたのか】【どうすれば次はできるか】を自分で考え、間違いそのものを糧にしようとする態度が身についています。
このような姿勢は、親や先生の関わり方にも影響されます。
日頃から【失敗=ダメ】ではなく、【失敗=考えるチャンス】と捉える価値観が根づいている家庭では、子どもも自然と試行錯誤することに前向きになります。
この失敗を恐れないという考えは、小学校高学年以降の学力にダイレクトに影響してくると個人的に感じています。
子どもも自我が芽生えて精神面で成長してくるので【失敗したら恥ずかしい】という思いが強くなる子は、安定して解ける問題しかやりたがらなくなります。
なかには、賢くても答えを丸写しする子も出てきます。
こういう行動をとるようになると、学力を鍛えることは難しくなるので、【失敗を恐れない気持ち】を育てていくことは勉強させることよりも、ある意味大切です。
三つ目の特徴が【人との関わり方が柔らかい】という点です。
賢い子は、友達とのトラブルが少ないことが多いです。
これは、私も子ども時代に【トラブル発生率の高い子とほぼない子はなんだか学力が関係しているかも】と感じていました。
それくらい、人との関わり方と成績は関係しているなと思ってしまう場面に遭遇してきました。
賢い子は、感情のコントロールができて、しかも、自己主張が強すぎるわけでもなく、なりふり構わず同調するわけでもなく、*自分の意見を持ちつつ、相手の立場にも気を配れる【対話の力】が身についています。
また、同年代の子だけでなく、先生や年上の子、大人とのやりとりの中でも、言葉を選びながらしっかり話せる力が見られることがよくあります。
これは、家庭での会話の質が高いことや、日常的に【考えて話す】経験が豊富であることの表れです。
最後に、四つ目の特徴としてあげられるのが、【考える時間】が多いということです。
賢い子は、ぼんやりしているように見えても、頭の中で物事を整理したり、考えたりしている時間がしっかりあります。
たとえば、図工の時間に他の子がすぐに手を動かし始める中で、一人だけじっと材料を見ながら構想を練っていたり、発表の準備で【どう話せば伝わるか】をノートに書き出しているような姿が見られます。
算数の難しい問題も、腕組して頭の中で整理して、いきなりスラスラと答えにたどり着くまでの条件の整理を書き始めたり、式や答えを書き始めるというのも、【独特の考える時間】と言えるでしょう。
こうした【考えることを苦にしない子】は、単なる作業や暗記ではなく、創造的な学びに強い傾向があります。
改めて見てみると、【賢い子】とは、単にテストで満点を取る子ではありません。
自分の頭で考え、失敗を受け入れ、人と関わる中で学びを深める。
そうした日々の何気ない態度が、小学校という日常の中に確実に表れているのです。
親の関わり方に見る【伸びる家庭】の共通点
さて、小学校で明らかに【賢い】と感じる子どもたちは、家庭での親の関わり方に共通点があります。
教育費をかけているわけではなく、日々の小さな積み重ねや親の姿勢が、子どもの【考える力】を確実に育てているのです。
ここでは、伸びる子が育っている家庭に共通する5つのポイントをご紹介します。
まず、【勉強しなさい】と言わない家庭ほど、子どもが自然に学びます。
【うちの子には一度も勉強しなさいと言ったことがありません】。
こういう話は、中学受験、大学受験で難関校に受かったという話の中でよく取り上げられる話ではありますが、やはり、親が強制してやらせている子で学力最上位層、上位層に入るという子は進級進学するとどんどん減っていくというのは個人的に感じています。
最後まで上位層に残る子というのは、自主的に学習に取り組む姿勢が身についています。
その理由は、親が【勉強=義務】ではなく、【学ぶこと=面白い・意味がある】と伝える関わり方をしているからです。
小さなころから好奇心を育てるような声かけをしていたり、テレビやニュース、日常会話から疑問を引き出し、一緒に考えるような姿勢が日常にあります。
【これはなんでだろう?】という問いを共有し、考えるプロセスを家庭で楽しんでいるのです。
次に、読書と対話で【語彙力】と【思考力】が自然に育っていきます。
読書習慣がある子どもは、語彙力や文章理解力が自然に高まることはよく知られています。
しかし、伸びる家庭ではただ【読ませる】のではなく、読んだ内容について親子で話す時間をとても大切にしています。
【この登場人物はなぜこんな行動をしたのかな?】【自分だったらどう思う?】といった会話が、子どもの中で読書=考える力を育てる材料になります。
我が家の子どもたちは、地方の公立小のクラスの中ではそこそこ読解力、表現力のある方だと自認していますが、やはり小さい頃から独特な読み聞かせ、様々なジャンルの本を読んできて、親子の会話もかなりしてきた影響はあると思っています。
こうした取り組みは国語力だけでなく、理科や社会、さらには他人との対話力にもつながっていきます。
3人ともコミュニケーション能力は高い方に育ち、学校で人間関係でトラブルを起こしたことはなく、トラブル回避をしています。
三つ目のポイントは【間違い=ダメ】ではなく、【考えた証拠】として受け止めることです。
賢い子の親は、子どもが間違えたときに責めるのではなく、【よく考えたね】【ここでつまずいたのは、今の理解が深まっていないという証拠だよ】と声をかけます。
こうした言葉の積み重ねが、子どもにとっての間違えることへの安心感を生み出します。
間違いを恐れずに挑戦し、間違いから学ぶことができる子どもは、結果として学びが深くなります。
これは中学以降、応用問題や記述力が求められる学習において、大きな差となって表れてきます。
塾で仕事をしている時、小学校ではトップクラスの優秀だけれど、親が間違いを許さない、満点を取るのが当たり前というスタンス、という子達は、高学年以降は応用問題をやりたがらなくなる傾向が強まるという共通の特徴がありました。
こうなると、子どものためにはならないので、【間違いを許さない】は一旦捨てて、【間違いから学ぶ】という意識を親には持って欲しいと強く思っています。
そして、四つ目が習い事や家庭学習の選び方が【先回り】ではないことです。
先回りしてあれこれと詰め込みすぎる親よりも、子どもが【なぜそれをやるのか?】を納得し、自分で目的を持てるように支える家庭が、結果的に長く伸びます。
先回りし過ぎて、それが子どもを苦しめることにもなります。
実際、そういうケースを見てきました。
習い事との向き合い方というのは親の考えがかなり出てしまうところがあります。
賢い子の親は、たとえば、【英語を早く始めないと遅れる】と焦るのではなく、【英語って何のために使うんだろうね?】と問いかける。
【この塾に入れるべきか?】という選択も、【この子にとって本当に必要か?】という問い直しから始めて、検討します。
子どもの勉強も【どれだけ進んだか】より、【何を考えたか】【どう感じたか】に目を向ける姿勢が大切です。
最後、五つ目のポイントが、親が正解を与えすぎず、対話で考える力を引き出すように意識することです。
日常の会話の中で、子どもが何か質問してきたとき、すぐに答えを教えるのではなく、【あなたはどう思う?】【もし○○だったらどうなる?】といった問いかけを重ねる家庭では、子どもが考える時間が自然に育っています。
これは、学校での学びだけでなく入試での差がつく難問での対応力にも大きく影響します。
子どもは【誰かが教えてくれる】前提で動くのではなく、【まず自分で考えてみる】習慣を持つようになるため、初見の問題や未知の課題に対しても柔軟に対応できるようになります。
正直、親が賢くふるまう必要はありません。
大切なのは、子どもの考えを止めない関わり方を日々の中に取り入れていくことです。
そして何より、【学ぶことを親自身が面白がっている姿】を見せることが、子どもにとって何よりの刺激になります。
学力の先にある【本当に伸びる力】とは
ところで、小学校時代に【賢い子だな】と感じる子どもたちは、中学、高校に進んでも多くが安定して高い学力を維持します。
ただし、その賢さの本質は、単なる暗記力や計算の速さではありません。
変化の激しい社会で活躍するために必要な【思考力】や【主体性】、いわゆる非認知能力が、じわじわとその差を広げています。
かつては、暗記や反復練習による学力で、ある程度の進学や将来が保証された時代もありました。
しかし現在は、AIやICTが発達し、情報が簡単に手に入る環境が整ったことで、【知っていること】そのものに価値がある時代ではなくなりました。
今必要とされているのは、【どう使うか】【どう考えるか】という知識の活用力です。
我が家の子ども①②は国立中学に進学しましたが、学校でも【知識をいかに活用するかが問われる学びになっている】と先生からよく聞かされていましたし、実際の定期テストの問題でも【思考力重視型の問題】が多く出題されています。
つまり、ある知識を他の場面に応用したり、複数の視点から物事を捉える思考の柔軟性が不可欠なのです。
賢い子は、知識を単に詰め込むのではなく、【なぜ?】【本当だろうか?】【他に方法はあるか?】と、自分で問いを立てながら学びを進めています。
こうした学び方が、応用力や創造力に直結していきます。
たとえば中学受験では、計算や漢字といった知識系の問題だけでなく、【なぜそうなるのか?】【自分の考えを説明しなさい】といった記述力、論理的思考、自己表現力を問う問題が年々増加しています。
これは単に国語力や算数力の問題ではなく、普段からどれだけ自分の考えを持ち、言語化する訓練ができているかの差になります。
つまり、非認知能力が大きく関係しているのです。
公立中学の定期テストでも、教育レベルの高い地域の中学では暗記型などが多いと差が出ないので、【本当の学力】をみるような思考力重視の問題が出題されることもあります。
また、高校や大学進学においても、【志望理由書】や【探究型学習】の重視が進み、学力だけでなく【どんな姿勢で学んでいるか】や【どんな問題意識を持っているか】が評価される時代になってきています。
学びが急激に変化している時代でも伸びる子の大きな特徴は、【一度答えを出したら終わり】ではなく、考え続けられる粘り強さと好奇心を持っていることです。
【これはどういうこと?】【本当にこれでいいのかな?】と、自分の考えに自分で疑問を持てる力は、学習だけでなく、社会に出てからも不可欠な力です。
この姿勢があるからこそ、どんな分野に進んでも学びを深められるのです。
このような力は、テストの点数には表れにくく、見落とされがちですが、家庭や学校で子どもが自由に考え、対話できる時間が多ければ多いほど、自然に身についていきます。
AIがどんどん高度になっていく今、子どもたちが目指すべき姿は【指示を待って正解を出す子】ではありません。
むしろ、【何が問題なのかを自分で見つけ、どう取り組むかを考える子】、つまり自問自答してちゃんと動ける子が求められています。
そのためには、【この問題、どう思う?】【別のやり方ってあるかな?】と、大人が答えを与えすぎず、子ども自身に考えさせる関わりが重要になってくるのです。
また、子ども自身が【自分の考えに価値がある】と思えるような経験を積ませることも、自己肯定感や学習意欲の土台になります。
学力とは、単なる得点力ではなく、【どう考えるか】【どう学び続けるか】の力を含んだものです。
今、目の前にいる子どもの学力だけを見るのではなく、どんな姿勢で学んでいるのかに目を向けることが、将来本当に伸びる力を育てる第一歩なのです。