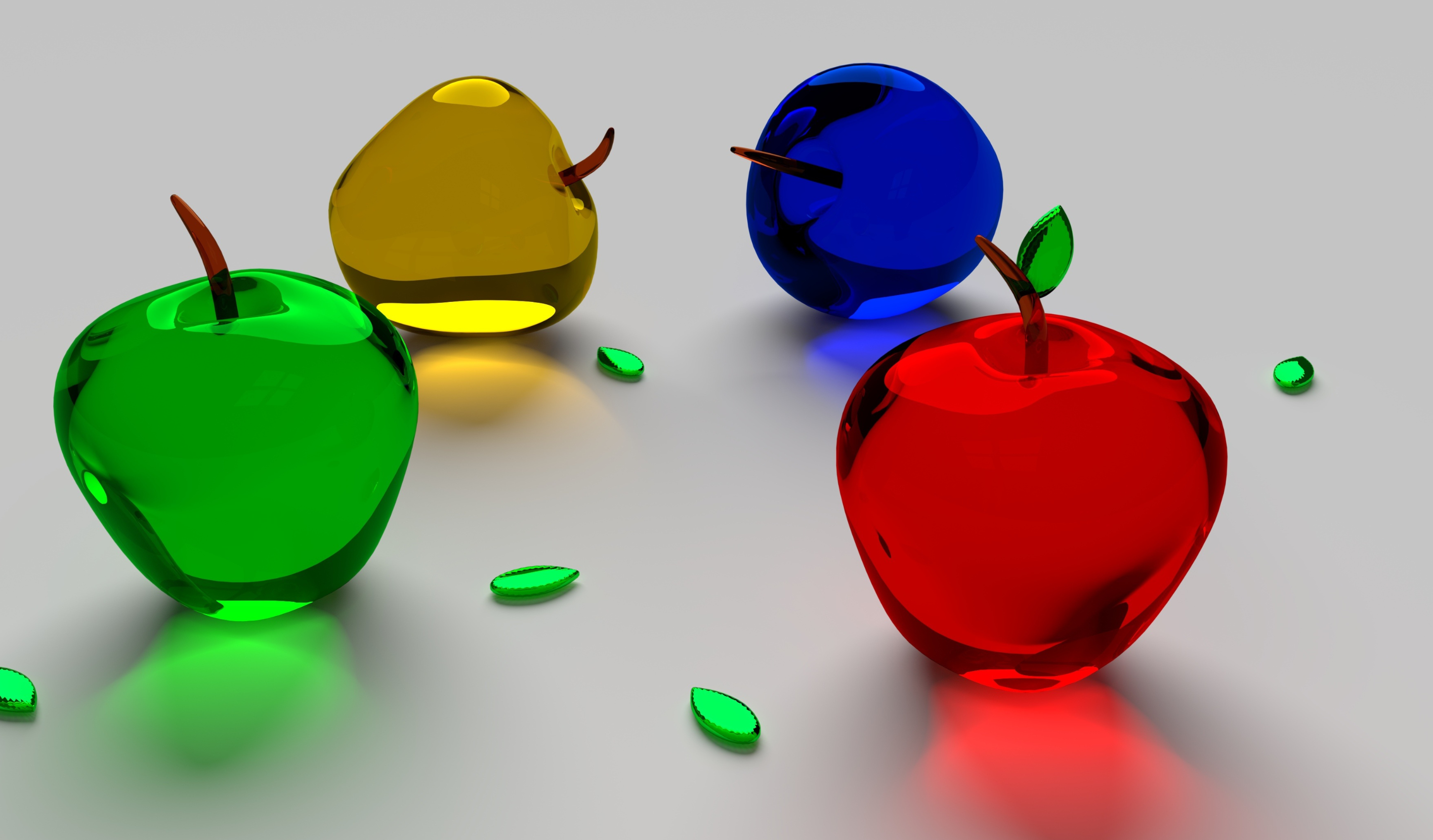今回は【中学でも安定して伸びる子に育てるために 親が今できること】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校のテストで高得点を取れているからと言って、中学でも同じように定期テストで高得点を取れるとは限りません。
また、【うちの子は90点台や80点台が多いから中学生になっても安心】とは思わないでください。
私も塾で仕事をしている時に、【小学生のときは成績が良かったのに、中学に入って急に伸び悩み始めた】といった声を耳にすることは少なくありませんでした。
反対に、小学校時代はどちらかといえば普通だった子が、中学に入ってから着実に力を伸ばし、上位層に食い込んでいくケースもあります。
もしくは、同じような成績だったのに片方は高校受験で地元でも有数の進学校に合格し、もう一方は中学進学後に成績を下げて偏差値52程度の高校に進学するということもありました。
なぜこのような差が生まれるのでしょうか?
その要因は、単に学力の高さや知識量ではなく、子ども一人一人の学びに向かう力、姿勢の違いにあります。
小学校までは、授業についていき、宿題をきちんとやっていれば、それなりに良い評価を得られる構造です。
しかし中学校に入ると、学習内容の量と難易度が一気に増し、定期テストや内申点を気にし、自主学習の習慣が求められるようになります。
つまり、【誰かに言われてやる勉強】から【自分で組み立てて学ぶ勉強】にシフトチェンジしないと、成績上位層にはなれない世界へと質が変わるのです。
この変化にうまく対応できる子は、ぐんぐん伸びていきます。
一方で、親に管理されていた子や、【やらされ型】の学習に慣れていた子は、早い段階で躓きが目立ち始めます。
我が子が、そういうタイプの子にならないことを望むばかりですが、中学生になってから何とかしようとしても思春期真っ只中で親の話を聞いてくれなくなります。
やはり、小学生の頃から対策をしていくことが肝要です。
そこで今回は、誘導型の勉強に慣れていた子を伸びる子にする方法に切り替えるために、親としてどのようなことに気をつければよいのかを考えていきます。
中学で【躓く子】の共通点
まず、小学校の学び方に慣れ過ぎているという傾向があります。
小学校の学習は、基本的に【指示通りにやる】ことが中心です。
授業は先生が導いてくれ、宿題も決まった内容をこなすスタイル。
テストも、習ったこと、しかも基本的な内容が多く、【授業で教わったことを覚えていればできる】という仕組みになっています。
しかも、テストは単元が終わったら時間を経たずに行われるので、コツコツ取り組む子や、指示に従うのが得意な子は、安定して高得点を取れます。
親から見ても【うちの子は真面目で優秀】と安心しやすい、というのが小学校の勉強です。
しかしこれは、小学校特有の学びであり、それが進学しても全く学びの構造が変わらないというわけではありません。
中学になると、勉強量が増え、複数教科を自分で管理しながら学習を進めていく必要があります。
部活と勉強との両立も大きな課題となります。
さらに、単元のつながりや知識の応用、思考を求められる問題が増え、【覚えれば何とかなる】だけでは通用しなくなるのです。
つまり、小学校のうちは【やらされた学習】でもそれなりに成果が出る環境だったために、自分で考えたり応用したりする力が育ちにくく、中学で【自分で考えて勉強できるかどうか】という差が一気に表れてしまうのです。
そしてもうひとつ、見逃されがちな躓きの要因として言えるのが、【失敗に慣れていないと伸びにくい】ということです。
小学校時代に成績が良かった子ほど、間違いや躓きに弱い傾向があります。
なぜなら、小学校の勉強があまりにスムーズだったため、【できない】という経験をほとんどしてこなかったからです。
私も塾でこういうタイプの中学生に何人も出会いました。
失敗の経験が少ないと、中学で初めて本格的に壁にぶつかったときに、必要以上に落ち込んだり、自信を失ってしまったりするのです。
私が教えた子どもたちも、【小学生の時はもっとできた】【どうしてここまで復習をしないといけないのか】とプライドが高く、自分の成績低下を受け止められないところがありました。
このとき、親が【なんでできなかったの?】【もっとちゃんとやりなさい】といった減点型の声かけをしてしまうと、子どもはますます【間違え=ダメなこと】と思い込みます。
そして間違えることを恐れて、復習を避けたり、新しいことにチャレンジできなくなったりするのです。
ご存知の通り、【間違えてもそこから学び取る力】が、学力を伸ばし続ける上では不可欠です。
しかしそれを育むには、小学生の頃からできたことばかりを褒めてきた環境から、【失敗しても大丈夫。そこから工夫していこう】という転換が必要なのです。
また、親に管理されている学びは進級進学を重ねて成績をあげていくには限界があります。
中学で躓く子のもうひとつの共通点が、学習管理の依存です。
小学生のうちは、親が宿題を確認し、勉強の段取りを整え、スケジュールを決めてあげていたケースが多くあります。
もちろん、それが悪いわけではありません。
むしろ小学生のうちは、ある程度の親のサポートは必要です。
ただし、その管理がずっと続いてしまうと、子どもは自分で【何を】【いつまでに】【どうやってやるか】を考えられなくなります。
すると、中学に入り教科数が増え、提出物、テスト勉強、部活動などを同時にこなす生活が始まったとき、【全部が親任せだった】という子は急に立ち行かなくなるのです。
中学生に必要なのは、何と言っても【自己管理力】です。
学習計画を立て、自分で進めていく力、困ったときに人に相談したり、復習の優先順位を決めたりする力が不可欠です。
これは、いきなり中学に入ってから身につくものではなく、小学生のうちに少しずつ【任せる経験】を積んでおくことが何より重要になります。
このように、中学でつまずく子には共通点があります。
【指示されたことはできるが、自分で学びを動かす力が弱い】こと。
そして、【失敗に対する耐性がない】さらに【親による管理に依存していた】というものです。
これらはどれも、小学生時代の学び方や親の関わり方の延長線上にあります。
中学になってから慌てないためには、今のうちから【考える力】【学習の自立】そして【間違いから学ぶ姿勢】を、少しずつ家庭の中で育てていく必要があります。
中学でも伸びる子が持つ【3つの学びの力】
さて、中学に入っても安定して成績を伸ばす子には、いくつかの共通点があります。
それは【地頭が良い】や【記憶力が高い】といった一人一人が持つ学力スキルだけではなく、自分の学びを自分で動かす力が備わっていることです。
一つ目が、【わからない】を自分で乗り越えようとする力です。
伸びる子は、わからない時にすぐに答えを求めるのではなく、まず自分で考えたり調べたりしようとします。
この姿勢こそが、思考力と問題解決力を育て、中学の複雑な学習にも対応できる土台となります。
たとえば算数の問題でつまずいたときに【なんでこうなるのかな?】【似たような問題はなかったかな?】と考える。
あるいは理科や社会で出てきた言葉がわからないとき、教科書や辞書を自分でめくって調べてみる。
このような【自分で探るプロセス】を繰り返すことで、学びに粘り強さが生まれます。
この力は、親の関わり方次第で小学生から十分に育てることが可能です。
たとえば、子どもが【これなに?】と聞いてきたとき、すぐに答えを教えるのではなく、
【どこかに書いてありそう?】【どうやって調べてみようか?】と声をかけてみてください。
最初はうまくできなくても、自分で考え、自分で調べる経験を積むうちに、学びに対して受け身ではなく主体的になっていきます。
次に、学びを自分ごととして捉えられる意識の有無の影響は大きいです。
学びに対して【やらされ感】がないことは成長するにつれて威力を発揮します。
伸びる子は、【誰かに言われたからやる】のではなく、【自分のために学ぶ】【できるようになりたい】という気持ちを持っています。
この意識は、生まれつきの性格というよりも、日々の積み重ねで育つ習慣です。
たとえば、小学生のうちから簡単なToDoリストを自分で書かせたり、【今日の勉強、どれを先にやろうか?】と選ばせたりすることで、自然と自分の学びを自分で管理する感覚が育ちます。
また、週末に【今週はどんな勉強をした?】【うまくいったこと・難しかったことは?】と一緒に振り返るだけでも、学習への自覚が生まれます。
親が手取り足取り指示を出すのではなく、問いかけて子ども自身に考えさせることが、自立心を促すことがポイントです。
自分でやる内容を決め、自分で振り返ることができる子は、たとえ中学で課題が増えても、自分なりの学習スタイルを築いて前向きに取り組むことができます。
そして、失敗や間違いに対する向き合い方も子どもの勉強への意欲を決定的にするポイントです。
中学生になると、テストや受験などで思うようにいかない経験が増えます。
そのとき、気持ちを切り替えて前に進めるかどうかが、大きな差になります。
伸びる子は、【できなかったから終わり】ではなく、【どうすれば次はできるか】と前向きに改善策を考える習慣を持っています。
それは、家庭で【間違えたことを責められなかった】【失敗を冷静に分析できる空気があった】からこそ育つ姿勢です。
たとえばテストでミスをしたとき、【なんでこんなことも間違えたの!】と叱るのではなく、
【どうしたら次は防げるかな?】と親子で一緒に考える。
このように、反省より工夫を重視した声かけが、子どもの学びを前向きにしていきます。
また、【努力してもうまくいかないこともある】と知ることは、実は非常に大切です。
努力と結果が必ずしも比例しない場面でも、心が折れずに再挑戦できる力、これが本当の意味で長期的に伸び続ける子どもを支える根幹になります。
中学で安定して伸びていく子どもは、ただ賢いのではなく、考える力、主体性、失敗を受け止める力という、地に足のついた学びの力を持っています。
そしてそれは、特別な才能ではなく、日々の関わりや家庭の空気から育っていくものです。
【先に答えを与えず、考えさせる】【自分で決める経験をさせる】【失敗に意味を見出させる】の3つの積み重ねが、子どもを中学でも伸びる子へと導くカギなのです。
親ができる【伸びる子の土台づくり】
ところで、中学で安定して伸びる子に共通する力は、日々の家庭の中で育まれます。
難しい教材を使ったり、特別な教育を受けさせたりしなくても、親のちょっとした意識と工夫で、子どもが学びに向かう力を自然に育てていくことは十分可能です。
まず、【できた、できなかった】より【どう考えたか】を問う習慣を持ちましょう。
【100点だったね!】【すごい、間違いゼロ!】、という結果を評価する声かけは一見良さそうに見えますが、子どもにとっては【正解すればそれでいい】が目的になってしまいがちです。
それよりも大切なのは、【どう考えたか】【どこでつまずいたか】に目を向けることです。
たとえば、テストで80点だったときに【どこが難しかった?】【どうやって考えたの?】と問いかけてみる。
たとえ間違っていても、【こういう考え方をしたんだね】と認めてあげる。
これにより、子どもは思考することが価値あることだと感じ、自分の頭で考える習慣が育ちます。
正解や点数だけでなく、考えたプロセスそのものを認める重要性が浸透していれば、ミスを恐れず挑戦できる思考力の土台を築いていきます。
次に、【勉強しなさい】ではなく、【学びに向かいやすい環境づくり】を重視してください
【勉強しなさい】と小言を言われて素直に机に向かう子は、そう多くありません。
大切なのは、自然と学びに向かえる環境を整えることです。
まず意識したいのは、物理的な空間です。
リビング学習でも自室でも構いませんが、テレビやスマホの通知音が常に鳴る場所では集中できません。
可能であれば【この時間は家族みんなで静かに過ごす時間】と決めて、親もスマホを控えるなど、共に集中できる空気感を作ることが効果的です。
さらに、学習のルーティン化もおすすめです。
たとえば、【朝5分で今日のやることを確認】【夜5分で1日の振り返り】といった習慣を通して、自分の学習を見える化し、振り返る機会を持つことで、自己管理力も自然と育っていきます。
言われてやるのではなく、自分で流れを作れる学習スタイルを家庭で支えることが、子どもの自立を大きく後押しします。
そして家庭に学びの空気をつくることは子どもにとって学ぶことの敷居をかなり低くするのでおススメです。
子どもに【勉強してほしい】と思うとき、多くの親は学習時間やテストの点数に注目しがちですが、もっと根本にあるのが家庭の空気です。
親が知的なことに触れている姿そのものが、最大の教育になります。
たとえば、読書や新聞を読む、時事ニュースに関心を持つ、資格試験の勉強をしている。
そんな親の背中を見た子どもは、【学ぶって当たり前のことなんだ】と感じるようになります。
また、日常の雑談の中に知的な問いをさりげなく入れてみるのも効果的です。
【どうして台風って夏に多いんだろうね?】【自動運転って将来どうなると思う?】、という会話から、学びは始まります。
目指すのは【勉強する子】にすることではありません。
そうではなく、【自然と学び続ける姿勢が身につく家庭】をつくること。
親が楽しそうに学んでいる姿、考えている姿が、子どもにとって最高のモデルとなるのです。
中学でつまずく子と伸びる子の違いは、単なる学力の差ではなく、【学び方の質】にあります。
中学以降に必要となるのは、自分で学ぶ習慣、失敗に向き合う力、思考を言語化する力。
これらを小学生のうちから少しずつ育んでいくことで、長く安定して伸びていく土台が築かれます。
親は【教える人】【管理する人】から【支える人】へ。
指示するより、任せる勇気を持つ。
その関わりの積み重ねが、伸び続ける子どもを育てる最大の力になるのです。