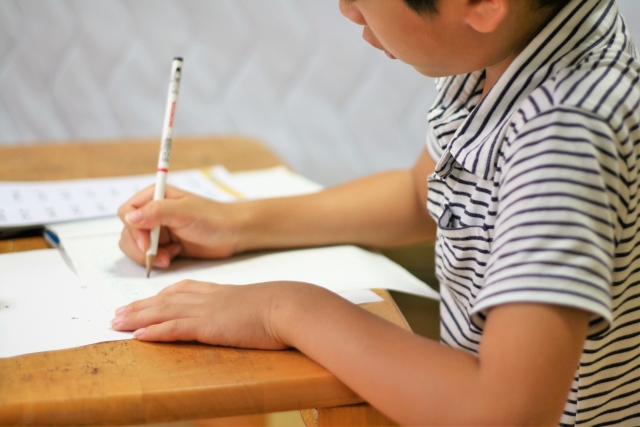今回は【小さい頃から分かる 伸びる子と伸びない子のシンプルな違い】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもが勉強をして伸びるかどうか、または受験学年になり勉強に本腰を入れていくと驚異的な勢いで成績を上げていく子がいたる一方で、成績が低迷していく、勉強している割には停滞期が長くて志望校を下げないといけない、という子もいます。
伸びる子と伸びない子というのは親にとっても気になるテーマだと思います。
ただ単に勉強しているかしていないだけの違い、というわけでもない面もあります。
とくに後伸びタイプの子が追いかけてくるというのは、先を進んでいる子を持つ親からすると恐ろしいことであり、【あの子達に負けないようにするにはどうすればいいのか】と考えたり、子どもに叱咤激励をする方もいることでしょう。
塾で仕事をしていると、【この子は伸びるな】【この子は今は成績が良いけれどいずれ停滞する】というのが分かる瞬間がありました。
おそらく、教育関係の仕事に就いたことがある方なら感じ取ることができる職業病のようなものだと思います。
現在、子育てをしている一人の親としては【うちの子は伸びるのか】というのを時折考えながら接することもありますし、、なんとか【伸びない子】にならないよう気をつけてはいます。
一般的に【伸びない子】と聞くと単に勉強しない子、というイメージを持っている方が多いと思います。
しかし、塾で仕事をしていても強く感じたのが【学習量うんぬんよりも大切なことがある】ということでした。
そして、教育関係の仕事に就いた経験がない方でも簡単に見抜くことができます。
今回は伸びない子と伸びない子の違い、特徴をご紹介していきます。
悪い言い訳をしない
まず、伸びる子は悪い言い訳をしません。
そして、伸びない子は言い訳をしてばかりです。
これは塾で色々な年齢、学力層の子に勉強を教えてきましたが、本当に面白い位の違いがありました。
悪い言い訳とは、【自分に非があるのにそれを認めない】【他人のせいにする】【言い訳をしてその場をしのごうとする】というものです。
逆に良い言い訳は【解き方がどうしても分からなかったので】とか【自分のレベルよりも高い問題であまり進めることができませんでした】と自己分析をしっかりした上での言い訳です。
そして、勉強をできなかったこと、宿題ができなかったことに対して伸びる子は【できませんでした】と謝り、その日の宿題を【やれなかった分と新しく出される宿題をやります】と自分から提案し、次回にはキッチリ終わらせてきました。
宿題ができなかったのは、部活の大会が目前に迫って勉強する時間が取れなかった、体調を崩して学校を休んでいた、という【納得できる理由】があるのですが、100%そのことを理由にせず、【やれなかった分はちゃんとやります】という姿勢で勉強と向き合っていました。
言い訳をしないというのは、【約束を破らない】という気持ちを常に持っていることの証です。
伸びない子は【できなかった理由ばかり探す】という特徴があり、それは小学2年生でも、中学3年生でも、高校生でも伸びない子に見られる特徴でした。
【やればできる】のに最初からやろうと努力していないので、【できない理由を考える】ということばかりに力を入れてしまい、結局勉強しないのが当たり前、勉強しなくても何とかなるという考えをも持つようになります。
子どもがどのような言い訳をしているのかを振り返ってみてください。
自分の保身に走り、やれない自分に非があることを認めないような発言ばかり繰り広げている子は、成績が伸びない子になってしまうので気をつけてください。
先延ばしをしない
さて、伸びる子と伸びない子にはこの他にも性格的な違いがあります。
それが【先延ばしをするかしないか】という点です。
これは色々な子どもと接してきただけでなく、自分の子ども時代、そして子ども①②③の子育てで出会ってきた子どもたちを振り返っても、【なるほどな】と感じることが多々あります。
まず、塾で出会った子ども達の中には当然ながら【宿題やるのが面倒】と取り組むのを先延ばしにし、次の授業の前日に親に叱られながら勉強する子もいました。
そういう子達は小学生でも中学生でも【あまり伸びない】という傾向がありましたし、進学校を受けて合格する子達の中で先延ばしをするタイプの子は皆無でした。
成績が伸びる子、学力が高い子は【宿題も自分のペースで取り組む】【自由時間を確保するために早々に宿題を片づける】という行動が出来ていました。
我が家では、【宿題を終わらせないと友達と遊べない】というルールを決め、その他にも【漫画や本を読む前に宿題を終わらせる】にもしています。
最近は、子ども①②は【宿題をする前に少し本を読む】ということもしていますが、それも【先延ばしをしない】という習慣が定着し、本を読んでいてもキッチリ時間や区切りの良いところで切り上げることができているからです。
先延ばしをすると、計画を立てて行動する習慣が身につきません。
親と口げんかする回数も増えます。
実際に、子どもがなかなか学校の宿題をやろうとせずに、毎日親子でバトルを繰り広げていると悩んでいる方もいました。
先延ばしをしてしまうというのは、忍耐力がないという捉え方もできます。
勉強をする、成績を上げる、受験期を乗り越えるには【忍耐】ということが求められます。
昭和的な言葉かもしれませんが、どんな分野でも上達するには努力を続けること、そして結果が出るまで忍耐するということが不可欠です。
先延ばしをしてしまう子は、こうした部分が欠落しているので、まずは【頑張って続けること】【ダラダラ過ごさずに取り組むまでの時間を早める】ということをカレンダーなどで書き込んで努力を視覚化していき、先延ばしをしない子へと変身させていきましょう。
ウソをつかない
そして、学力が伸びる子はウソをつかず素直です。
【この問題が解けなかったのはこういう理由があるから】と分かっていて、できなかった自分を誤魔化しすることもしません。
素直なので、間違えた問題を受け止めて解けるようにしたいと、真面目にやり直しをします。
成績を上げていくには自分の弱点を見つめ、改善していくために対策を考えて日々の勉強を続けていくしかないです。
【自分が苦手なところがある】ということを把握しているので、苦手克服にも自然と向き合うようになります。
子どもでもウソをついていいかどうかという判断は小さい頃からできます。
ですから、【ウソをついても仕方がない】と理解している子、ウソをついても誰の得にもならないことを分かっている子は、勉強面でもそういうことがプラスにならないと理解しているという印象があります。
一方、伸びない子はその場しのぎのウソをついたり、【分かったけど時間が足りなかった】と分からない事実を誤魔化し、なんとか勉強させられないよう知恵を絞るような発言をします。
また、ウソをつく子というのは、たとえ明るい性格であっても、学年が上がると【ウソばかり言う】【責任感がない】とみなされ、信頼を勝ち取ることができず、周囲の同級生も上辺だけの付き合いをするようになります。
ウソをつかれてばかりだと、その子のことを信頼することもできません。
受験学年になり、同じ志望校同士の子達は一緒に自習室で勉強をして【負けてられない】と切磋琢磨していきます。
ただ、ウソをつく子はこうした仲間には入れないことも多く、孤独な戦いになる様子も見たことがあります。
そういうのを見ていると何となく寂しい気持ちにもなりますし、でも【身から出た錆】でもあるので、ウソをつくことをしないよう子どもに話をしていきたいですね。