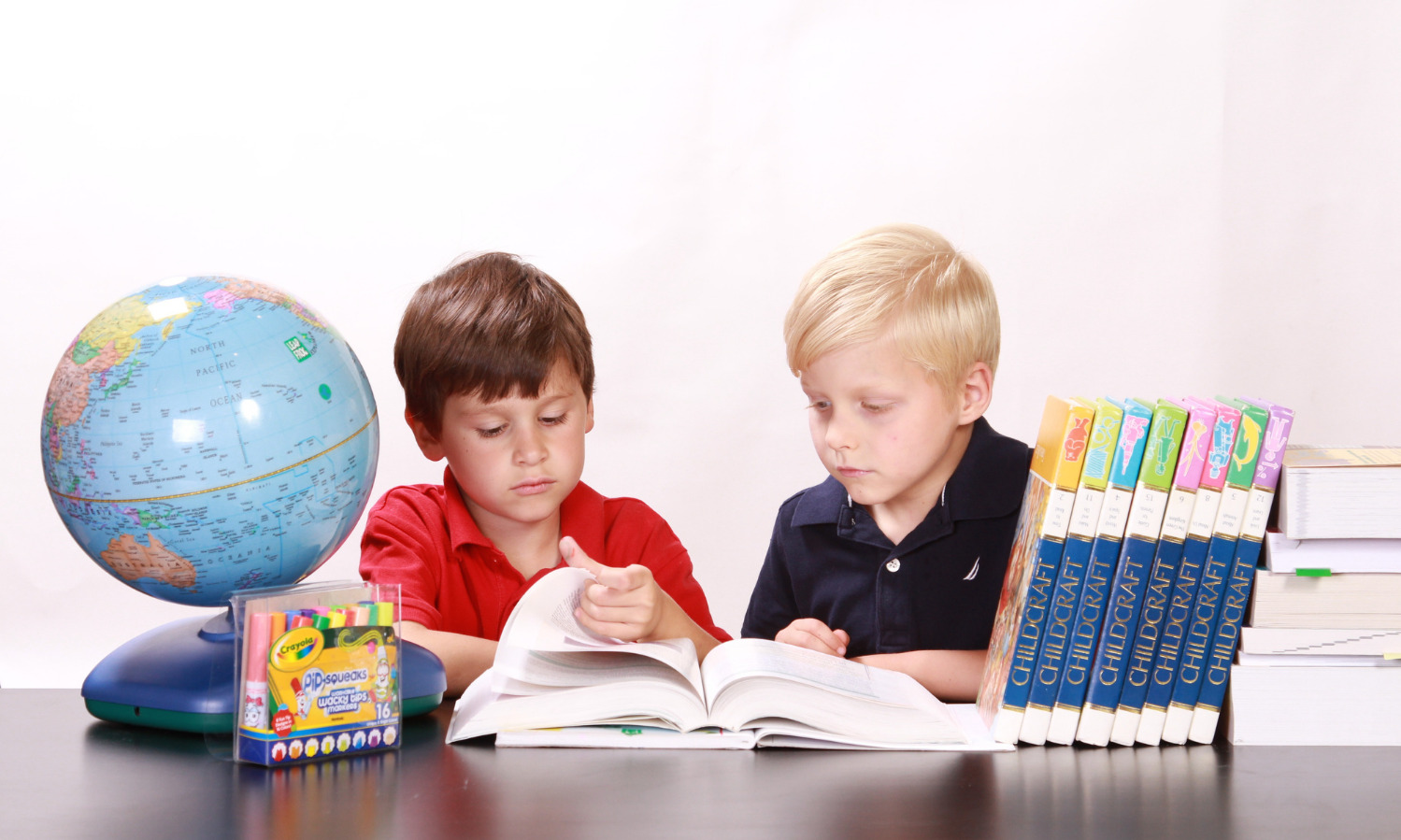今回は【小3が分かれ道!算数の苦手を作らないために今すぐ見直したい習慣】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【算数の苦手意識が出てくるのは4年生や5年生から】と言われることが多いですが、実際には3年生での理解力の差がその後の得意・不得意を分ける分岐点になります。
小3では、九九や筆算といった基礎計算を終え、本格的に【考える算数】へと学びがシフトしてくる学年です。
文章題、長さ・重さ・時間の単位、図形、分数の導入など、思考の幅を求められる単元が一気に増えます。
この時期に【わかったつもり】【答えが合っていればOK】で進んでしまうと、4年生以降に壁にぶつかります。
一方で、3年生のうちに【考える楽しさ】や【理解して解く感覚】を身につけておけば、算数への苦手意識を持つ子が増える高学年でも算数が得意な子に育っていきます。
そこで今回は、まず小3がなぜ重要な分岐点なのかを整理し、そのうえで高学年でも算数を得意に保つための3つの対策、さらに家庭でできる学習のコツを紹介します。
焦らず、でも確実に。子どもの算数力を【伸びる土台】から育てていきましょう。
なぜ小3が算数の分かれ道なのか
多くの親が【算数の壁は4年生から】【5年生の算数で苦戦している】と感じていますが、実際にはその差は3年生の終わりにはすでに生まれていることが多いのです。
小3では、これまでの【見て覚える】【手を動かして計算する】学びから、【考えて理解する】学びへとステージが変わります。
親が色々と気にかけて勉強させてきた九九や筆算といった計算に加え、グラフ・長さ・時間・分数・小数といった、数の意味を考える単元が増えます。
つまり、小3は【算数の抽象化】が始まる時期です。
ここでつまずくと、表面的に答えを合わせられても、考え方が曖昧なまま進んでしまいます。
それが4年生以降、がい数、図形、割合・面積・速さといった一歩進んだ学びで一気に表面化するのです。
また、この学年は勉強習慣や集中力が安定してくる子もいる一方で、学びに対する自信やモチベーションの差も出始めます。
算数が【わかる】【楽しい】と感じられるか、【難しい】【苦手】と感じるか。
この時期の体験が、その後の学習意欲を左右します。
ここからは、小3が算数の分かれ道になる3つの理由を、より具体的に見ていきましょう。
理由①抽象的な思考が求められ始める
小3からの算数は、それまでの【目で見える算数】から【考えて理解する算数】へと変化します。
たとえば、1年生では【りんごが3個あります、もう2個買いました】というように、具体的なイメージで問題を理解できます。
しかし3年生では、こうした条件をもとに【グラフを書いてみましょう】など、頭の中で数量を関係づける力が必要になります。
ここで問われるのは、単なる計算力ではなく、数の意味を理解する力です。
【なぜそうなるのか】【どんな関係があるのか】を説明できることが、真の理解へとつながります。
この【抽象的思考】は、算数だけでなく理科・国語・社会にも広く影響します。
文章を読んで状況をイメージしたり、データをもとに考察したりする力は、すべてここで育つからです。
もし3年生で【式は書けるけど、何をしているのかわかっていない】状態を放置すると、4年生以降で問題の意味を読み取れなくなり、算数が急に難しく感じられるようになります。
この時期こそ、【数の関係を考える】学び方への切り替えが必要だと親の方も受け止めてください。
理由②学習内容のつながりが一気に強くなる
3年生の算数では、分数・小数・単位・グラフなど、すべてが後の学年の基礎となる単元が詰め込まれています。
この段階での理解が浅いと、4年生以降の内容が【ものすごく難しい】に変わり、応用が効かなくなってしまいます。
たとえば、3年生で登場する分数は、5年生で学ぶ【割合】の土台です。
1/2や1/4の意味がわからないと、【100gの半分】【120円の4分の1】などの感覚がつかめません。
また、小数もお金や速さ、面積など、多くの単元に直結します。
ここで小数と分数の関係が曖昧なまま進むと、後の【比】【単位換算】で混乱します。
さらに、3年生からは【式を立てる】力が重視され始めます。
つまり、ただ答えを出すだけでなく、【なぜその式になるのか】を説明できる力です。
これが定着していれば、どんな応用問題にも対応できる算数の筋力が育ちます。
学年が進むほどに新しい単元が既習の内容を前提とするため、3年生の理解度こそが後々の学力の差を生む根っこになります。
理由③勉強の習慣と自信が定着する時期
小3は、学習習慣や自信のベースが固まり始める時期です。
低学年では、家庭や先生のサポートに頼って学んでいた子も、3年生頃から【自分で勉強する】姿勢が少しずつ形成されていきます。
だからこそ、この時期の成功体験が【勉強は楽しい】【自分でもできる】という自己肯定感につながり、反対に失敗体験が【どうせ自分はできない】という苦手意識に直結します。
とくに算数は、正解・不正解が明確な教科。間違えることを恥ずかしいと感じてしまう子も多く、【できない】経験が続くと、学ぶ意欲を失いやすいのです。
一方で、小さな【できた!】を積み重ねていけば、自然と自信が生まれ、挑戦する意欲が育ちます。
この段階では、結果よりも過程を大切にしましょう。
たとえば、答えが間違っていても【考え方は合っていたね】と認める。
計算ドリルよりも、【どうしてそう思ったの?】と考える時間を一緒に持つ。
それだけで、子どもの中に【考える力】が根づいていきます。
3年生は、勉強の習慣・意欲・思考力が三位一体で育つ時期。
ここを大切に過ごすことで、算数に強い学びの姿勢が自然と形成されていきます。
高学年でも算数が得意でいられるための3つの対策
さて、高学年になると、算数の内容は一気に難しくなり、分数・小数・割合・速さ・体積など、複数の概念を組み合わせて考える力が求められます。
この時期に算数が得意なままでいられる子は、共通して【基礎の確実さ】と【考え方の整理力】がしっかりしています。
つまり、算数の実力は土台の厚さで決まるのです。
いくら応用問題を解いても、計算や概念があやふやでは理解が深まりません。
逆に、基礎が安定していれば、どんな難問にも【どう考えたらいいか】が見えるようになります。
そのために意識したいのが、①正確な計算力の維持、②分数・小数の感覚的理解、③文章題を読み解く力の3つです。
この3要素は、ただの練習量ではなく、【どう定着させるか】という質の面が重要です。
ここでは、それぞれを家庭でもできる工夫を交えながら、具体的に解説します。
算数が得意でいられる子に共通する考える習慣を、毎日の中でどう育てていけるかを見ていきましょう。
対策①確実な計算力を維持する
計算力は、算数のすべての基礎です。
高学年になると【もう計算ドリルは簡単だから】と省かれがちですが、基礎計算の正確さが思考力の土台になります。
なぜなら、文章題や応用問題では、複雑な思考を行う前提として計算処理を正確に行う必要があるからです。
ここで大切なのは、【速さ】ではなく【正確さ】。
速く解こうとするとミスが増え、理解より作業になってしまいます。
ゆっくりでも1問1問の意味を確認しながら、確実に答えを出す練習を習慣化することが大切です。
また、毎日少しずつ続けるのが効果的です。
1日5分でも、筆算や暗算をコツコツ行うことで、脳が【数の感覚】を忘れません。
九九や基本の四則計算を繰り返すことは、スポーツで言えば基礎トレーニングのようなもの。
一見地味でも、後の応用力を支える筋肉になります。
【基礎計算は退屈】と感じる子には、計算アプリやタイムチャレンジなどでゲーム感覚を加えるのもおすすめです。
楽しみながら正確さを磨くことが、算数の得意を長く保つ秘訣です。
対策②分数・小数を感覚で理解する
算数で苦手が広がるきっかけの一つが、【分数】と【小数】です。
これらは単なる記号ではなく、量の感覚を伴って理解すべき内容です。
しかし、多くの子が【1/2=0.5】【3/4=0.75】と機械的に覚えるだけで、実際の意味を理解できていません。
ここで意識したいのは、体験を通して数を感じ取る学びです。
たとえば、料理で【1/2カップ】【1/4切れ】といった表現を使い、ペットボトルを比べて【0.5Lと1.0Lの関係】を体感する。
こうした日常的な体験が、数字の裏にある量のイメージを育てます。
また、分数と小数をつなげて理解させることも大切です。
【1/2=0.5】【1/4=0.25】といった対応関係を、数直線や図で視覚的に見せると、抽象的な数が見えるようになります。
こうした経験を重ねていくことにより、後で学ぶ割合・単位換算・比などの学習がスムーズに進む手助けになります。
数字を【ただ数を表すもの】ではなく【意味を持つもの】として捉えられれば、算数の楽しさが広がります。
感覚と理論をつなぐことこそ、高学年でも算数が得意でいられる最大の鍵です。
対策③文章題を【考えて整理する】力をつける
文章題が苦手な子は少なくありません。
多くの場合、【計算はできるのに、問題文の意味がわからない】というケースです。
つまり、つまずきの原因は国語力と論理力の不足にあります。
文章題を得意にするためには、まず【問題を読む】段階で止まらないこと。
ただ読むのではなく、【何がわかっていて、何を求められているのか】を整理することが大切です。
紙の上に図や表を書き、条件を視覚化する習慣をつけましょう。
また、問題を解いたあとに【なぜこの式を立てたのか】を言葉で説明させるのも効果的です。
説明することで、自分の考えの流れを客観的に見直せるようになり、論理的な思考が定着します。
家庭では、【どうやって考えたの?】と聞いてあげるだけでも十分です。
正解・不正解よりも、考え方に焦点を当てる関わり方が、子どもの思考力を育てます。
算数は【答えを出す教科】ではなく、【筋道を立てて考える教科】。
文章題を整理しながら解く習慣をつければ、応用問題にも自信を持って取り組めるようになります。
家庭でできる3つの学習のコツ
ところで、算数の得意・不得意は、才能ではなく【家庭での関わり方】で大きく変わります。
学校で学ぶ時間は限られていますが、家庭では安心して間違えられる場をつくることができます。
この環境づくりこそが、子どもが算数を前向きに続けられる最大のサポートです。
多くの親は、【勉強を見てあげないと】【教えなければ】と思いがちですが、実際に子どもにとって必要なのは教えるよりも支えることの方が大切だったりします。
学びに向かう姿勢や自信を壊さずに支えることが、算数の苦手を防ぐ一番の近道です。
ここでは、家庭学習でとくに意識したい3つのポイントを紹介します。
どれも特別な勉強法ではありませんが、意識する、実践していくことで子どもの【算数は好き】という気持ちを守りながら、確かな学力を積み上げていくことができます。
コツ①100%できるレベルの問題から始める
算数が苦手になる最大の原因のひとつは、できない状態が続くことによる自信喪失です。
子どもにとって、【わからない】【間違えた】という体験が続くと、学ぶこと自体を避けるようになります。
だからこそ家庭学習では、【100%できる問題】から始めることが大切です。
たとえば、前に習った単元や簡単な計算ドリルでも構いません。
【できた!】という成功体験を重ねることで、子どもの脳は学びをポジティブにとらえるようになります。
この【できる感覚】こそが難しい問題に挑戦する力の源になるのです。
さらに、できた問題にはしっかりと褒め言葉を添えましょう。
【やればできるね】【考え方が上手だったね】といった肯定的なフィードバックは、学習意欲を高めます。
逆に、【こんな問題、前にもやったでしょ】などの否定的な言葉は、算数への興味を一気に冷ましてしまいます。
学びのスタート地点は【苦手なところ】ではなく、【得意を伸ばすところ】。
小さな成功体験の積み重ねが、算数を楽しむエンジンになります。
コツ②数年後に伸びると信じて焦らない
算数の力は、一夜にして身につくものではありません。
一度つまずいたように見えても、時間をかけて理解が深まる教科です。
だからこそ、親が焦らずに見守る姿勢がとても大切です。
子どもが間違えたり、できなかったりすると、【もっと練習しなきゃ】【教え方が悪かったかな】と焦ってしまうことがあります。
しかし、算数の学びは理解するまでにかかる時間は個人差があります。
すぐにできなくても、考え方の芽が心の中に残っていれば、後で必ずつながります。
大切なのは、【今は成長の途中】と信じて待つこと。
焦りが親から伝わると、子どもは【できないとダメなんだ】と思い込み、挑戦を避けるようになります。
逆に、【少しずつでいいよ】【昨日よりわかったね】と言ってあげることで、学ぶ姿勢が前向きになります。
算数はじっくり育てる教科です。
焦らず、比べず、見守る。
それが子どもの算数力を確実に伸ばす最良の方法でもあります。
コツ③苦手意識を持たせない親の言動を意識する
算数に対する子どもの印象は、家庭での言葉や態度から大きく影響を受けます。
【ママも算数苦手だったから】【この単元は難しいよね】といった何気ない一言が、子どもに算数は難しいものという思い込みを与えてしまうことがあります。
まず意識したいのは、親の【算数への姿勢】そのものをポジティブにすること。
子どもは、親が苦手だと感じていることには自然と抵抗を持ちます。
【一緒に考えてみよう】【この問題、面白いね】といった声かけで、算数を共に楽しむ時間に変えていきましょう。
また、間違えたときこそチャンスです。
【惜しい!ここまで考えられたのすごいね】と、努力や過程を認めてあげましょう。
結果よりも思考のプロセスを褒めることで、子どもは【考えること自体が楽しい】と感じられるようになります。
親の言葉ひとつで、算数への印象は変わります。
【できない】を責めるより、【やってみよう】を支える。
そんな小さな姿勢の違いが、子どもの算数への向き合い方を変え、長期的な学びの自信につながります。
算数を【苦手】ではなく【得意】に変える家庭の力
算数は、単なる教科のひとつではありません。
論理的思考力、粘り強さ、そして【考えることを楽しむ力】を育てる、すべての学びの基礎となる科目です。
子どもが身につけたその力が将来の進路選択にまで影響することは、決して大げさな話ではありません。
今回見てきたように、算数の分かれ道は小3から始まります。
抽象的な思考を求められ、理解の深さが次の学年の伸びを左右する大切な時期です。
さらに高学年では、計算力・分数や小数の感覚・文章題の読解力といった【質の高い基礎力】が問われるようになります。
そして何より、家庭での関わり方が子どもの算数への姿勢を大きく左右します。
100%できる問題からスタートして自信を育てる、焦らずに成長を待つ、ポジティブな言葉で学びを支える。
この3つの姿勢を持つことで、算数は【苦手を克服する科目】ではなく、【自分の考えを形にできる科目】へと変わっていきます。
算数の学びは、点数のためだけではありません。
論理的に考え、筋道を立て、諦めずに解決する力を育てるプロセスです。
その力は、将来どんな道に進んでも、確かな生きる力となります。
親ができる最も大切なことは、【算数を一緒に楽しむこと】。
苦手を恐れず、できた瞬間を一緒に喜ぶという積み重ねが、子どもの学びの土台を確かなものにしていきます。