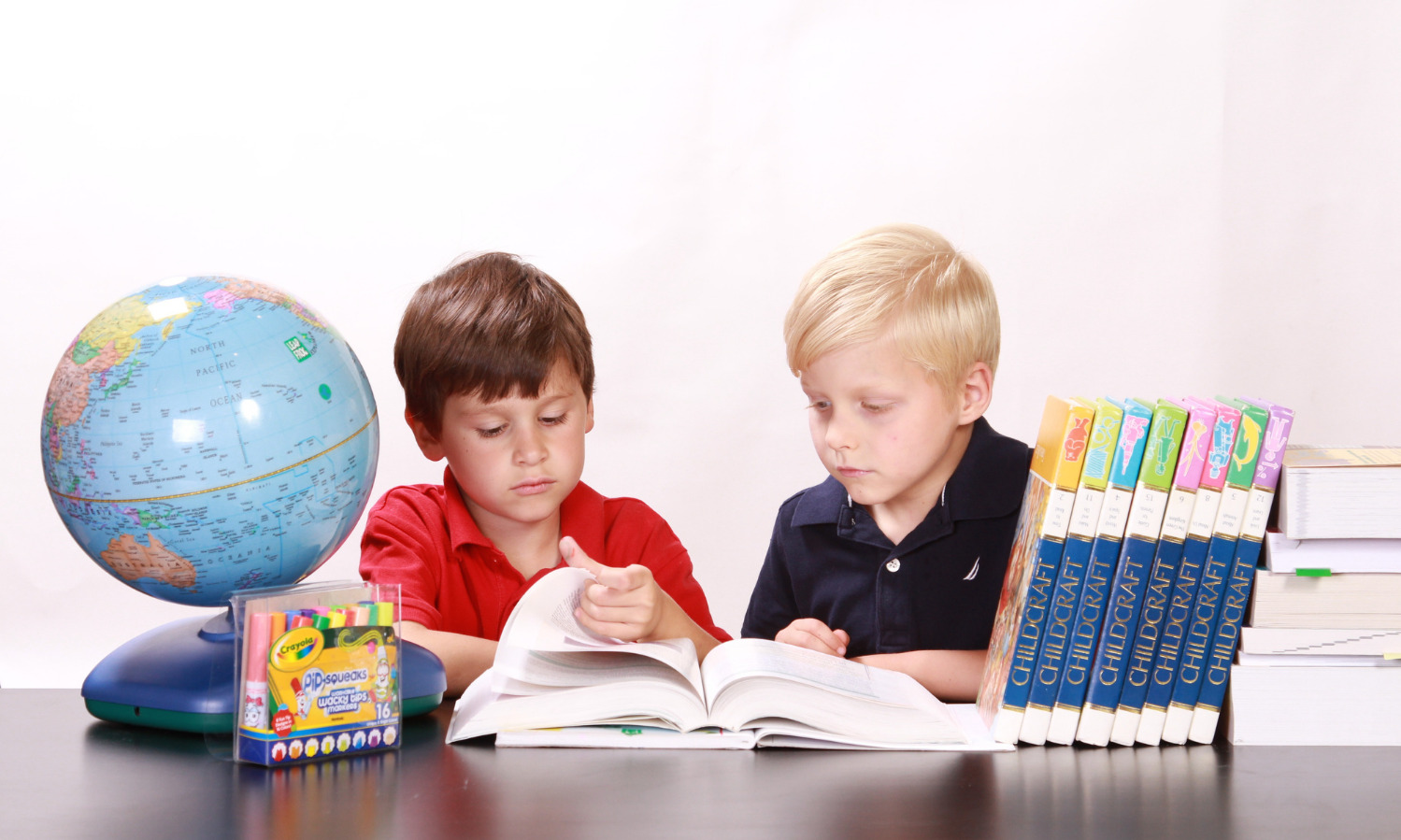今回は【地方から旧帝大 地方在住組のための戦略的進路設計とは】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
地方に住んでいても、東大、京都大を筆頭とした旧帝大に現役で合格する子は存在しています。
たしかに、小学生の時から他の子とは明らかに違う賢さを発揮していましたが、同じくらい賢い子でも進級進学の途中で伸びが鈍くなり、力尽きる子もいたので、東大や京都大の医学部医学科を除けば【選びぬかれた子しかたどり着けないというわけでもない】という見方もできます。
ただ、【地方に住んでいるから、旧帝大なんて無理じゃないか…】
そう感じている親は少なくありません。
しかも、軽々しく【旧帝大を目指しているんです】と言えるような雰囲気ではないです。
大都市圏のように塾や情報が豊富な環境ではない地方、中学受験組も多くはない地方では、【高校受験をして大学受験をする】が一番多いパターンです。
令和の今も大都市圏に比べれば、進学における情報格差や学習機会の格差が存在するのは確かです。
しかし、その中でも確実に旧帝大に合格している生徒たちは存在します。
しかも彼らの多くは、中学受験をせず、学区の公立中学から地域の進学校に進み、最終的に旧帝大に合格しているのです。
地方在住の子どもにとって大切なのは、【今いる場所でどう積み上げるか】という視点になります。
特別な環境や施設がなくても、家庭主導の学習、タイミングを見た塾利用、そして戦略的な高校選びを組み合わせることで、旧帝大にチャレンジできる学力を十分に育てることは可能です。
特に重要なのは、小学校高学年からの意識の持ち方と学びの習慣化だと個人的に感じています。
この時期に、自分で学ぶ力や基礎的な思考力を身につけておけば、中学校でも最上位層に入りやすく、高校受験や大学受験に向けての土台が自然と築かれていきます。
そこで今回は、地方に住んでいる子どもが【塾の数や環境に左右されず、地元の学区中学でもトップを取り、進学校から旧帝大へ進む】ための進路設計を、3つの柱でご紹介します。
小学校高学年から始めるべき家庭学習の戦略、学区の公立中学でもトップ層を維持するための具体的な方法、そして進学校選びと高校での過ごし方を通して、旧帝大への道筋を明確にしていきます。
どこに住んでいても、準備と継続があれば、子どもの可能性は無限大に広がります。
小学校高学年で差がつく!地方での【家庭主導型】学習法
まず、小学校高学年、特に小5年生、6年生の時期は、学力の土台が固まり、思考力や読解力が大きく成長する重要なタイミングです。
この時期に学び方を会得できるかどうかが、その後の中学、高校、そして大学入試にまで影響します。
大都市圏では中学受験を通して自然にその力が養われるところもありますが、地方では中学受験する子が少なく、多くの子どもたちは学区の公立中学へ進みます。
ですから、小学生の間は塾に通って学校以上の勉強をする子というのはかなり限られています。
その分、小学生時代は家庭で基礎力を積み上げていく【家庭主導型】の学習がとても重要になります。
大都市圏と地方との教育事情の違いを理解し、旧帝大を目指すのであれば【小学校高学年は未来の進路を決める重要な時間】と定めて戦略を立てることが必要になります。
この時期に子どもたちの間で差がつく最大のポイントは、【学習習慣】【読解力】【思考力】の3つです。
子どもが本格的に抽象的な思考を始めるのは小学校中学年からです。
ここで語彙力や文脈理解力、数的思考のベースをしっかり鍛えておくと、中学に入ってからの数学・国語・理科での理解がスムーズになります。
逆にこのタイミングでの積み上げを怠ると、【文章を読めない】【問題の意味がわからない】といった躓きに直結しやすくなります。
中学受験をしない場合、小学校のラスト2年間は時間的に非常にゆとりがあります。
塾に時間を取られることなく、家庭でじっくり学ぶことができるという意味で、5年生、6年生は地方の子どもにとって学習の中身を見直す最大のチャンスともいえます。
ただし、 【中学受験しない=油断していい】ではないことを肝に銘じてください。
地方では【中学受験をしない=受験勉強は中学から】という空気が根強いですが、これは非常に危険です。
我が家では、私の経験や塾で出会った色々な子ども達の成長を見ていく中で【受験はしないけれど受験算数を学ばせた方が有利】という考えで小学生から塾通いをさせました。
結果として子ども①②は受験をしましたが、大都市圏の子と大学受験で相まみえる将来を考えると【何も考えずにのんびりと過ごす】ということは怖くてできません。
ましてや、旧帝大を目指すような家庭では、高校入学時点で中学受験組に負けない相当な基礎学力と学習習慣が備わっている必要があります。
その準備は中学からでは遅く、小学生のうちからコツコツと積み重ねていく必要があります。
実際、旧帝大に合格している地方出身者の多くは、中学受験経験はなくても、小学生から地道に学習習慣を築いてきた子ばかりです。
私の同級生や先輩や後輩、そして塾で出会った子どもたちを見ても、例外なく小学生の頃からしっかり勉強していました。
現実的に家庭で子どもの学習を支える場合、やはり【学習環境】と【親の関わり】が最も大切なポイントになります。
何より重要なのが【日常の中に学習の時間を組み込むこと】です。
スマホやゲーム、テレビに接する時間を適度に制限し、【毎日この時間は学習時間】と決めるだけでも子どもは落ち着いて取り組めます。
また、内容面では音読、計算、漢字練習といった地味だけど確実な力を育てる学習を習慣化することが大前提です。
基礎力の向上に直結する勉強を蔑ろにすると、将来の読解・記述・計算力に確実につながります。
親と子の関わり方も重要です。
【勉強した?】と尋ねるだけでなく、学習内容を一緒に確認したり、テキストを音読し合うなど、共に過ごす学習時間が、子どもの意欲を高めます。学びを【家庭内の日常】にしていく工夫が求められます。
家庭で盤石な学力を鍛えていくための教材選びについては、無理に高難度のものに取り組ませる必要はありません。
むしろ【ちょうどよい難易度】【ほんの少し背伸びをする問題がある教材】に取り組ませることを継続する方が、力になります。
おすすめは以下のような組み合わせです。
私の周りでも進学校に進学した子が、小学生時代に利用していたという話をよく耳にするZ会の通信教材は記述力、思考力をバランス良く鍛えられます。
中学受験するわけではなくても、幅広い知識を得るために小学生新聞を取ったり、やはり読書を通じて語彙力や背景知識を自然に育てることも意識してください。
そして、市販のドリルや問題集はくもんや学研などの歴史ある教材だと、苦手克服シリーズなどピンポイントで鍛えたい単元がある時に上手に活用したり、教科書ワークなどで基礎力の反復と定着していくというのも小学生の間に学力のジャンプアップする時にしっかり伸びるための準備をしていくのもおすすめです。
賛否両論ありますが、図形や実験の手順などを理解するのに役立つYouTubeの教育系チャンネルを視覚で理解する補助教材として活用するのも時代に即した学び方でもあります。
これらをベースに、週ごとの学習スケジュールを家庭でざっくり立て、終わったらチェックを入れるなどの【見える化】も有効です。
【やらされる学習】から【自分で管理する学習】へ、意識を徐々にシフトさせていくことで、今後の自学力の芽を育てていくことができます。
このように、小学校高学年のうちに【学びの習慣】と【自分で考える力】を育てておくことで、中学に入ってからの学力の伸びが大きく変わってきます。
中学は学区内でもOK!最上位層であり続けるための戦略
さて、旧帝大進学を視野に入れると、【中学受験をしなければ不利なのでは?】と不安に思う方も多いかもしれません。
しかし、地方では中学受験を行わずに、学区の公立中学から難関国立大学へと進むという子もしっかりいます。
ポイントは、中学に入ってからいかに最上位層であり続けるか。
ここでは、地方の学区中学でトップを維持し、進学校や旧帝大に繋がる土台を築くための戦略を紹介します。
まず押さえておきたいのが、【公立中=不利】ではないということです。
通学のしやすさや生活リズムの安定、小学生時代からの人間関係の継続性など、余程問題を抱えた地域でなければ、学区内の公立中学にもメリットはあります。
また、地方の公立中学校では、成績上位者に対して【あの子はスゴイ子】という存在感が際立つため、子ども本人も優等生としての自覚を持ち、自信をもって学校生活を送れることも期待できます。
何より、環境を変えずに中学生活にスムーズに入れるというのは、学習に集中しやすい土台になります。
無理に遠方の私立中学に進学して通学で疲れ切ってしまうよりも、地域とのつながりを保ちつつ、日々の学習に力を注げる環境は、かえって大きなアドバンテージになることもあります。
将来的に旧帝大を目指す中で、学区内の公立中に進学する際に大切なのが、【常に学年トップを目指す】という明確な目標を持つことです。
成績上位者であることには、いくつものメリットがあります。。
学年上位であれば、学校の先生からの信頼も厚くなり、私立の進学コースの推薦枠や教育相談などのサポート体制においても学年随一の優等生ということで何かと気にかけてもらえるなど、有利になることがあります。
また、学年1位であることは、子どもにとって強い自己肯定感と学習意欲を生みます。
【努力すれば結果が出る】という成功体験は、後の高校・大学受験においてもモチベーションの源泉となります。
中学3年間は入学したと思ったら気がついたら受験が迫るという感じで、時間との勝負になります。
【慣れるまで様子見】とならないよう、学習方針を決めてしっかり定期テスト対策をして、可能であれば先取り学習をしていくのが安定した成績を残すためには不可欠です。
学区の中学で最上位を維持するためには、3年間の学習方針を意識的に組み立てていきましょう。
最初のカギは、【定期テスト対策の徹底】と【先取り学習のバランス】です。
定期テストでは、学校の教科書やワークから出題されるため、そこをしっかり押さえる意識を持つよう家庭でも話をしてください。
その一方で、学校の授業進度に合わせるだけでは、難関高校や旧帝大に必要な学力を十分に育てるのは難しい側面もあります。
そこで必要なのが先取り学習です。
特に数学・英語は中1の段階から中2・中3の範囲を少しずつ先に進めておくと、定期テスト対策にも余裕ができ、応用問題への対応力もつきやすくなります。
この先取りを効率的に行うには、塾で最上位クラスに入ることや市販の教材で子どもが自発的に予習をしていくのが理想的です。
地方で塾に入るタイミングは親世代の頃は中学2年生の秋くらいから3年生になるタイミングが多かったですが、今では学区の中学に進学する子でも【小学校高学年くらい】という子もいます。
どのタイミングがベストかというのは断言できない難しさがありますが、家庭だけでの学習に限界を感じたら、塾の活用を検討するタイミングです。
おすすめは【小6の春〜中1の夏休み前】の間に入塾を済ませておくと、部活と勉強の両立ができるようになります。
この時期に入っておくことで、中学校の先取りや学習スタイルの確立を早期に行うこともできます。
地方では都市部のように大手塾が選び放題という環境ではありませんが、地域密着型の塾には、その土地に合わせた高校受験のノウハウが蓄積されています。
とくに【上位高校への合格実績】【大学入試の合格実績でも結果を残している】という塾を選ぶことが重要です。
体験授業を受けて、先生との相性や指導スタイルも見極めましょう。
私も経験していますが、地方にいると、【自分がどのくらいの学力なのか】が見えづらくなりがちです。
学校の成績だけでは全国レベルでの自分の位置は測れません。
そこで重要なのが、全国規模の模試を受けることです。
駿台中学生テストなど、全国の受験者を対象とした模試を年に数回受けておくと、地方の学区中学にいながらも、自分の実力を客観的に把握することができます。
模試を受けることで、【井の中の蛙】にならず、常に広い視野で自分を見つめ直す姿勢が育ちます。
駿台中学生テストは自宅受験も可能です。
我が家の子ども①②も受けて、全国レベルとの違いを強烈なくらい知って、【上には相当かなりいる】という事実を中学生の頃から気づくきっかけにしています。
こうした模試での偏差値は、高校選びや大学入試の戦略にも役立ちます。
資料などから【自分の地域のトップ高校は全国的に見たらそんなに高いわけではない】を把握することもできます。
学区中学であっても、戦略的に学習を進めていけば、トップ層を維持し、進学校や難関大学へとつながる力をしっかりと育てることが可能です。
トップ高校でもトップ層に!大学入試まで見据えた戦略的選択
ところで、地方から旧帝大を目指すのであればトップ高校でもトップ層にいるというのが鉄板です。
学区の中学でトップ層を維持した先に待っているのが、高校受験です。
地方における旧帝大進学のカギを握るのは、【どの高校に進むか】と、【その高校でどう過ごすか】の2点です。
トップ高校への進学は通過点に過ぎず、その中でトップ層に入り続けることで、旧帝大レベルの学力と実力が備わっていきます。
順調に中学生生活を送り、高校受験に挑む時も、親は決して高校受験をゴールにしないでください。
高校受験、高校入学はあくまでもスタート地点です。
地方の進学校に合格した時点で、【とりあえず安心】と感じるご家庭も多いですが、旧帝大を目指すのであれば、ここからが本当の勝負です。
進学校に入ると同級生の学力レベルも高く、予習もせずに中学生時代の感覚で受け身で授業を受けているだけでは、すぐに成績が中〜下位に落ちてしまうこともあります。
そのため、合格後も【燃え尽きない】意識と、継続的な学習習慣が必要です。
子ども①も塾の先生から【大学受験は高校受験よりも勉強する意識を1年生からずっと持ち続けて実践してそれで全国のライバルと同じ土俵に立てる世界】と言われ続けていて、ビビっていました。
地方育ちの子は、世界が狭い中で成長するので【高校に合格したら人生バラ色】にならないように親も気をつけてください。
地方で旧帝大を目指すなら、基本的にはトップ高校に入るのが鉄板です。
ただ、大学合格実績に力を入れている私立高校も地方には存在しているので、【伝統ある公立高校か手厚いサポートが期待できる私立の進学コースか】の二択になると思います。
子ども①の同級生にも後者を選んだ子がいましたが、地方で私立の進学コースに入ると部活動に入れない可能性もあるので、勉強一辺倒ではなく部活も頑張りたいという子は不向きです。
私立の進学コースに入り、指導が厳しくて退学する子もいるので、そこは軽い気持ちで受験校を決めることのないように気をつけてください。
そして、進学先の高校を選ぶ際には、【旧帝大への合格者数】や【現役合格率】などの実績を参考にするのはもちろんですが、それ以上に重要なのが、【学びに対する空気】です。
たとえば、同じ進学校でも、校風や生徒のモチベーション、教師の姿勢によって、学力の伸び方に大きな違いが出ます。
自習室の有無や、課題の質と量、模試の実施頻度なども確認ポイントです。
また、指定校推薦枠が多い高校では、一般入試よりも推薦に流れる傾向が強く、大学受験への本気度が薄い場合もあるため、志望大学の入試方式との相性も考慮に入れましょう。
晴れて希望通りの進学校に入ったからといって安心してはいけません。
中学まで成績が良かった子でも、高校1年生の序盤で大きく躓くケースがあります。
とくに数学や英語は、進度も速く、内容も抽象度が一気に上がるため、授業にただついていくだけでは間に合わなくなることがあります。
このギャップを埋めるには、中3の冬から高1の夏にかけて、高校範囲の先取り学習や復習の仕組みを家庭内でも整えておくことが有効です。
我が家の子ども①の周囲にいる神童さん達は、中学1年生で中学校3年間の数学の先取り学習を終わらせ、中学3年生では受験対策もしつつ高校数学の予習を進めていました。
高校に入る前には青チャートの数ⅢCまで一通り終わらせているという状態に仕上げている子も複数人いました。
子ども①は受験が全て終わった日から高校数学の予習をスタートしましたが、中学生の感覚のまま春休みを過ごし、4月になって高校の授業がスタートしたと同時に高校数学の勉強をする同級生もいました。
このように地方でも先取り学習、予習に対する考え方はかなり違いがあります。
大学受験を控えているなら、やはり予習をしていないと旧帝大を目指すのは難しいですし、実際高校入試の時点ではさほど開きのなかった学力差は1年を過ぎると先取り学習の有無で相当広がります。
地方から旧帝大を目指すなら高校内容の先取り学習はもはや絶対条件です。
また、地方では塾に通うのは高校受験のためという考えが根強いですが、今では進学校を中心に高校に入った段階で、塾や予備校をどう活用するかも重要な戦略になっています。
地方には大手の予備校、塾が少ない場合もありますが、映像授業を使えば、自宅にいながら大都市圏の子と同じレベルの学習が可能です。
ただし、高校生活では部活や行事なども多く、時間の管理が難しくなるため、最終的に求められるのは【自走力】、つまり【自分で計画を立て、実行し、振り返る力】です。
この自走力を早くから育てるためには、中学時代からの自学の習慣が大きく影響します。
計画的に学び、模試での結果を分析し、自分の弱点を補うというPDCAサイクル、計画、実行、評価、改善、を日常的に回せるかどうかが、旧帝大合格の分かれ道になります。
進学校に合格しただけでは終わりません。
その中でいかに【上位に食い込むか】が、旧帝大の合否を左右します。
地方に住んでいるからといって、旧帝大合格が不利になるわけではありません。
むしろ、大都市圏ほどの過熱した受験競争がない分、自分のペースで着実に学力を積み上げていけるチャンスがあります。
小学生のうちに学習習慣と基礎思考力を身につけ、中学では最上位層を維持する。
高校では【自分で学び、自分で考える力=自走力】を育てることで、難関大学に通用する本物の学力が磨かれていきます。
重要なのは、塾や学校環境に依存するのではなく、戦略的にステップを踏み、日々継続する力を育てることです。
旧帝大合格は、特別な環境ではなく【意識】と【積み重ね】で決まります。
どこに住んでいても、明確なビジョンを持ち、家庭と本人が一体となって取り組めば、その夢は確実に現実のものになります。